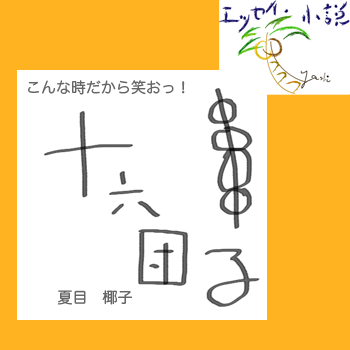★最後はこうなります。ここまで読んでいただいてありがとうございました!(作者注釈)
第2部〜第4章(最終章)『終わりの始まりの終わり』
1『雨の早朝念仏』
ホゲゴッゴー!
貫太郎の家のニワトリが鳴いている。
午前6時。
この時期にしては暗い朝だった。小降りになったとはいえ雨はまだ降り続いていた。
薄暗がりの貴志の家の前の道には、傘をさした村人が30人ほど集まっていた。彼らは頭に五徳こそかぶっていないものの、一様に厳しい表情を顔に浮かべ黙って立っている。手に数珠と『西国三十三所御詠歌』と書かれた小さな冊子を持って。
「さて、行くかの」
作之進はみんなに向かってそう言うと、ぬかるんだ道に杖をついて歩き出した。村人たちは黙って後に続いた。
「ごーめーん!」
作之進が玄関から声を掛けた。しばらくしても誰も出てくる気配がない。
「ごーめーん!」
作之進はもう一度大きな声で叫ぶと、玄関の戸に手を掛けた。
「はあ」
作之進は隣にいる松吉を見た。
「なした? 開がねが?」
金歯の松吉が言った。
「どれ」
松吉は玄関の戸を乱暴に開けようとした。
「鍵掛がってるな」
その声を聞いて、後ろにいた村人の何人かが前に出てきた。
「何だど!」
歌子だった。歌子は、玄関の磨りガラス越しに中をのぞき込んでいる。その隣に進み出てきたミセスホーメンが後ろを振り返りながら先生口調で言った。
「誰か、勝手口に回ってみなさーい!」
その声に反応したのは禿頭の竹信だった。竹信は水たまりを跳ねるようにして勝手口に向かった。
「こっつも開がねえど!」
竹信が勝手口から大きな声で叫んだ。
「何だど!」
「あいづらいねえのが!」
「何のまねだ!」
村人たちから罵声が上がった。
「何とす?」
松吉が作之進に言った。
「はあ」
作之進はそう言って、口を開けたままグルリ村人たちを見回した。
「全部だ、全部。どごも開がねえ。便所の窓さまで錠掛かってるど」
戻ってきた竹信が息を切らしながら言った。
葬式の次の日から家を留守にしているということ自体、村人には信じがたいことであったが、それ以上に普段留守のときでも家に鍵を掛ける習慣のない村人にとって、家に施錠しているというこの行為は、ことさらに彼らの気持ちを逆撫でした。貴志たちが意図的に自分たちを排除したのではないかと思った。
「何とす?」
松吉がまた聞いた。村人たちもジッと作之進を見詰めている。
「こごでやるしかないの」
作之進はきっぱりとそう言うと、松吉に向かってうなずいた。松吉は、風呂敷に包んで持ってきた鉦を出して、玄関の戸に向かってそれを鳴らした。
ジャリーン!
ホゲゴッッゴー!
その音に驚いたニワトリが鳴いた。
作之進が御詠歌の音頭を取った。
補陀洛や岸うつ波は三熊野の
那智のお山にひびく滝つせ
村人たちが唱える念仏は、そぼ降る雨の音と混ざり合いながら7時過ぎまで続いた。それは、しめやかと言えば実にしめやかなものではあった。
ジャリーンッ!
松吉が鉦を打ち念仏が終わった。
作之進はゆっくりと玄関の戸に向かってお辞儀をすると、村人のほうに向き直って、
「みんな、ご苦労じゃった」
と言って頭を下げた。
村人たちは帰り支度を始めた。
「誰か貴志の電話番号を知らんかの?」
彼らの背中に向かって作之進が聞いた。
「作じいが知らなけりゃ、誰も知らんべよ」
「ああ、おらだぢさ聞いだってダメさ」
村人が答えた。
「それにすてもたまげだなあ」
「ああ、こんたごどはあったもんでねえ」
「賢しい人っつうのは違うなあ。考えてるごどがよう」
「バヂ当だる、バヂ当だる。おお、おっかねえ」
村人は、貴志たちへの怒りと嫌みを込めた言葉をめいめいに吐きながら雨の中を帰っていった。
作之進はみんなが帰るのを見送ってから、杖をついてゆっくりと歩き出した。彼が向かったのは自分の家ではなかった。
△このページのトップへ
2『作じい怒る』
「そろそろ行かなきゃ」
彩はエプロンを手に持って出掛ける支度をしている。
「うん、俺も後から行くから」
周平は流しで洗い物をしている。
「了解、そういえば念仏やったのかなあ」
「ああ、五徳をかぶって・・・」
周平がまた横溝正史調に言う。
「こわーい!」
彩が大げさに怖がる。
「ははっ、とにかく頑張って!」
「うん、じゃあね」
彩が勝手口の戸を開けた時だった。
「わっ!」
目の前に作之進が立っていた。
「あっ! おは、おはようございます!」
「はあ、どうしたのかの?」
「あっ、ええ、今から金蔵さんの家に手伝いに行くんです」
「おお、そうか、そうか。ご苦労じゃの」
「いえいえ、作之進さん、あのう、周平ですか?」
「ああ、実はな、ちいと聞きたいことがあってな」
「じゃ、ちょっとお待ち下さいね」
彩はそう言って周平を呼びに行った。
周平がやってきた時、作之進は上がりかまちに腰掛けていた。
「あっ、作じい、どうぞ中に」
周平が言った。
作之進は手を少し挙げて、
「いやいや、ここでいい。ちょっと分かれば教えてもらいたいんじゃが」
と言った。
「何でしょう」
「貴志の家の電話番号知っとるか?」
「貴志さんの向こうの家ですか?」
周平と彩はお互いに顔を見合わせた。
「電話はちょっと・・・なあ、彩」
「ええ、ケータイとかも・・・ねえ」
作之進は少し困った顔をして、
「そうか、分かった」
と言って立ち上がった。
「でも、『北都新聞』に電話して聞けば美樹さんのなら分かるかも」
彩がひらめいたように言った。
作之進は黙って彩を見詰めた。
「何かあったんですか?」
周平が聞いた。
「いや、あいづにひと言、言っておきたいと思ってな」
「えっ?」
「貴志は・・・実に・・・バガ者じゃ!」
作之進のこめかみがピクピク脈打っているのが分かった。
こういう作之進を見るのは2人とも初めてのことだった。
「どうしますか? 聞いてみましょうか?」
彩が恐る恐る聞いた。
「それには及ばん」
作之進はそう言って、いつもの穏やかな表情になると、
「邪魔してすまなかったの、タマヨの力になってやってくれ」
と彩に言った。
彩はニッコリ笑ってそれに応えた。
「周平、すまんが一緒にまた触れを頼むな」
作之進はそう言って杖をついて歩き出した。
△このページのトップへ
3『ジャパンペット成仏堂』
「この度は大変ご愁傷様でございました。『ジャパンペット成仏堂』の加賀美と申します」
加賀美と名乗る男は、そう言っていんぎんに名刺を差し出した。
彼は役場の土木課が着ているような作業服を着、ゴシック体で『加賀美』と書かれたネームプレートを付け、役場の住民生活課の主任クラスのような没個性的な顔をし、役場の福祉課が応対するときのような少しも役には立たないが、かといって特別感情を逆撫でするわけでもないしゃべり方だった。
つまりは、どこからどう見ても「私はフツーです」といった雰囲気を体全体ににじませていた。もっと言えば「私は絶対に怪しい者ではありません」を絵に描いたような男だった。
(あっ、大丈夫です。社名なども入っていない地味なクルマですので、目立って怪しまれるようなこともありませんし、担当者もよく心得ておりますから)
美樹はそう言ったオペレーターの言葉を思い出した。
「あっ、どうも、宮下です」
貴志が名刺を受け取ると、加賀美は隣にいる美樹に向かって頭を下げた。
「では、早速これからペット様の火葬をさせていただきますがよろしいでしょうか?」
彼は役場のまちづくり課のような、ちょっとだけへりくだった口調でそう言った。
「はい、お願いします」
貴志が答えた。
「では、出棺の儀式を執り行いますので、失礼します」
加賀美は役場の税務課が延滞税を回収するときのような、ちょっとだけ威圧的な口調でそう言って靴を脱ぐと、
「どちらでしょうか?」
と言った。
「あっ、こちらです。そうぞ」
貴志が加賀美を案内した。
ジャムはダイニングテーブルの上に安置されていた。
加賀美は発泡スチロールの箱の前に立った。そして、手を合わせて静かに目を閉じた。
箱の前に置かれたマフラーの色と、加賀美の着ている作業着の色がお揃いだった。
美樹はわけもなく不快な気分になった。
加賀美は美樹たちに向き直って言った。
「では出棺となります」
(もう?)
「お聞きかと思いますが、当社は『完全個別立ち会い火葬』になっております。私がこの箱をお持ちしますので宮下様も私の後に続いてください。火葬車は駐車場の目立たない所に止めてあります」
加賀美は発泡スチロールの箱に手を掛けながらそう言った。
3人は無言のままエレベーターに乗った。11階からきれいな身なりのおばさんが、4階から幼稚園児と手をつないだお母さんが乗り込んできた。
「ママ、マサオちゃんのお母さん何て言ってた?」
園児が貴志たちにチラッと目をやりながら聞いた。
「何って? もういじめませんって言ってたわよ」
「ホント?」
「そうよ、だから心配しなくても大丈夫よ」
「そう」
「あっ、ユウカ、マスク持った?」
「うん」
園児はボケットからマスクを取り出した。
「マスクしてね。それからお手ても洗うのよ。ゴロゴロもね」
母親は子どもに新型インフルエンザ対策の指導をしながら、貴志たちを横目でチラッと見た。
加賀美は箱を持ったままジッとエレベーターの隅に立っている。誰も怪しんで彼を見る者はいない。
(宅配屋に成り済ましている。完璧だ!)
貴志は思った。
火葬車は確かに目立たない所にあった。
マンションの駐車場は建物の三方を囲むようにして『コ』の字型に配置されていて、その周りは雑木林と芝生になっていた。そのさらに外側は日本海だ。クルマが止まっていたのは、分かりやすく言えば『ゴ』の字の点々に当たる部分である。そこはうっそうとした雑木林の中だった。
(しかし・・・)
駐車場を歩きながら貴志は思った。
(これじゃ、かえって目立つんじゃないのか?)
加賀美の後についてその場所まで来た時、貴志は何となく気まずいものを感じた。美樹も同じだった。
(何かしてはいけないことをしている)
貴志はキョロキョロと辺りを見回した。
見覚えのある主婦の姿が遠くに見えた。
(こっちを見ている)
そんな気がして、貴志は慌てて茂みの陰に隠れた。
加賀美はクルマのエンジンをかけると2人に向かって、
「では、お別れになります」
と言った。
クイーンッ!
静かに火葬車の扉が開いた。
貴志は一瞬、2日前の火葬場でのことを思い出した。
(あれは失敗だった)
貴志は思った。
(これも焼き加減の調節って可能なんだろうか?)
貴志はフトあらぬことを考えた。
(もし可能だとしたら・・・)
貴志はズボンのポケットをまさぐった。
(この人も賄賂を求めるだろうか?)
貴志はそこに財布があることを確かめた。
(でも待てよ)
貴志は財布を握りしめながらまた考えた。
(そもそもネコにのど仏などあるのだろうか?)
貴志はポケットから手を出し、その手で自分のほっぺたを2回叩いた。
「発泡スチロールは煙が出ますので、ご遺体だけお入れします」
加賀美はそう言って発泡スチロールのふたを開けると、ジャムを持ち上げて金属製の台の上に載せた。
「ジャム・・・」
美樹は、手を伸ばしてジャムの体に触った。ジャムの体は死後硬直が進んで置き物のように堅かった。
「では、よろしいでしょうか?」
加賀美が言った。
貴志は美樹の顔を見た。美樹は「うん」とうなずいた。
「お願いします」
クイーンッ!
扉が閉まった。
「では、着火します」
加賀美は扉の脇に付いている小さなボタンを押した。
バホッ!
アイドリングの音が少し大きくなり、やがて上部の短い突起から薄い煙が立ち上った。
「この大きさですと30分から45分かかりますので、その間お部屋に戻っていただいても結構です。終わったらお呼びしますので」
加賀美はそう言った。
「じゃあ、いっぺん戻ってます」
貴志が美樹に目配せしながら言った。
「あっ、この箱どうしますか? 不要であればこちらで処分しますが」
「ええ、そうしてください」
貴志と美樹は、駐車場を横切ってマンションのエレベーターへと向かって歩き出した。途中、さっき貴志たちを見ていたおばさんと行き違った。おばさんは訝しげな目でに2人を見ていた。
マンションの3階のベランダで洗濯物を干していた主婦が、火葬車のあるほうに目をやっていた。
貴志が振り返ると、その辺りから焚き火程度の煙が出ているのが分かった。
「あれってかえって怪しいよな」
エレベーターのボタンを押しながら貴志が言った。
「いっそ焼き芋屋にでも変装してくれればいいんだよ」
「うん」
「そういえばゴリラも焼けるって言わなかった?」
「うん、パンフレットにはライオンも」
「ってことは人間も焼けるんじゃないのか?」
「機能的には、たぶん」
チンッ!
エレベーターの扉が開いた。
22階、ボタンを押しながら美樹が言った。
「証拠隠滅」
「うん、殺人犯が死体を包んで『これ、ゴリラです』って言って、何か袋に入れてここにお願いすれば・・・」
「完全犯罪成立!」
チンッ!
扉が開いた。
「こういうのってどうなんだろうね」
「えっ?」
「番号札持ってハンバーガー待ってるみたいでさ」
「うん」
「コインランドリーの中で洗濯物乾くの待ってるみたいでさ」
「うん」
「味気ないよな」
「でも・・・」
ドアのノブに手を掛けながら美樹が言った。
「かえってこのほうがいいよ」
△このページのトップへ
4『謎の倒木』
パトカーはサイレンを鳴らしていなかった。
「エアコンさっぱ効がねなあ」
佐々木巡査はそう言ってギコギコと窓を開けると、二重あごのくぼみにたまった汗をハンカチで拭いた。
「ガスねえんだす」
運転席の渡部巡査は32歳、佐々木巡査とは干支ふた回りも歳が離れている。
「エアコンのガス代は落ぢねえのが?」
「無理だすぺ。事業仕分げ、経費節約っつうご時世だすから」
渡部はそう言って計器パネルのオドメーターに目をやった。総走行距離は25万キロを超えていた。
「誰がら電話だった?」
佐々木が聞いた。
「分がらねっす。聞ごうど思ったら切っちまったんだす」
「3人ともが?」
「んだす」
パトカーは、愛宕村の入り口に差し掛かった。
「ほう、全員名無しのタロベエだが?」
佐々木はそう言って窓の外を眺めた。
「んだす。ただ『木、邪魔んなってクルマ通られねえ』っつう話だったす」
「ほう」
渡部が愛宕村のメインストリートに入ろうと左にハンドルを切った時だった。
キーッ!
彼は急ブレーキを掛けた。佐々木巡査の巨体がフロントキャビネットにつんのめった。
ギーッ!
チョロQの赤いトラクターも急ブレーキを掛けた。
2台は鼻先スレスレのところで止まった。
渡部は車内からトラクターの運転席を見上げた。
「ぶつかってねえべ?」
「当だってねっす」
渡部はトラクターが少しバックしてくれることを期待したが、運転手はなかなか動こうとしない。
「何だべ、下がってければいいべっちゃな」
渡部はそう言ってドアを開けて外に出た。
「すいませーん、ちょっと下がってもらえねすべが?」
警察帽に片手を掛けながら渡部巡査が言った。
「・・・」
「悪いども、ちょっと・・・」
「・・・」
チョロQはワナワナと震えていた。大きく開けた口の奥で喉ちんこまでプルプルと震えていた。
「よう、大宮さん!」
佐々木巡査がチョロQに声を掛けた。
その声にハッと我に返ったチョロQは、佐々木巡査に向かって笑顔を向けた。
「頑張るなあ、いやあ、悪がった、悪がった。仕事の邪魔したなあ」
佐々木巡査がそう言って頭を下げると、チョロQは大きくうなずいてギアをバックに入れた。
ピーッ、ピーッ、ピーッ、ピーッ・・・。
トラクターを道の端に寄せてくれたチョロQに、
「ありがどう!」
と佐々木巡査は言って渡部巡査に通るように手を振った。
「とごろ大宮さん、宮下貴志っつう人の家はこの辺りがね。住民票さも警察の調査表さも載ってねえんだや」
佐々木巡査はトラクターに寄り掛かりながら聞いた。
「ああ、そごの角右さ曲がって30間ばがり行った右側の家だ。貴志は梅松どかなめの息子だ」
チョロQが美しいバリトンボイスで答えた。
佐々木巡査は大きくうなずいた。
「何があったのかい?」
チョロQが聞いた。
「いやあ、警察さ電話あってさ、道ばたさ木倒れで通行でぎねえっつうごどだったんだが」
「ああ、確かに松の木倒れできてるども通行でぎねえってほどでもねえよ。今のどごはな。おらも今通ってきたどごだ」
「そうが、じゃあまあ、ちょっくら見でくるわ」
「ああ、本人留守だったら本家の作之進さ聞げばいい」
「そうが、ありがどな。いやいや、邪魔した、邪魔した」
佐々木巡査はそう言って手を振ってパトカーに乗り込んだ。
赤いトラクター上のチョロQも会心の笑みを浮かべてパトカーに手を振ると、慎重に角を曲がっていった。
「ああ、あれだな」
前方右側にその木はあった。根元から1メートルぐらいのところで無惨に断裂し、道側に向かって倒れ込んだ木は垣根に引っ掛かる形で留まっていた。上部が3メートルばかり道にせり出していたが、チョロQの言った通り今すぐ通行に支障があるわけではなかった。
「夕べの嵐で倒れだんだべ」
佐々木巡査はそう言ってクルマを下りると、折れた老木を見上げた。
「樹齢5〜60年はあるすぺ?」
渡部巡査は折れた箇所を見ながら言った。
「ああ、しかしこれが折れるどはなあ」
そう言って垣根の中をのぞいた佐々木巡査の目が、木の付け根の辺りに留まった。
「おや?」
「えっ?」
「あれ見ろ!」
「あっ!」
倒れた木の付け根の地面に、くっきりと足跡が付いていた。
「人の通り道でもねえのに何でだべ?」
「しかも裸足でねえすか?」
「ああ、小さいのど大きいのがある。男ど女だべな」
「んだすな。かなりめり込んでるどご見るど・・・」
渡部巡査の目が光った。
「うーん・・・」
佐々木巡査は二重あごに手を当てた。
「匿名電話どいい、この足跡どいい、何が臭うな」
佐々木巡査の顔が刑事コロンボの顔になった。
「事件だすな!」
渡部巡査の目がキラッと輝いた。
警察歴14年、彼が今まで関わった事件といえば、隣の家のニワトリの鳴き声がうるさいとか、隣の家のじいさんが道ばたに痰をして汚いとか、隣の家の『ミズたたき』の音がうるさいといった、さもない相隣トラブルばかりだった。
ちなみに『ミズたたき』とはウワバミソウの茎を包丁などでトントントントンと1万回も叩いてネバネバ状にし山椒の実をつぶして混ぜ合わせた山菜料理で、それをご飯にかけて食べるのが春から夏にかけてのこの辺りの習慣だった。
「渡部巡査!」
「はいっ!」
「この木どげでもらうべ」
(えっ?)
「まずは証拠写真を撮れ!」と言われると思っていた渡部巡査は拍子抜けしてカクッとなった。
2人は玄関に回った。
「おや? ここでも不幸あったようだな」
佐々木巡査は『忌中』と書かれた看板を見て言った。
「立派な家だすな」
渡部巡査は瀟酒な家に目を奪われていた。
「ごめんください」
反応がなかった。
2人はきびすを返してパトカーに戻ると、通行者に危険を知らせるために、せり出した松の木の枝に佐々木巡査の汗が付いたハンカチを結んだ。そして200メートルほど先の作之進の家に向かって歩き出した。
△このページのトップへ
5『裸足の足跡』
作之進の家の前には、ちょうど別家衆への触れを終えて帰ってきた作之進と周平が立っていた。
「やあ、どうも、今日も暑いですなあ」
佐々木巡査が声を掛けた。
2人が声の方向を見た。
「おうおう、佐々木巡査」
作之進が顔にしたたる汗を拭きながら言った。周平も頭を下げた。
「何があったかの?」
作之進が聞いた。
「いやあ、宮下貴志さんっちゅう家が留守なもんで、作之進さんにちょっとお尋ねしたいんですが」
「何かの?」
「警察に通報がありましてなあ。木が倒れて通られんっちゅうんで来てみましたら、確かに倒れておりました」
佐々木巡査は、そう言って木のある方向を指さした。
「ああ、確かに松の木が折れておったのう。しかし、通られんほどではなかろう。一体誰が通報したのかの?」
「それが、名無しのゴンベエでして・・・」
「はあ」
「まあしかし、今は垣根に引っ掛かって大丈夫かもしれませんが、いつ道路に倒れてくるか分かりませんので」
「貴志はいなかったじゃろ?」
「ええ、連絡の取りようはありませんかなあ」
作之進は周平の顔をジッと見て、
「取れんこともなかろうが、なあ周平」
と言った。
「ええ、北都新聞さ電話して聞ぐごとはでぎるかと」
周平が彩のアイディアを告げた。
「ああ、では、そうしていただけませんか。倒れてけが人でも出たらことですからなあ」
渡部巡査は警察手帳を広げながら、佐々木巡査が謎の足跡のことに言及してくれることを期待していた。
「では、そういうことでよろしくお願いします。本官はこれで」
(えっ?)
渡部巡査は慌てた。
「あっ、あのう・・・」
渡部巡査が言った。
全員が彼を見た。
「木の根元さ裸足の足跡があったんだす! ちっちゃいのとおっきいのがいっぱいあったんだす!」
彼は警察官らしからぬアバウトな表現をした。
「はあ、足跡・・・」
作之進が言った。
「んだす。ちっちゃいのどおっきいのが、こう、ゴチャゴチャッと」
渡部巡査は両手を使ってゴチャゴチャ感を出そうとした。
「はあ」
「何か心当だりはねえですか?」
しどろもどろになりながら、やっと渡部巡査が用件を伝え終えた。
作之進は周平の顔を見た。
周平の目がキラッと光った。FBI捜査官の目だった。
「裸足の足跡が付いでだんですか?」
周平が聞いた。
「んだす。こう、ゴチャゴチャッと」
渡部巡査は、また両手を使ってゴチャゴチャ感を出そうとした。
「本官は、その人物だぢが木を倒した犯人ではねえがど思ってるんだす!」
渡部巡査が確信に満ちた言い方をした。
佐々木巡査は目を丸くして渡部巡査を見ていたが、顔をしかめてこう言った。
「おいおい渡部、おめえ何しゃべってるんだ。刑事ドラマの見過ぎだべ。なんぼ怪力の持ち主だってあんだげの木2人ばがりで倒せるわげねえべよ。そもそも誰が何のために木倒さねばねんだ? あれは夕べの嵐で倒れだんだ。バカだなおめえ」
佐々木巡査は刑事コロンボなどではなかった。
「まっ、とにかぐそういうごどですから。我々は忙しいものでこんで失礼します。ほらっ、行ぐど!」
佐々木巡査はそう言って渡部巡査に目配せした。
「し、しかし・・・」
渡部巡査は悔しさを顔ににじませながら渋々佐々木巡査の後に続いた。
「はあ」
作之進はそう言ってから、貴志の家のほうの空を見上げてため息をついた。
「どういうごどだべ、作じい」
作之進は周平の問いには答えずに、
「悪いが、北都新聞に電話してくれんかの」
とだけ言った。
△このページのトップへ
6『お前はバガじゃ!』
美樹のケータイが鳴ったのは、ジャパンペット成仏堂の加賀美が火葬の完了を知らせにきていた時だった。
「作之進じゃが、貴志に代わってもらえんかの?」
電話に出た美樹にいきなり作之進が言った。
「あっ、はい」
美樹は不得要領な顔で貴志にケータイを渡した。
「俺っ?」
貴志がポカンとして電話に出ると、作之進はいきなり言った。
「お前はバガじゃ!」
貴志はあっけにとられた。
「今からすぐに来い!」
「えっ?」
玄関には、可愛いペットちゃんの絵柄入りの『特製オリジナル骨つぼ』を抱えた加賀美が、長寿祝を持ってきた役場の長寿福祉課の職員のような顔で立っていた。
△このページのトップへ
7『切る!』
愛宕村の別宅に着いた2人が庭に出て見たものは、無惨にも引き裂かれるようにして折れているアカマツの木だった。2人はうっそうと生い茂った庭木の間をかき分けてその根元にたどり着いた。
「チェッ、何でこんな時に!」
貴志はのこぎりを持って木の断裂部を見やりながら、迷惑そうにつぶやいた。
「何これ?」
謎の足跡に気が付いたのは美樹だった。美樹は大小2つの裸足の足跡を、しゃがみこんで食い入るように見詰めている。
「ねえ、この足跡見て!」
ギゴギゴギゴギゴ・・・。
いきなり貴志が木を切り出した。貴志はむしゃくしゃしていた。それは美樹には言わなかったが、作之進に言われた言葉が原因だった。
(お前はバガじゃ!)
彼は、眉根にしわを寄せて力任せに木を切っていた。折れた部分の直径は50センチほどだったが、ギザギザに裂けるようにして折れていたので切り離すのに手間が掛かった。汗をしたたらせながら、ようやく貴志が切断を終えた時だった。
ワサッ、ワサッ・・・。
という音とともに、木は少しずつ道の方向に傾いていった。
「あっ!」
貴志は慌てて道路に身を乗り出した。
美樹も立ち上がって、
「危ない!」
と叫んだ。
ダーンッ!
垣根を基点にして、ちょうどシーソーがギッコンバッタンするように、松の木は天地が逆転する形で倒れ道をふさいだ。
幸い通行していた者はいなかったが、一歩間違えば大惨事という場面だった。
(お前はバガじゃ!)
作之進の言葉がまた貴志の脳裏をよぎった。
2人は急いで道路に出た。
「どうする?」
美樹が言った。
「少しずつ切るしかないだろう!」
貴志の顔には、はっきりといら立ちの色が浮かんでいる。
「業者に頼んだら?」
これは手に負えないと思った美樹が言った。
「いや!」
即座に美樹の提案を拒絶した貴志は、充血した目で木を見やってから腹立ち紛れに思い切り木を蹴飛ばした。
ビンッ!
鈍い音がした。
「切る!」
足の痛みをこらえながら、貴志は先端の枝を切り始めた。30センチばかりの枝を1本切り落とすのにもかなりの時間がかかった。汗だらけの真っ赤な顔で3本ほど力任せに枝を切った貴志は、ゼーゼーと息を吐きながら倒れた幹の上にへたり込んだ。
「無理だって」
美樹が空を見上げながら言った。
「・・・」
「ねえ、何いらだってんの?」
「・・・」
「餅は餅屋だって」
そう言いながら、美樹はふと団子を思い浮かべた。
「こういうの、どこに頼めばいいんだろ?」
「・・・」
「取りあえず役所に聞いて・・・」
「いや切る!」
そう言って、貴志が立ち上がった時だった。
ダダダダダダダダダッ・・・。
遠くからトラクターの音が聞こえてきた。
(あっ! やべえ!)
トラクターは急速に近付いてきて木の前で止まった。
貴志は恐縮した顔で運転席を見上げた。
「日長ぐなったな!」
チョロQだった。
「頑張るなあ!」
のこぎりで切られた枝を見ながら、満面の笑みでチョロQが言った。
「あっ、どうもすみません、これ」
貴志が倒れた木を指さして苦笑した。
チョロQは「うんうん」と木を見ながらうなずくと、満面の笑みを浮かべて、
「明日までかがるど!」
と言ってトラクターを下りた。
「待で待で!」
チョロQはそう言って荷台に常備している様々なアイテムの中から小型のチェーンソーを手に取ると、慣れた手付きでスターターハンドルを引いた。
ドッ、ドッ、ドッ・・・グイーンッ!
小気味いい音をたててエンジンが始動した。チェーンソーを持ったチョロQの腕は、まるで自分の体の一部のようだった。彼はその腕を巧みに動かしながら、ちょうど1尺の長さに木を切り刻んでいった。あっという間だった。
2人は目を丸くしてその動きを見詰めた。
「よしっ!」
チョロQはチェーンソーのイグニッションスイッチをオフにすると、2人に向かって張りのある声で、
「この木、要るが?」
と尋ねた。
「えっ? いえ」
貴志が答えた。
「オラさけるが?」
「ええ、どうぞどうぞ」
貴志がそう言い、美樹もうなずいた。
「薪にすっから」
チョロQはそう言って、荷台に木を積んでトラクターに乗り込んだ。
「ありがどうな」
運転席からチョロQは満面の笑みでそう言った。質の高いバリトンボイスだった。
「あっ、あのう、料金は・・・」
貴志が聞いた。
「なもなも」
チョロQはまたそう言って笑った。笑顔の口元からのど仏がのぞいていた。
「あっ、どうも・・・すみません」
貴志が口ごもりながら言った。美樹もペコンと頭を下げた。
「なもなも、へば」
ダダダダダダダダダッ・・・。
軽快な音を響かせながら、チョロQはいつもの忙しい顔になって走り出した。
△このページのトップへ
8『2年半後』
それから2年半後の年の瀬、12月26日の朝。
出社前の貴志と美樹がダイニングテーブルで朝食を食べている。
「忘年会も今日が最後だ。毎年のことだけど、年々疲れるようになったよ」
二日酔いの腫れぼったい顔で貴志が言う。
「忘年会やれるだけいいじゃん」
美樹がコンソメスープを飲みながら言う。
「まあな。そっちは休みないんだろ?」
「うん、しばらくない」
「そう言えば、昨日お父さんとこ行ったの?」
「ううん、電話したらタラ鍋作ったから食いにくるかって言われて」
「へえ!」
「グラッときたけどやめた」
美樹は、そう言って自分の食器を片付け始めた。
「それにしても変わったよな、お父さん。塩辛とかも作るんだぜ。自分でイカ買ってきてさ。これがまたうまいんだよ」
新聞を広げながら貴志が言った。
「へえー!」
「まだまだ大丈夫だな、あの分じゃ、お父さん」
美樹は自分の食器を洗い終わると、
「それ、洗っといて!」
と言って、用意しておいたコップと皿を持って寝室に入っていった。そして小さな仏壇の前に立った。
チーンッ!
美樹は鈴を打って静かに手を合わせた。
雪明かりがレースのカーテン越しに仏壇を照らしていた。
右にジャムの写真、左にかなめの写真が並んで置かれ、その手前に美樹が持ってきた水の入ったコップと白い皿があった。皿の上には、器用に丸められた直径3センチほどの団子が16個、きれいに並んでいた。
「じゃあ、行ってくるから」
居間に戻った美樹はそう言ってコートを着ると、自分のクルマのキーを持った。
「おう、いってらっしゃい!」
新聞をたたみながら貴志が言った。
「あっ!」
ドアを開けようとした美樹が、思い出したように後ろを振り返った。
貴志が目をやると、美樹はキッチンの脇にある大きな米袋を指さして言った。
「それなくなったから、挽いてきてくれない?」
△このページのトップへ
9『特ダネ』
北都新聞社の編集部は、元日用の特別紙面の編集で多忙を極めていた。
この4月からデスクになった美樹の机の上には、記事や広告の原稿がうずだかく積まれている。
「デスク、おはようございま・・・ふぁーっす!」
入社5年目の長谷部甚一郎が、あくびをしながらコーヒーを持ってやってきた。
「サンキュ! あっ、その辺置いといて」
ノートパソコンのキーボードをカタカタ打ちながら美樹が言う。
「はいい・・・」
そう言いながら長谷部は置き場を探すが置けるような場所がない。長谷部は仕方なくコーヒーを手に持ったまま美樹に話し掛ける。
「共同の記事見ました?」
「まだ」
「ロシアで氷漬けのマンモス発掘・・・」
「どれ?」
ようやく目を上げた美樹は、長谷部の持っているコーヒーに手を伸ばした。
長谷部は自分の机からその記事を持って戻ってきた。
「これこれ」
美樹は、コーヒーを口に運びながらタス通信社発信の共同通信の記事を手に取った。『ロシアで世界最大級のマンモス発掘』というタイトルのその記事には、発掘されたマンモスと発掘チームのカラー写真が付いていた。
発掘チームの写真が美樹の目に留まった。20人ほどの氷焼けした真っ黒い顔が、まん中の白いひげをたくわえた初老の男を取り囲むようにして写っていた。どの顔もことさら真っ白い歯が印象的だ。
(ん?)
美樹は、その中に見覚えのある顔を発見した。多国籍の外国人に混じって映っているその顔は、忘れもしない金剛力士のモンタージュ顔だった。よく見ると隣には彩らしき顔まで写っている。美樹は本文を斜め読みした。
(日本からもボランティアで参加者?)
「これ、国際面っすね!」
長谷部が言う。
「ジン! これ一面トップ! 入れ替えよ!」
キッパリと美樹が言う。
「えっ!」
「早く!」
「トップですか!」
「それから、共同通信に電話してこの日本人のこと調べて!」
驚いている長谷部に記事を渡しながら、美樹は続けて言った。
「星野って名前の夫婦だったら特ダネ。社説も変更よ!」
「ホシノ?」
「ここの出身者よ!」
「ええーっ!」
美樹は飲み終わったコーヒーカップを長谷部に手渡すと、またカタカタとキーボードを叩き始めた。
「デスク、おくやみの原稿チェックお願いします」
今度は、入社3年目の石川友子が校正原稿を持ってやってきた。
受け取って原稿を見ていた美樹の目が、中段6行目で止まった。
宮下作之進、97歳の訃報だった。
(完)
△このページのトップへ