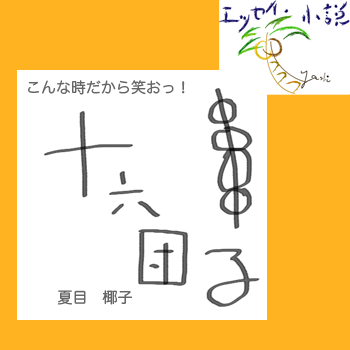★ダミ行列はようやく動き出したが・・・。(作者注釈)
第2部〜第3章『そして十六団子は・・・』
1『ダミ行列』
ジャン! ボン! ジャン! ボン!
ダミ行列はかなめの畑を通って、五反山を望む田んぼのあぜ道をゆっくりと進んでいった。それは、生前のなじみ深い場所をかなめに見せてあげるためだった。
五反山の上空に、シミのようなひと刷けのねずみ色の雲が浮かんでいたが、それを除けば見渡す限りの青い、まるでゴッホの愛したピュアプルシャンブルーの青空が広がっていた。
グライダーのような青鷺が1羽、単調な空にアクセントを付けるかのようにギコギコと無骨な羽ばたきで飛んでいく。彼が鳥瞰しているのは、豪雨の冠水で上がった流木が所々残る畦道をうねりながら進んでいく龍の姿だ。
青い空とコントラストをなす緑の稲田は、冠水にもめげず元気に成長を続けているようだった。自然災害に打ち勝つ力は、自然そのものの中に既に内在しているということを証明するかのように、稲は今からどんどん分けつを繰り返し、秋には実りのこうべを垂れることだろう。
ダミ行列の長い列は、やがて緩やかな坂を蛇行しながら村里へと上っていった。セミ時雨が一足ごとに大きくなって降ってくるようになった。
村のメイン通りに来ると、合掌して行列を迎える村人の姿が増えてきた。彼らは源蔵が言ったとおり、行列の最後尾に付いて一緒に歩き出した。ダミ行列の龍のしっぽは次第に長くなっていった。
集会所のある角を左に曲がった時だった。
そこは、かつて『タメばあ物干し事件』の現場となった場所だった。
行列の前のほうで傘を広げた者がいた。
(あれっ? 誰だろう。何で傘持ってんだろう?)
周平は訝しく思った。源蔵も「チッ!」と舌打ちして首を傾げた。
やがて、傘がタメの家の前に来た時だった。
「おいっ、ボラッ!」
と前方で叫ぶ声がした。
ウー、ウオン! ウオン! ウオン!
イヌのガブが吠えた。
「おめえみでえに、いっつも悪いごどばっかやってっと、まどもに人のツラも見られねべ。ほれっ、そうやってツラ隠して」
歌子の声だった。その声は後ろにいた周平の所にも届いた。歌子の後ろにはタメが腰に手を回して立っていた。
昭介は傘で顔を隠して歩く速度を早めたが、前がつかえて進めない。
歌子は昭介の横を歩きながらこう言った。
「いいが、人間出来心っつうごどもあるもんだ。悪いごどやっつまったらそれっきりにして、あどは絶対にすねえようにすろっって、おらそうやって親にもかなめにも教わったもんだ。そうすれば少しずづ忘れでもらえるもんだって」
歌子の大きな声に、行列の前にいる人が何人か振り返って昭介を見た。直前にいた道秋は、
「えっ? 何? 何? 誰? この人、ねえ」
と、歌子の顔を不思議そうに見ていた。
昭介はいっそう傘を深くかぶった。隣にいたやえが気まずそうに下を向いた。高太は「何だこのババア!」という顔で歌子をにらみ付けている。
「でねば、おめえ、一生そうやってツラ隠して逃げまわらねばねえんだど。お天道様もおがめねえでな!」
「おいっ! ババア、誰にもの言ってんだよ!」
高太が歌子にガンをつけた。
「おめえのオヤズだ!」
負けずに歌子もガンを返した。
今日の諜報部員はなかなか凄みがあった。
「んでねばなあ、せいぜい『なまはげ』の面でもかぶって生ぎでいぐしかねえんだど。分がったが、このボラッ!」
歌子は一気にそう言うと、後ろにいたタメに、
「ああ、すっきりしたあ」
と言ってニッコリ笑った。
タメも胸のつかえが下りたような顔でニコッと笑った。2人はそのまま行列に続こうとそこに立ち止まっていた。
周平がその前に差し掛かった時、歌子と目が合った。歌子は周平に向かって、前を指さしつつ片目をつぶった。周平も笑顔を返した。
(ああ、これはきっと、かなめばあが歌子ばあの口を借りて言わせたに違いない)
周平はそう思った。今日の歌子の口調は、どことなく生前のかなめを彷彿させるものだったからだ。
「チェッ、何だ、あのババア。覚えてやがれ!」
高太は後ろを振り返ってチンピラの常套句を吐いた。
「なあ、おやじ、あのババア、バッキシおとしまえつけてやんなきゃな」
「・・・」
「なあ、おやじ。あのババア・・・」
「・・・」
「おやじ、いいから俺に任せろ。絶対おとしま、いでっ!」
行列の動きが急に止まり、傘で身を隠していた昭介は前にいた道秋とぶつかった。その昭介に高太がぶつかった。
(あれっ? 何があったんだろう?)
周平が前方に目を凝らすと、行列の先頭にいるナマスと、家の中から出てきた小柄な男が真剣な顔で何か話をしていた。
周平は隣の源蔵と顔を見合わせた。
△このページのトップへ
2『バガ野郎!』
ナマスと小柄な男の会話の内容は、伝言ゲームのようにして後ろに伝わってきているようだった。ダミ若勢や行列に参列していた村人が、列を離れタマヨの家に走っていくのが分かった。周平は胸騒ぎがした。
やがて周平の元に届いた伝言は、『何でも金太郎という人が鬼退治に行ったようだ』というものだった。
(ダメだこりゃ!)
周平は、傘の束をその場に置いて急いでタマヨの家に走った。
居間の入り口にタマヨが団子のように丸まって座っていた。その脇にはスミとマチが、タマヨに寄り添うようにして丸くなっていた。
ナマスが目をまっ赤にしていた。
作之進は肩をガックリと落とし、下を向いて目を閉じていた。
貫太郎は黙って天を仰いでいた。
歯欠け3人衆は口をしっかり結んでいた。
周平はそれらの状況からすべてを理解した。
「おーい、おいおいおい、おーい、おいおいおい・・・」
突然タマヨが泣いた。
「あいい・・・あいい・・・あいすかだにゃー」
そう言いながらマチも泣き出した。
「キンゾー、キンゾー、あいい、いだわすなあ・・・」
スミは畳を爪で引っ掻きながら泣いていた。
「いづ死んだんだ?」
周平が低い声で隣にいたボンチンに聞いた。
「今、病院さ行ってる息子の正夫がら電話きたんだど」
ボンチンも低い声でそう言って鼻水をすすった。
(嘘だろう! 昨日まであんなに元気だったのに・・・)
周平だけではない。誰もが金蔵の死を信じられないでいた。何か狐につままれたような気持ちだった。
「金蔵! なして死んだ!」
ナマスが突然、天井に向かって怒鳴った。
「お、おらが・・・、ヒッ、おらがしとめるって・・・」
ナマスの目から涙がボタボタ土間に落ちた。彼は天に向かってライフルを構えるまねをした。
「おらが、ヒッ、この手でしとめるって・・・、ヒッ」
照準器が涙でかすんだ。彼は袖でグイと涙を拭った。
「ヒッ、ヒッ、言ったべ、バガ野郎!」
ナマスは顔をグチャグチャにして泣き崩れた。
「おーい、おいおいおい、おーい、おいおいおい・・・」
タマヨが畳に顔をこすりつけて泣いた。ボンチンも周平も泣いていた。いたるところから嗚咽が聞こえた。
その時だった。
「ねえねえ、皆さん。あれっ? もしかしてお取り込み中? そうですか、お取り込み中ですか。こりゃ困ったねえ。お取り込み中のところにお取り込み中なんだからねえ。こっちもお取り込み中なら、あっちもお取り込み中。あっちもお取り込み中なら、こっちもお取り込み中だ。ねえ、そうでしょう?」
全員が声の主を見た。玄関の入り口に立っている声の主は周囲の空気を全く読めないまま、またヘラヘラとしゃべり出した。
「こういうのバッチングっていうんだよねえ、バッチング。あっちのお取り込み中は、ほらっ、行列だね、行列。野辺送りの行列。その途中だもんねえ。さあ、こっからが問題だねえ、問題。クイッチョンだ、ねえ。どっちがよりお取り込み中かってことだ。ねえ、そうでしょう? ぼくは断然あっちだと思うなあ。だってほらっ、あっちのお取り込み中はなんたって重いでしょう。荷物持ってるからね、荷物。荷物っていうのは、僕の場合はまあ『タツノオトシゴ』っていう棒なんだけどね。タツが頭に付いたやつ。あれ、軽いように見えて結構重いんだよ。ねえ、そういうのみんな持ってるんだ、ねえ。だって行列なんだからね。それからもう一つ、あっちのお取り込み中は暑いのね。ホント暑い、ねえ。表だから、表。こっちはこう家の中でしょ。わあ、涼しいねえ、ほらっ。風も通って、ねえ。皆さん、熱中症って知ってます? あれ大変なんだよ、熱中症。ぼくも経験あるんだけどねえ。あれつらいよう。ねえ、ほんとつらいの。さあ、軍配はどうでしょう? ねえ、あっ! うっ! うっ!」
ヘラヘラ男の話をさえぎったのは照子ではなくナマスだった。ナマスが道秋の襟首をギュッとつかんでいた。
「うーっ! な、な・・・」
「おめえ!」
ナマスがスナイパーの目で道秋をにらみ付けた。そして右腕に大きな力こぶを作ってそれをグーッと上に持ち上げた。道秋の体が宙に浮いた。
「うっ! うっ、うーっ!」
「殺す!」
ナマスの腕にさらに力が入った。
「ぶっ殺す!」
「ク、クッ・・・」
道秋の足元にチョロチョロとしたたるものがあった。それは打ち水のように土間の上に黒いしみを作った。
「益男、やめろ!」
作之進がナマスの肩に手を置いて言った。
ナマスが手を離すと、道秋はヘタヘタと黒いしみの上にへたり込んだ。
作之進はタマヨに向かって、
「かなめを送ったら、すぐ来るからの」
と言って、みんなに外に出るように促した。
ジャン! ボン! ジャン! ボン!
斎田道秋と照子を残して、ダミ行列が静かに動き出した。
△このページのトップへ
3『胸騒ぎ』
「スミさんたち遅いですね」
かつらと2人で留守番をしていた彩が、時計を見ながら言った。
「そうねえ、もう3時間近くになるわねえ」
かつらも自分の腕時計を見た。
「お昼大丈夫でしょうか」
「えっ?」
「マチさんが、ダミ若勢さんたちに家で食べさせるんだって言ってたんです」
「そうねえ、お弁当はさっき持ってきていただいてるからいいとして、問題は場所よねえ」
「ええ、マチさんがいなかったら・・・」
「じゃあ、こうしましょう。もしマチさんが戻らなかったらここで食べてもらいましょう」
「そうですね、何かいろいろ作ったものもあるし」
彩はそう言って、のり子が作った『とろみあんかけ風ベチャベチャくっ付きまくりナス』をチラッと見た。
(でも、これは出さないほうがいいな。勘違いされても困るし)
彩は自己防衛的にそう思いながらも、胸の奥にうずくような胸騒ぎを覚えていた。
△このページのトップへ
4『墓地にて』
村の隅々を回り終えたダミ行列は、ようやく墓地に続く『おせど』付近までやってきていた。かつて周平は『おせど』というのは『お伊勢井戸』のことだと一三から聞いたことがある。
「昔はこの辺りに湧き水があって、それを共同で生活に利用すていだのがもすれないですね」
一三先生は言った。
「しかす、地方によっては裏庭を意味する方言だったりもするので、この歌に出てくる『おせど』がどっちがは定かではありません」
音楽の時間だった。
『おせど』周辺にはブナやナラなどの広葉樹が多かった。周平は一三先生のピアノに合わせて『里の秋』を歌いながら、
ポチャン、ポチャン・・・と、木の実が井戸の中に落ちる音を想像した。そして、その時には既に他界していた母を思慕したものだった。
おせどの前の道に銀色のRV車と、その後ろに『割烹中川』と車体に書かれたバスが止まっていた。
一三は、RV車に近付いていくとトントンと窓を叩いた。自動で開いた窓から坊主が顔を出した。一三はどこかで電話を借りて、抜かりなく彼に連絡をとっていたようだった。荘道は面倒くさそうにクルマを下りると、眩しそうな目で上空を見上げた。
「では、お願いすます」
一三がいんぎんに言った。
「あーい、あい!」
おサルさんのようにそう言って、荘道は便所下駄のようなものを履いて歩き出した。手にはこの期に及んでもまだケータイを持っていた。
ここから墓地に続く道はダミ若勢たちによってきれいに草が刈られ、山ヒル対策用の塩もまかれていたのだが、何しろ道幅が狭く彼らは一列縦隊になって進まなければならなかった。
村人たちは墓地までは入らずに、墓地を見下ろす途中の高台でひと塊になった。狭い墓地の収容人員を考えてのことだった。作之進、源蔵、周平はそこに留まることにした。坊主、喪主はもちろん、近しい親族と別家、そしてダミ若勢の数人が待機チームが持ってきた持ち物を預かり持って墓地に向かって歩いていった。
彼ら墓地チームが全員墓地に到着した頃、タツガシラを杖代わりにして、死にそうな形相で待機チームの脇を通り過ぎた者があった。斎田道秋と照子だった。道秋は、口元に白い泡をくっ付けてハアハア言いながら、転がるように坂を下りていった。
その時、空が急に暗くなった。
「チッ!」
源蔵が上空を見やりながら舌打ちをした。
周平も空を見上げた。
さっきまでのペルシャンブルー一色だった空は、ゴッホの『雨雲のあるオヴェールの野』を思わせる風景に変わっていた。五反山上空にひと刷けだけだった雲は、東に連なる尾根から伸びてきた黒い大きな雷雲の塊に絡めとられていた。そして、その黒い絵の具の刷毛は急速に勢いを増しながら、ペルシャンブルーのキャンバスを上塗りしていくのが分かった。
村人たちも不穏な空模様に顔を曇らせた。
「降らなきゃいいですね」
周平が言った。
「チッ、んだなあ」
源蔵は抱え持った傘の束を見ながらつぶやいた。
墓の前に参集した者たちも、雲の動きを気にして皆ソワソワしていた。
「葬儀屋さん、早くしてくんないかなあ」
荘道が一三に言った。
一三はもうイライラしなかった。それは、荘道という男に対する免疫ができたということではなく、ましてやそういうことに動じない立派な人格が突如形成されたわけでもなかった。彼は、自分が本当に葬儀屋であるような錯覚を持ってしまっていたのである。
「さあ、急いでくださーい!」
にわか葬儀屋が呼び掛けた。
「はい、遺影写真はここ、こちらに置いてくださーい!」
「その前に位牌でーす。違う、違う、骨箱はその手前、そうそう」
「お膳の方、お膳の方は? お膳の方、そごのあなた、あなたですよ。そうです、それがお膳です。何持ってだと思ってたんですか? えっ? まんま? 確かにそれもありますけど、それはお膳です。はいはい。ここここ。あーっ、逆、逆、逆。向きが逆です!」
「お花、お花の方。こっちとこっちに。そっそっそ。それでいいです。いいです。これは向きはどっちでもいいですから。花はいいんです、向き関係ないです。はいはい」
「花台の人、こごでーす。そうです、そうです。あっ、あど1人、いませんかあ?」
「卒塔婆は後ろ、あなた、こっちがら回って。あっ、いいですよ別に、そっちから回ってもいいんですけど、こっちのほうが広くて歩ぎやすいと思っただげです。だから、いいんですって、ええ、そっちからでもいいですって。そう、そのまま立て掛げでおいて、いいです、いいですって。押さえでなくても、そのまんまで。倒れませんから、大丈夫、大丈夫」
にわか葬儀屋はなかなか忙しかった。
一方、貫太郎は貫太郎で、
「ケッ、ケッ、ダゴ、ダゴ、ダゴ、ダゴ」
と、十六団子を持った人に指示を出したがっていたが、密集した人ごみの中にあって、背の低い彼は悲しいかな完全に埋没してしまっていた。
「このお団子はどこに置くんですかあ?」
向こうで十六団子を持ってきた郁子が聞いていた。
「ダゴ、ダゴ、ダゴ・・・」
貫太郎は人ごみをかき分けながら、郁子に近付いていった。
「ダゴ、イガ、ハガンヨッスミッサフトッツヅオゲ」
貫太郎が郁子に言って無垢のほほ笑みを向けた。
(・・・)
郁子は、すがるように隣の大地を見た。
「ねえ、何? この人何て言った?」
「さっぱり分かんない。でも、タコとかイカとか言ってるような気もするな」
「何それ?」
「ダゴ、イガ、ハガンヨッスミッサフトッツヅオゲ」
大地の腕に抱っこされている洋が、貫太郎と至近距離で目が合っていた。
洋の手が怪しく動いた。それは例のニンニンのポーズだった。
「イガ、ダゴ、ハガン・・・グギャ!」
洋の指は貫太郎の大きな鼻穴に奥深く刺さった。受難だった。
「こらっ! 洋!」
貫太郎は目に涙をためて鼻を押さえた。
「すみませーん。ところで、このお団子は?」
その声を聞きつけた貴志が郁子に向かって叫んだ。
「あっ、それは墓の四隅に一串ずつ置いてくださーい!」
「分かりましたあ!」
コミュニケーション力の違いだった。十六団子は墓の四隅に収まった。
貫太郎は涙目でそれを眺めていた。もちろん感極まったわけでも、自分のコミュニケーション能力のなさに落ち込んでいたわけでもなく、単に鼻が痛かったからだった。
用意が整ったところで、葬儀屋になり切っている一三が荘道に言った。
「それでは、導師様よろすぐお願いいだすます」
「あいっ!」
便所下駄を履いた導師様が小さな鉦を鳴らした。
チーンッ!
ピカッ!
五反山の真上に稲妻が走った。
ゴロゴロゴロゴロ・・・。
2秒後に雷鳴がとどろいた。
洋は大地の胸に顔を埋めた。体がブルブル震えていた。明らかにあの時のトラウマだった。
ガシャクショゾーショアクゴー・・・。
パチッ、パチッ、パチッ・・・。
ついに雨が落ちてきた。雨粒は導師様の坊主頭にシミを作るように少しずつ広がっていった。
墓地チームのメンバーは眉をしかめながら頭の上に手をかざした。
ピカッ!
また稲妻が走った。
「うっ、うっ、うええーん!」
洋が耳を押さえて泣き出した。
・ ・・カイフシンイカイフホーサンボーカイ。
ゴロゴロゴロゴロ・・・。
チーンッ!
あっという間に読経は終わった。ものの30秒だった。
「葬儀屋さん、あと納骨お願いね」
荘道はそう言ってそそくさと帰り支度を始めた。
「はい! かすこまりますた!」
一三は、葬儀屋としてのへりくだり口調まで身に付けてきているようだった。
「割烹中川は1時半ね!」
荘道が今度は貴志に向かって聞いた。
「ええ」
と答えながら貴志は苦々しく思った。
(こいつ、食うことだけはしっかり覚えていやがる)
荘道は、「じゃあ」というふうにケータイを持った手を上に挙げると、便所下駄を引きずるようにしながら帰っていった。
△このページのトップへ
5『ウッサナゲ』
「それでは納骨になりまーす。係の方お願いすまーす!」
葬儀屋になり切っている一三がアナウンスした。
ナマスが怪力で水鉢台をズズズーッと横にずらすと、納骨穴が姿を現した。
ピカッ!
ゴロゴロゴロゴロゴロ・・・。
稲光と雷鳴の間隔が短くなった。
辺りは夕方のように暗くなってきた。
バヅッ、バヅッ、バヅッ・・・。
大粒の雨が降り出した。
待機していた村人チームの脇を、ガンモのように着物の裾をまくり上げて小走りに荘道が通り過ぎていった。
「チッ、はいどんぞ」
源蔵は傘を縛っていたひもをほどくと、村人たちに1本ずつそれを渡して歩いていた。
「これ、向こうに持っていきますね」
周平が源蔵に言った。
「チッ、頼むす」
周平は傘を持って駆け出した。
ザザザザザザザザザア・・・。
その時、バケツの水をひっくり返したようなものすごい雨になった。
墓地チームは、松明を模した棒で納骨室に骨を入れる作業を行っていた。
「はい、次の方どうぞ」
全員ずぶ濡れになりながらも作業は続行されていた。そんな中、たった1人だけ、正確に言えばたった1家族だけ濡れていない家族があった。彼らはどこまでも悪運が強かった。
骨箱の中にも水が入り、もともと粉化していた骨はだんだんペースト状になっていった。「これをフライパンかオーブンで焼けば、カルシウムたっぷりのパンケーキになるはずだ」とは誰も思わなかった。誰にもそんなユーモアを語る心の余裕がなかったからだ。
「大体これくらいで・・・どうでしょう?」
もうスプーンがなければすくえなくなってしまった『ペースト状かなめ骨粉』をかき混ぜながら、貴志が困った顔で一三に聞いた。
「分かりますた。では閉めてくださーい!」
一三はナマスに合図を送った。
ナマスはまた怪力で水鉢台の石を動かした。
ピカッ!
ドーンッ!
ものすごい音がした。雷が近くの木に落ちたようだった。
「うっ、うっ、うえーんっ! えんえんえんえんえん・・・」
洋がひきつけを起こしたように激しく泣き出した。
「きゃああああーっ!」
郁子の悲鳴が聞こえた。
「どうすました!」
「ナタ、ナタ、ナタ!」
一三と貫太郎の声が重なった。
貫太郎は素早く郁子の所へ行くと、
「サッサ、オッチュ、サッサ、オッチュ」
と言いながら、額の小鼓をパチパチ打った。
顔面蒼白になって郁子が見ていたものは、洋の首に付いてビー玉くらいにふくれあがった山ヒルだった。山ヒルはかくいう郁子の首筋にも引っ付いていた。どうやら雨で塩の効果が薄れて山ヒルが大量に動き出したようだった。
貫太郎は例のセリフを吐きながら狼狽した。
大地が洋の首に付いたヒルを引っぱがそうとした。
「ダダ、ダダ、ヒパナ、ヒパナ、ヒパレバダダ」
貫太郎が大地の手を押さえた。
「マッソ、マッソ、ソニャガ」
貫太郎がナマスに、「塩はないか」と叫んだ。
「塩だば邦彦たがでる」
どうやら塩を持っているのは待機組の邦彦のようだった。
「わっ! ヒルだ、ヒルだ! おめえさも付いでる、ほれっ!」
郁子ほどの驚きではないものの、村人たちの間にも動揺が走っていた。
ちなみに野々村一家の体には、見えるだけでもつごう18匹のヒルが付着していた。
斎田道秋と照子は盛んに股間付近をモゾモゾやっていた。彼らは、そろって陰部方面に深く侵入されたようだった。
あちこちから悲鳴が上がった。
ザザザザザザザザー。
ドドドドドドーン!
雨はさらに勢いを増し、墓石を揺るがすほどの雷鳴がとどろいた。
「み、皆さーん! は、走って戻ってくださーい!」
一三が叫んだ。
「バスまで急いでくださーい!」
一三が叫ぶまでもなく墓地チームはすでに駆け出していた。貴志は白装束を着たまま位牌を持って駆け出した。美樹は遺影写真を持ってそれに続いた。
傘を抱えた周平の脇をまっ先に通り過ぎていったのは昭介一家だった。彼らの逃げ足はさすがに早かった。続いて股間を押さえながら斎田夫婦が続いた。彼らはぬかるんだ道に足を取られ何度も転んだ。それから何人もの人が必死の形相で周平の脇を通り過ぎていったが、誰一人周平の傘を受け取ろうとする者はいなかった。彼らにそういう余裕はないようだった。
一団が去った後、周平は墓地に下りていった。
(誰もいない・・・)
豪雨にかすんだ墓地を見やりながら周平は思った。
周平は黙って墓に近付いていった。
目を凝らすと、墓の前でぼう然と立ち尽くしている男の影があった。男の頭を滝のように雨が流れている。
周平は、男がジッと見詰めている方向に視線を向けた。
(あっ!)
ピカッ!
ドドドドドドーン!
男が串を手に取った。
「シュヘ、フパレ」
周平はベチョベチョになった団子を片側から引っ張った。
「ウッサナゲ」
男が言った。
△このページのトップへ
6『万古不易』
「大学時代アルバイトしてたのね」
彩が言う。CDラジカセから吉田拓郎の『フキの歌』が流れている。
「えっ? アルバイトって?」
周平はコーヒーミルを回している。
「昔、弁護士事務所でちょっとバイトしてたことがあるんだ」
「へえ、初耳だな」
「裁判提出用の書類のタイピングとかやったことがあるの」
「うんうん、それで?」
「いやでもいろんな訴訟の書類を見るわけね。守秘義務なんだけどさ。お金でも土地でも、たくさんある人がトラブルを起こすのよね。人間の果てしない欲望ってやつよ。それから離婚訴訟とかも多かったな。ドロドロした怨恨劇をいっぱい見たわ」
「そういうの圧倒的に多いんだろうね」
「そう、世の中の争いの根っこにあるのは、人間の心の中にある業や欲なのよね、結局のところ」
彩はそう言って渋い顔を作った。
「うちは大丈夫だな」
コーヒーメーカーに豆をセットしながら周平が言った。
「そうね、お金ないもんね」
「うん、自信もって」
周平が笑う。
「それに夫婦仲も良好」
「それしかないからね、私たちの財産」
彩も笑う。
「確かに」
キッチンの調度品を見回しながら周平が深くうなずいた。貴志たちの家と比べるまでもなく、周平の家の電化製品はどれも年季の入ったものばかりだった。
「ねえ、ここに来て5年、原点に戻れたと思う?」
「そう言えば、そう思ってここに来たんだったよな」
周平が少し間を置いて答える。
「うーん、時代が変わってもぶれないもの、万古不易っていうんだっけ? 少なくともそういうものを学んだことは確かだな」
「そうね、体重にならない肥やしはいっぱい身に付けたわ」
「えっ? 体重にならない肥やし?」
「うん、心の肥やしよ」
「なるほど、それいい、その肥やし」
腹を手でさすりながら周平が言って立ち上がる。
「どうしたの?」
「ちょっと出してくる」
「えっ?」
「こっちの肥やし」
周平はそう言って下腹に手を当てた。
「ゲッヒーン!」
やがてトイレから戻ってきた周平は、
「あー、スッキリしたあ!」
と言って椅子に座った。
「オシッコをしながらこう考えた」
「ゲッ!」
「何事もじっくり味わうことがことが大切だ!」
「何それ?」
「うん、サラリーマンだった頃って、例えばオシッコをしてるときでも、こんなふうに『ああ、気持ちいいなあ』って思ったことなかったような気がする」
「そう?」
「うん、何かいつも次のこと、次のことって考えててさ。トイレ入っててもオシッコに集中してないっていうか、いつも何か別のこと考えていたような気がするんだ」
「ああ、なるほどね。次のスケジュールは・・・とかね」
「うん、今していることに集中してないって感じでさ。ああ、放尿ってこんなに気持ちいいもんだったんだって今つくづく思ったな」
「なるほど、それも学んだことか。まさに人間の原点だわね」
「うん、食ってるときもそうだよ。本当に何食ってもうまい」
「よせやい顔が多くなるわけだ。それも原始的欲求ね」
彩は、弁当を食べていた時のスミとのり子の顔と、『Oーマズロー』と言ったカマジイの顔をチラッと思い出した。
「邦彦さんとこで牛見てるとさ、やつら草をゆっくりゆっくり食べるだろ?」
「ああ、『咀嚼』ってやつね」
「うん、飲んだり出したりしながら何度も何度も味わってる。ああいうふうに人生を咀嚼して味わって生きられたらいいなって思ってさ」
「そうね、人生何倍も楽しめるわね」
「それが『笑って死ねること』なんじゃないかなって思ったりしてさ」
周平は牧草を食む牛の顔と、木之倉与左衛門商店のいいしわ顔のおばあちゃんとおじいちゃんのことを思い出した。
「でも、そういう心穏やかな豊かな人生を歩むためにはやっぱり余裕がなきゃな。そういう意味ではお金も大事な要素なんだろうな」
周平が言う。
「人生には勇気と想像力とほんの少しのお金があればよい」
「ああ、誰だっけ? それ」
「『ライムライト』のチャップリンの言葉よ。この前見たじゃない」
「ああ、そっか。『ライムライト』といえばキートンおかしかったなあ。バイオリンを踏み抜くとこサイコーにおかしかった」
周平はこの手のコメディが大好きだ。頭の中に『上映中』のランプが点灯する。
「勇気と想像力があればお金はほんの少しでも気高く生きられる。貧困の少年時代を過ごしたチャップリンだからこそ言える言葉だと思うわ」
彩はどこまでもアカデミックだ。
「キートンがさ、ピアノ弾こうとして楽譜がバラバラ落ちて、それを押さえてる時の顔もおっかしかったよねえ、プッ!」
話が噛み合なくなってきた。
彩は無視してアカデミックな話を続ける。
「『少欲知足』ってあるでしょ。温故知新で知る古き良き時代の法則だわ。不知足の人はたとえ富んでいても心が貧しい。知足の人は貧しくても心が富んでいる」
彩は悟りの境涯に入ろうとしている。
「キートンって絶対笑わないからおかしいんだよね。笑ったらダメさ」
「えっ?」
ようやく周平の言葉に彩が反応した。
「だから笑わないキャラは最後まで笑わないでいてほしいと思って」
「あっ! そういえば今日、ゴルゴ笑った!」
彩はやっと俗世界に下りてきた。
「マジ?」
「うん」
「あれぞ笑わないキャラの代表なのに?」
「うん、しかもあいさつもした!」
「ええーっ!」
「スミばあが言わせたのよ。そしたら最後に『あ、ども、ども、ありがとう・・・ございました』って言って笑ったの、こんなふうに」
彩はゴルゴのまねをした。
「わあーっ! すげえ!」
「うん、かつらさんがそれ写真に撮ってた」
「かつらさんもすげえ!」
「でも気持ち悪かった」
「うーん・・・」
3秒の間があった。周平も彩もそろって別の話題を探していた。できれば早く『ゴルゴ笑い』の残像を消し去りたかった。
「山路を登りながらこう考えた」
彩が切り出した。
「突然だな、どう考えたんだい? 漱石さん」
彩は『草枕』の冒頭をそらんじた。
「智に働けば角が立つ。情にさおさせば流される。意地を通せば窮屈だ。とかくに人の世は住みにくい」
「ふんふん、その通り」
「ちょっと飛ばして、ええと、住みにくい所をどれほどかくつろげて、つかの間の命をつかの間でも住みよくせねばならぬ。あと何だっけ?」
「あらゆる芸術の士は?」
「そうそう、人の世をのどかにし、人の心を豊かにするがゆえに尊い」
「さすが漱石さん、含蓄があるね」
周平がコーヒーを口に運びながら言う。コーヒーは398円のキリマンジャロブレンド。カップは高合町の山の中で瀬戸を焼いている窯元から買ったお揃いのものだ。
作り手と使い手の気持ちを温め合えるようにという願いが込められた陶器は、このコーヒーカップに限らず土鍋や鉢などどれも味わいがあって使いやすかった。それは彼らがここに来て買った唯一の有形財産だった。
「このカップもそうね」
彩が夢見るようにコーヒーを一口すする。
「うん、心をのどかにしてくれる、これぞ芸術!」
麻の布目模様に入ったカップを見ながら周平が言う。
周平はフト自分の好きな言葉が浮かんだ。
「おもしろきこともなき世をおもしろく」
「誰だっけ?」
「高杉晋作。世の中をおもしろくするって何か好きだな。そういうことができたら本当に幸せだろうなあ。世の中をおもしろくする力って、文学や芸術だけじゃなくて、本当は政治や行政にこそ必要なんだと俺は思うよ。今はそれがないんだよ」
珍しく周平がちょっと理屈っぽいことを言う。
彩は「うんうん」とうなずいている。
「コーヒーを飲みながらこう考えた」
彩がまた言う。
「ほう、今度は何を考えたんだい?」
「私はここで『ねこばり岩』にはなりたくない!」
彩が言う。周平は彩を見詰めている。
「スギナの根っこにもなりたくない!」
彩がまた言う。周平が少し笑う。
「私たち、もう一度『挑む』時かもね」
炯々とした目で彩が言う。
周平はジッと彩の目を見詰めている。
「ながらまんずな生き方じゃなく」
「ゆるぐなくても・・・か?」
「私たち、2人合わせてもうすぐ100歳なんだから」
「えっ? あっ、そっか」
「うん、人生後半生よ」
「今からの2人の人生を考えると何だかワクワクするね」
周平は子どものような目をしている。
彩はリビングの棚に置かれたロシア製の写真立てを見ている。その彩を周平が見詰めている。
「今日はいろんなことあったね」
彩が言う。
「一番はムスタキさんだな」
周平の頭のスクリーンにムスタキさんの姿が映し出される。
「信じられないね」
しんみりと彩が言う。
「うん」
「本当に『異国の人』になっちゃった」
淋しそうな声で彩が言う。
「あのへんてこりんな『支那の夜』ももう聞けないな」
「うん」
「かなめが引っ張っていったんだって、村の人が言ってた」
「・・・」
「2人は同級生で小さい頃から仲が良くて相思相愛だったんだって。でも、ムスタキさんが戦争に行くことになって、その間にかなめばあは見合いで結婚してしまったんだって」
「じゃあ、あながち・・・」
「うん、でもタマヨばあ、かわいそうだな」
「また未亡人が1人増えるわ」
「うん」
「ここに来て何人の人が死んだんだろうね」
「去年だけでも7人。今年に入ってこれでもう6人目だもんな」
「好きだったおじいちゃんやおばあちゃんがいなくなるってマジつらいよね」
「うん、仕方ないことだけど確かにつらい。出会わなきゃよかったと思うくらいだ」
庭の闇の中でガマガエルが鳴いている。
「23日がお葬式なんだって」
沈黙の後で彩が言う。
「また手伝いがいろいろあるみたいだな」
「頼まれたわ。明日から来てほしいって」
「そうか、じゃあ、また団子作るんだな。大丈夫か?」
「うん、けっこう要領覚えたから大丈夫よ。今回はスミさんやマチさん頼りになりそうもないし・・・」
「相当気落ちしていたね、彼女たち。ムスタキさんと同級生だったんだもんな。突然のことだし無理もないよな」
「うん」
「それに、作じいも何だかとても淋しそうだったね」
「ようし、こうなったら、団子はわたしに任せなさいって感じよ!」
しんみりムードを断ち切るように彩が言う。
「わっ! 頼もしい!」
「うん、そっちは?」
「ああ、俺も忙しくなりそうだ。ようし、俺も頑張るぞー!」
周平が力こぶを作った。
「一三先生」
「えっ?」
「また寝られなくなるね」
彩はそう言ってクスクス笑った。
チリン、チリリリン・・・。
風鈴が鳴った。蚊取り線香の灰がパサッと下に落ちた。風が出てきたようだった。
「そろそろ寝なきゃな」
10時半を回った時計を見ながら周平が言った。
「そうね」
彩はそう言ってコーヒーカップを持って立ち上がった。
△このページのトップへ
7『寝しゃべり2』
寝床に入っても2人の会話は途切れなかった。
井戸水を入れた湯たんぽは2人が考案した暑さ対策グッズだった。その上にふくらはぎを載せながら、彩は古井戸の前で作之進が話していたことを周平に教えた。
「へえー、村八分ってそういうことだったんだ」
周平は初めて聞く村八分の詳細に聞き入った。
「うん、秋塚厳兵衛っていう人の『いいふりこぎ』がそもそもの原因みたいね」
「地位とか名誉とか、それも人間の欲の一つだもんな」
「うん、OL時代、名刺にいっぱい肩書き書いてある人って嫌いだった。等々力小学校PTA役員とか川崎フロンターレサポーターとか裏にまで何十個も。そういう人のこと『ミスター肩書きさん』って呼んでた。軽蔑を込めてね。『私は星野彩です』でいいじゃんね」
「ワダスはタワスって人もいるなあ」
プッ!
2人同時に吹き出した。
ガダガダガダ・・・。
窓が鳴った。風が強くなったようだった。サッシのすき間から吹き込んだ風が蚊取り線香の煙をかき乱した。
「また荒れそうね」
彩が窓を見ながら言った。
「村の人が言ってたんだけど、今年の夏は天気が怒ってるって」
「天気が?」
「うん、怒ってるって。だから人が死ぬって」
「怖いね」
「こんなふうに続けざまに人が死ぬってことは、きっと何か原因があるって」
「えっ? 原因?」
「うん、それは貴志さんたちが十六団子や念仏を拒んだからだって、そう言うんだ」
「何か横溝チックだね。怖ーい!」
彩はブルッと身震いした。
「明日の早朝、みんなで念仏をしに行くらしいよ。寝起きを襲うって誰かが言ってた」
「貴志さんちに?」
「うん、五徳をかぶってロウソク灯して・・・みたいな」
周平はわざと『修学旅行の怖い話モード』の声色で言った。
「ひぇー!」
ザザザザザザザザザ・・・。
雨が降り出した。遠くで雷が鳴っている。
「ねえ、それ行かないでしょ?」
「うん、行かない、ちょっと怖い」
周平がわざと肩をすくめると、彩は安心したようにフッと笑った。
「そろそろ寝るか?」
周平が電気を消そうとした。
「うん、あっ、その前に一つだけ聞いていい? FBI捜査官の捜査報告」
周平の目が輝いた。
「聞きたい?」
「うんうんうん」
彩の目もギラギラしている。
「凄惨な最後だったよ」
「えっ?」
「流血のラストシーン!」
周平はまた例の声色を使った。
「俺が行った時、3人とも席に着いてるのね、ちゃっかり」
「3人も?」
「そうなんだよ。しかも彼らほとんど濡れてないの」
「えっ? 何で?」
「自分たちだけ傘持ってたから」
「ずっるー!」
「でも顔中ヒルにやられて血だらけでさ、テーブルクロスが血で真っ赤!」
「ひぇー!」
「そんでもむしゃむしゃ食ってたんだけどさ、さすがに途中から顔がパンパンに腫れてきて病院に行くって帰ったけどね」
「そりゃそうだ、中川さんも迷惑だわ」
「でも帰り際にこう言ってんの、割烹の女将に」
「何て?」
「残りの料理は包んでくれって」
「あきれた!」
天井を見ながら彩が言った。屋根を叩く雨の音が大きくなった。雷の音は小さいが今夜は風が強く吹いている。
「あと、美樹さんのお父さんにお酌された。案外元気そうだったから安心したけど『美樹をよろしくお願いします』って何度も頭を下げられてさ。彼、すっごく恐縮してんのね」
「ん・・・」
「それから美樹さんの会社の人とも話したんだけど、もうすぐデスクになるだろうって言ってた」
「・・・」
「あっ、そういえば自治会長の団子取れたの? 顔にベチャーッて付いてたやつ、あれひどかったなあ」
「・・・」
「ねえ、あれ取れた?」
「クゥ、クゥ・・・」
彩はいつの間にか眠ってしまったようだった。
△このページのトップへ
8『喪主たち』
「182万4000円か。そっちは?」
香典を計算し終えた貴志が言った。
「203万6000円ってとこ」
支払いを合計した美樹が言った。
「20万のマイナスだな」
貴志が電卓をしまいながら言う。
「うん」
「葬式でマイナスってのも珍しいな。坊主の70万と割烹の80万。それから葬儀屋か、大きい所は」
「うん」
「坊主丸儲けってほんとだな。あんななまくら坊主に70万なんてさ」
貴志はそこだけが釈然としない。
「ふう〜、終わった、終わった」
美樹はそう言ってソファーにゴロンとひっくり返った。
ザザザザザザザ・・・。
雨が降っている。仰向けになった美樹の耳がその音を捉える。
「明日、銀行に行かなきゃな」
貴志が分厚い札束を輪ゴムで留めながら言う。
「10時よ」
美樹がつぶやく。
「えっ?」
「10時に火葬」
「えっ?」
「ジャムの」
「うそっ!」
「・・・」
「どこで?」
「マンション」
「マンション?」
「火葬車が来る」
「火葬・・・シャ?」
「うん」
ザザザザザーッ・・・。
貴志は立ち上がって冷蔵庫を開けた。
「ゴリラまで焼けるらしいよ」
「ゴリラ?」
「うん、そう言ってた」
「ホントかよ。そもそもゴリラなんてペットにできんの?」
缶ビールを2つ手に持った貴志はそう言って、美樹に1つ差し出した。
「行こう」
缶ビールを払いのけて美樹が起き上がった。
「えっ?」
「早く支度して!」
「今から?」
「うん」
「明日でいいだろう」
手に持った缶ビールを見やりながら貴志が言う。
「また嵐になったら帰れないよ」
美樹はそう言ってケータイを手に持った。
貴志は缶ビールを冷蔵庫にしまうと、慌てて札束をバッグに入れた。
「あのババア、やっぱり部屋に入ったよ」
寝室の前を通る時、表情のない声で美樹が言った。
「・・・」
家中の明かりを全部消して靴を履いた貴志は、『さやか苑』と書かれた黄色い傘を1本手に取った。
△このページのトップへ
9『ヌーとボー』
午前2時。謎の徘徊者ヌーはガサゴソと天井裏を抜け出した。ヌーは壁を伝って下りる時に、あやまって尻から地面に着地した。家に電気がついてなかったせいだ。ヌーはぬかるみに足を取られながらタマヨの家に向かった。タマヨの家には電気がついていた。枕机の前で、タマヨが放心したように背中を丸めて座っていた。
(悪ぐ思うな。どっちみぢあどでみんなで遊べっからな)
ヌーはタマヨの背中に向かってそう言った。
ゴソゴソゴソ・・・。
その時、壁を伝って下りてくる者があった。
(ボーッ)
ヌーが言った。
(ヌーッ)
ボーが言った。
2人は手を握って歩き出した。
謎の徘徊者ヌーと謎の徘徊者ボーは、まず沢の目小学校に行った。そして古タイヤの前に立った。ボーは上機嫌で古タイヤの上に上がると、その上でピョンピョンと飛び跳ねた。ヌーはタイヤに座って黙ってそれを見ていた。6回ほど飛び跳ねたところで、ボーはツルッと滑って尻から地面に落ちた。
それから2人はブランコに乗った。座ったまましばらく仲良く揺れていたが、ボーはいきなり立ち上がって立ちこぎを始めた。
ギーッ、ギーッ・・・。
ブランコのさびたチェーンがきしみ音をたてた。ボーの体が地面と平行になった。それでもボーはこぎ続けた。
バッダーッン!
ボーは空中で1回転して地面に落下した。
この日つごう3回目の落下だったがボーは頑強だった。
2人はグラウンド脇の並木道を手をつないで歩いた。沢の目川が望める土手の大きな桜の木の下で、ボーはヌーのおでこにチューをした。
2人はモジモジとはにかみ合いながら土手を下りた。
それから一気に走って愛宕村に戻った。おせどの所まで来ると、ボーはヌーをおんぶして墓地へと下っていった。
ヌーは『宮下家之墓』と書かれた墓石の前に立ってジッと動かない。ボーもヌーの後ろからそれを見守っている。
ザザザザザザーッ・・・。
ピガッ!
ドドドドドーンッ!
突然激しい雷雨になった。
ボーは墓石に付着している団子の破片を引きはがして手に持つと、それを半分にしてヌーに渡した。そして残りを自分の口に入れた。ヌーはその団子を乱暴に放り投げるとズンズン来た道を引き返した。ボーはその後を追いかけた。
謎の徘徊者ヌーは、貴志の家の垣根をドサドサとまたいで敷地に入ると、うっそうとした庭木の間をかいくぐり、道路の脇に生えている大きなアカマツの老木に手を掛けた。
そして、それを思い切り揺らし始めた。
それと連動するかのように、ものすごい風が北から吹いてきた。嵐になった。
ヌーは何度も何度も木を揺らした。
ボーも手伝って一緒に揺らした。
松の老木がワサワサと揺れ出した。
荒れ狂う暴風雨の中、謎の徘徊者2人の謎の共同作業が続いていた。
バギバギバギバギッ・・・。
やがてアカマツの老木は、根元から1メートルくらいの所からササミジャーキーを裂くようにして割れるように折れた。
共同作業をなし終えた2人は、道の向こうに雨合羽を着た男の影を見た。新聞配達のタワスだった。『第2部第3章』完(まだまだ続きます!)
△このページのトップへ
『第2部第4章』へ