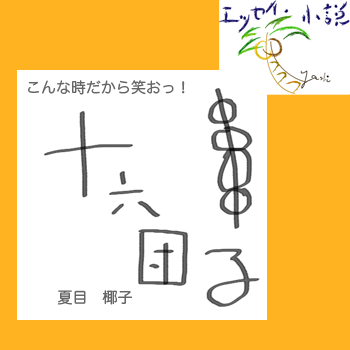★第1章は何やら不穏な立ち上がりでしたね。これから始まる事件を予感させます。いよいよ『十六団子』をめぐる奇想天外なストーリーが展開し始めますよ!(作者注釈)
第1部〜第2章『団子3人衆はツヨイのだ!』
1『未亡人倶楽部』
昨夜の豪雨は上がり、また青空が広がった。朝早くからアブラゼミが鳴き、ドクダミの匂いを強烈に含んだ水蒸気が地面からムンムン立ち上っている。
畑野のり子の運転する白い軽トラックが、集合場所である作之進の家に到着したのは朝7時前のことだ。
今年72になるのり子は、5年前に夫を胃癌で亡くした。スミもそうだが、村にはこうした未亡人が12人もいて、『愛宕村未亡人倶楽部』なる組織を作っていた。その生みの親は宮下かなめだった。彼女たちは、暇さえあれば寄り集まってお茶飲みをしたり、漬け物の品評会をしながら日常のうさ晴らしをし合った。また、年に1回は、積み立てたお金で温泉旅行にも出掛けた。村には『婦人会』という組織もあり、人数的にはこちらが圧倒的多数を占めていたが、その行動力と発言力、もしくは「ずうずうしさ」において、未亡人倶楽部のパワーには到底かなうものではなかった。
長年その会長を務めてきたのは、創設者でもあるかなめだったのだが、彼女がボケて老人ホームに入ってからはスミがその座に就いていた。未亡人歴5年ののり子は、会の中ではまだまだ新参者の部類だった。
のり子は軽トラックのエンジンを切ると、助手席からサヤエンドウの入ったビニール袋を小脇に抱えてクルマを下りた。
「よう、おはようさん!」
物干しに洗濯物を吊るしていた作之進の妻、マチが声を掛けた。
「おはよう、今日も暑ぐなるなあ。ほれ、これ、少しだども」
のり子はそう言って袋をマチに渡した。マチはそれを手に取って、
「わあ、立派なヨサグ豆だごど!」
と言って驚いた。エンドウ豆のことを村ではヨサグ豆と呼ぶ。年に4回も穫れることから「四作」と言うらしい。
「おめえんどこさも、いっぺえあるべども」
「いやあ、あるにはあるがこんな立派じゃねえよ。のり子は何を作らせても本当に上手だなあ」
マチはまた褒めた。
「それほどでもねえが・・・」
血圧が高く、いつも腫れぼったい顔をしているのり子の頬に赤みが差し、口はスイカの皮のように丸く弧を描いた。
「ほんとにたいしたもんだよ。のり子は村で1等賞さ」
そう言いながらマチは空になった洗濯かごを片付けると、のり子を家の中に招き入れた。のり子は上がりかまちに腰掛けると、手ぬぐいで首筋の汗を拭いながら、
「スミはまだが?」
と聞いた。
豆を冷蔵庫に入れて戻ってきたマチは、
「ああ、ああ、じき来ると思うよ」
と言ってのり子の隣に座ったが、急に思い出したように真顔になって、
「ところで、のり子、猿又橋流されたって本当かい?」
と聞いた。
「んだがら、おらビックラこいだよ。行ったら橋ねえんだもの」
のり子は、言葉とは裏腹にのんびりした口調でそう言った。
猿又橋は村に掛かる3本の橋の中で最も下流にあり、のり子の家からも近かった。橋の名前の由来は、昔の人がサルマタで遊泳していたもんだとか、山から猿がまたいで渡った橋だとか、いろいろな説がまことしやかにささやかれていた。
「ありゃー!」
と言ったままマチは絶句した。
「おらの田んぼもドップリ水浸しだ」
のり子はケロリと言って、マチの顔を見た。
「ありゃー!」
「田さ流木いっぺえ流れてきてな」
マチは、何度もコックリコックリうなずいた。
「あれだけ降ればなあ。おらの田んぼは大事に至らなかったようだけど、そりゃ大変だったなあ」
マチは、さも気の毒そうにのり子の顔を見た。
「だども、あれだけ流木あれば、今年の冬は薪の心配ねえよ」
そう言ってのり子は「あっはっはっ!」と豪快に笑った。いかにも未亡人倶楽部のメンバーらしいそのサバサバした態度に、マチは気圧されて目を丸くした。
その時、玄関先で何か動く気配がした。マチとのり子が目をやると、誰も乗っていない自転車が、目の前をスーッと横切って止まった。
(はて?)
2人は驚いて顔を見合わせた。
その時、自転車の陰から声がした。
「腰痛え、腰痛え」
スミの声だった。スミはただでさえ小さかったが、腰がほぼ直角に曲がったいる。そのため、自転車を押してやってきたスミの頭はサドルよりも低くなって、マチたちの方向からはあたかも無人の自転車が動いているように見えたのだ。
「プッ!」
マチとのり子は同時に吹き出した。
「なーに笑ってるんだ?」
そう言いながら、スミはサドルの下から2人を見上げると、つま先立ちになって思いっきり自転車の前かごに手を伸ばした。その格好は、今では村の伝説となった、かの『タメばあ物干し事件』で、スミが昭介のクルマに手を挙げた時と同じ、まるで釣り上げられたザリガニのようだった。やっとこさつかんだザリガニの手には、えさのイカにも似た白い袋が握られていた。
「お、おはよう、スミ。おめえ、と、と、透明人間かと思ったよ。なあ、のり子」
マチは、そう言って腹を抱えて笑った。のり子も真っ赤になってこらえ笑いをしている。
「なーに、そんたにおかしいんだべ」
スミはガニ股で玄関の敷居をまたぐと、「よっこらしょ」とマチの隣に腰掛けた。
「ほれっ、団子の粉だ」
スミが白い袋を差し出した。袋の中には餅米を挽いた白い粉が入っていた。
「も、持ってきたのかい?」
まだ笑いが収まらないマチは、あふれ出た涙を手の甲で拭き拭きそう言った。
「ああ、どうせ『銭の城』さは餅米なんかねえに決まってるがらな。うるち米は、マチ、おめえんとこさあんべ?」
「ああ、あるにはあるけど粉に挽いてねえよ」
「米ぐれえ、向こうさもあんでねえのが?」
のり子が口を挟んだ。スミは首を横に振った。
「いいや、うわさじゃあ、あいづらパンどスパゲッツだがっつうものしか食わねえっていうど」
「何だ? スバゲッツって」
のり子が聞いた。
「南蛮人のソバだ」
スミがいい加減なことを言った。
「ソバゲッツが?」
のり子が意味不明なことを言った。
「とにかぐ取りあえず用意してくれや。あどで誰がさ頼んで挽いてきてもらうべ」
スミはそう言うと、自分の腰を両手でパンパンと2つ叩いた。
「腰痛えのが?」
のり子が言った。
「ああ、今朝こっ早くから流木集めでだがらな」
「ありゃー! おめえんとこもかい?」
ようやく笑いの収まったマチは、今度は気の毒そうな顔でスミを見た。
「いや、おらの田は水上がらんかったもんだがら、岩之助の田さ入って集めだのさ」
「あいい、人の田さ入ってかい?」
「ああ、向こうだって助かるべよ。岩之助んとこは油のストーブだがらな」
スミはケロリと言った。
のり子は、さすが会長は違うという顔でスミを見ていた。
「とごろで、あんだけ団子は要らねえって言い張ってだアバが、今度は『やっぱり団子はお願いします』ってんだから、とんだお笑いぐさじゃねえか。なあ、マチ」
スミは含み笑いを浮かべながら言った。
「きっと、親戚中から猛反対されたんだべな」
マチが言った。
「あったりめえさ。どごの世界に十六団子やらねえなんてことがあるもんか」
「だども、団子はお願いしますとは言ったが、手伝いは要らねえ、留守番だけだとも言ってなかったか? のり子はどう聞いてる?」
マチに水を向けられたのり子は、ちょっと考えてから、
「あんまり早口で、おらさっぱ分がらねがった」
と言った。
スミは目を狡猾に光らせながら、
「本当は、おらだぢに来られるのが迷惑なんだべ。団子も手伝いも何もかも要らねえってのが本音の腹さ」
と言って、餅米の粉が入った袋をにらみ付けた。
「だがそうはいがねえ。これは死んだかなめのためにやるごどだ。決してアバのためではねえ」
スミはそう言って粉の袋をパンッと叩いた。
「マチ、そろそろ『銭の城』さ出掛けるど。早く支度しろ」
スミが進軍ラッパを鳴らした。
「おう、ほしたら今支度してくっから」
マチは立ち上がって台所に消えた。
夏の空から陽光が庭先に延び、ムクゲの葉の輪郭をくっきりと浮き上がらせていた。
「暑ぐなりそうだなや」
のり子が言った。
「ああ、流木もよう乾ぐわ」
スミは庭を見ながら笑わずに言った。
マチはなかなか現れなかった。
△このページのトップへ
2『団子3人衆』
作之進の家から貴志たちの家までは距離にして200メートルほどしかなかったが、彼女たちの歩調はいかにものろく、特にマチは歩くのが遅かった。
彼女は昔の女としては背が高く5尺6寸もある大女だったが、性格がおうようでおっとりしたところがあり、物言いも動作もゆったりとして緩慢だった。それは、作之進に嫁ぐ前の彼女が、隣村の大地主の令嬢だったことにも起因している。マチは、トレードマークの白い頭巾をかぶって、長身の体を揺するようにのったりのったり歩く。
その隣で、腰に手を回し、顔を地面すれすれに近付けながらペタペタペタペタと小刻みな早足でスミが歩く。それはまるで、スローモーションと早送りの映像を並べて見ているようでもあったし、見方によっては、ねずみ男が犬の散歩をしている光景に見えなくもなかった。
てっぷりと太ったのり子がふんずり返って、のんびりとその後ろに続いた。
団子作りに動員された3人が貴志たちの家に着いたのは、8時を少し過ぎた時刻だった。
彼女たちを最初に迎えたのは星野彩だった。
「おはようございます。お世話になります」
出迎えたのが美樹ではなく彩だったことに少し拍子抜けした3人だったが、マチはそれでもニッコリ笑って、
「あらー、彩ちゃんじゃねえが。おめえも来てたのかい?」
と言った。
「はい、団子のことは全然分からないんで教えてください!」
「したら、上がらせでもらうべ」
スミはいち早く靴を脱ぐと、餅米の入った袋を手にしてズカズカと這うような格好で居間に向かった。居間では、貴志と葬儀屋の二所谷が差し向かいで打ち合わせをしていた。人の気配に気付いた貴志が、振り返ってスミたちに声を掛けた。
「ああ、これはどうも。皆さん、どうもお世話になります」
そう言って貴志が立ち上がろうとした時、やおらスミが言った。
「アバいねえのが?」
(アバ?)
一瞬誰のことかと思った貴志だったが、すぐに美樹のことだと気付いて、
「あっ、はい。ちょっと用ができて。あのう、いろいろなことは、そちらの星野さんに教えてあるので聞いてもらって、適当にお願いできますか?」
と言った。
「適当にだと!」
スミが喧嘩を売るような目で貴志をにらんだ。険悪になりそうな雰囲気を察したマチは、取りなすように言った。
「あいい、米持ってきたんだけども、誰が挽いてきてもらわねえどなあ」
「米? 挽く?」
貴志はポカンとした顔で聞いた。
「ああ、粉っこさ挽いてきてもらわねえど、団子作れねえべ」
「はあ・・・。それはどこへ行けば・・・」
「長裾町の入り口に、大正御領旗が並べられた大きな屋敷があって、それはすぐ分がると思うんだけど、屋敷の長い塀の米倉部落寄りに、こう小さい字で『梅売ります』って書かれた看板があってさ。そっから入っていくんだが、言ってるごど分がるかい?」
「・・・」
貴志は首を傾げた。
じれったそうに今度はのり子が言った。
「マチ、あれは『梅売ります』ではねえど。『小梅買います』だど。しかも、その看板の入り口から入るわけではねえんだ。おら、間違ったごどあんだけど、そのもっと左に別の門があってさ。石の門のでっけえの。そっから入るんだが、声掛けてもいねえごどが多いんだ。そういうときはさ、大体裏の作業場のほうさいるから、おっきい声で叫ぶか、まあ、あれだ、面倒くせえからさ。おらなんか直接作業場に入っていってしまうのよ。そのほうが早えから」
貴志はますます何が何だか分からなくなってきた。
その時、二所谷が口を挟んだ。
△このページのトップへ
3『木之倉与左衛門商店』
「ああ、『木之倉与左衛門商店』のことでしょう。大正時代に創業した由緒ある商店ですよね。先代が亡くなられた時はうちが葬儀を執り行いました。いやあ、立派な葬儀でしたねえ。あそこで梅も売ってるんですか?」
「違うって、梅干しさ使う小梅を買ってるんだよ!」
血圧の高いのり子が、顔を真っ赤にしながらムキになって言った。
「あのう、彩さん」
貴志は彩に声を掛けた。
「はい」
「周平君にお願いできないかなあ」
「ええ、分かりました。私、ちょっと呼んできますね」
彩は素早くエプロンを外すと、
「冷蔵庫に麦茶がありますから、どうぞ飲んでて下さい」
と、スミたちに声を掛けて小走りに出掛けていった。
「そうだ、周ちゃんがいいよ。周ちゃんなら全部知ってるはずだ。うん、それがいい」
マチは大きくうなずいた。
「それにしてもアバはどこさ行ったんだ。こんな大事な時に」
スミは独り言を装って憎々しい口調でそう言ったが、それは明らかに貴志の耳に届くことを意識した意地の悪い言い方だった。
貴志はスミをにらみ付けたい衝動に駆られたが、グッとこらえて話を変えた。
「あっ、葬儀屋さん。どうも僕らがいると団子を作る邪魔になりそうですから、あちらの座敷に移動しましょう」
二所谷は「うん」とうなずいて、書類の束を抱えて立ち上がった。
△このページのトップへ
4『ジャムの消息』
美樹は、板橋要三の家の玄関の戸を乱暴に開け、バタバタと上がりかまちを駆け上がると、血相を変えて居間に飛び込んだ。
「お父さん、ジャムは? どこ? どこにいるの?」
息を切らしながら美樹が聞いた。
要三は座椅子に座って新聞を読んでいたが、美樹の声に驚いて視線を上げた。
「ほれ」
要三が伸ばした右手の先にジャムがいた。ジャムは茶色い座布団の上で力なくぐったりと横たわっている。
「ジャム!」
美樹が悲痛な声を上げて駆け寄った。そして、ジャムを抱きかかえようとして一瞬ためらった。それほどジャムは憔悴し切っていた。
「夕べから何も食わないんだよ」
座布団の脇には、皿に入った牛乳と手を付けていないペットフードの缶が置かれてあった。
「ジャム、ごめんなさい!」
美樹は、力なく横たわっているジャムを優しく抱き上げて抱擁すると、目から大粒の涙を流した。ほおずりしたジャムの体はまだ微かに体温を宿していたが、ジャムは目を開けることも美樹の声に反応することもなかった。
「お前のせいじゃないさ。これはもう寿命だったんだ。気にすることはない。それよりかなめさんのお葬式は・・・」
「とにかく、私、病院に!」
美樹は、ジャムを抱いたまま要三の家を飛び出した。
「ああ・・・」
心配そうに要三がそれを見送った。
△このページのトップへ
5『IHシステムキッチン』
麦茶を飲み終えた団子3人衆は、いよいよ台所に入り、IHシステムキッチンを前にして作業の打ち合わせを始めた。
「こいづ、何とすんだべ?」
取りあえず湯を沸かそうと思ったスミは、電磁調理器を前にして早くも固まってしまっていた。
「マチ、おめえ、分がるが?」
「ああ、これ電気のだべ。おらの家さもあるよ」
「ほしたら、おめえ、まず湯っこ沸かしてけれ」
「ああ、いいよ」
マチは、孫夫婦が購入した自分の家のクッキングヒーターのつもりでスイッチを探した。
「おやっ? ねえな」
美樹が選んだクッキングヒーターはデザインを重視した新式のものだったので、スイッチはすべてタッチパネル式になっていて、目立たない仕様になっていた。
「ねえって、何が?」
「うん? ボタンがねえんだよ。おらの家さあんのと違うわ。うん」
「したら、湯っこ沸かせねえべ。のり子、おめえ、分がらねが?」
目を丸くしてクッキングヒーターをのぞき込んでいたのり子は、
「どっからガス出んだ?」
と真顔で言った。
「もうダメだ」
スミは早くも白旗を上げたようだった。
「今、彩ちゃんくるから彩ちゃんにやってもらうべ、なあ」
マチはそう言って2人に視線を向けたが、のり子はじっとクッキングヒーターを見詰めたままだった。彼女は、やおら身を乗り出してヒーターの奥をのぞき込みながらこう言った。
「元栓どごさあんだ?」
△このページのトップへ
6『米の粉』
そこへ、周平を伴って彩が戻ってきた。周平は、仏に水を上げてから貴志にあいさつをした。貴志は、
「いやあ、周平君、すまないね。なんか、米の粉とかを挽かなきゃならないそうなんだよ」
と言ってから、含み笑いを浮かべ、
「あの団子のおばあさんたち」
と言って、居間のほうを指さした。
「それ、何とかお願いできるかなあ」
「はい、たぶん木之倉さんとこで挽いてもらうんでしょう。あそこなら何度か行ったことがあります」
周平が言った。
「そうそう木之倉与左衛門商店ね。ご存じですか? あそこの先代が亡くなられた時、うちが葬儀をやったんですよ。いやあ、立派な葬儀でした。何でも最近は梅なんかも売ってるそうですな」
二所谷が口を挟んだ。
(本当は小梅を買ってる、が正しいんだよな。梅干し用の)
どうでもいいことだと思いながらも、貴志はのり子の言ったことをしっかり記憶していた。
「へえ、そうなんですか。じゃあ行ってきます」
周平は、二所谷の言葉を軽く受け流しつつ立ち上がった。
「あっ、それから周平君。戻ったら声掛けてくれるかな。ちょっとお願いがあるんだ」
周平は、それにモンタージュ笑顔で応えると、騒々しい声が響くキッチンに向かった。
△このページのトップへ
7『朝礼』
団子3人衆の格闘は、彩が戻ってからも続いていた。
「朝早くからご苦労さんだな。米はどこだい?」
周平の声に一同が振り返った。
「あらっ、周ちゃん」
安堵した表情でマチが声を掛けた。
「米は、ほら、そごさあるがら」
「木之倉さんでいいのが?」
「うんうん、そうそう。おめえ分がるべ?」
「分かる、分かる。じゃあ、ちょっくら行ってくらあ」
「いねえどぎは、直接作業場さ回りな」
のり子が言った。
「おめえ、金持ってるか? 200円」
スミが言った。
「ああ、大丈夫、大丈夫」
周平は振り向きながら、手を挙げて答えた。
「あどで、ちゃんともらわねばダメだど。貴志がら200円な」
スミはしつこく言った。
「ああ、分かった、分かった」
周平の軽トラックを見送ってキッチンに戻った4人は、あらためて今日の打ち合わせを始めることにした。彩が合流してコンロが使えるようになったことで、団子リーダーのスミもがぜん元気を取り戻し、にわかにテンションが上がっていた。
「んでは、今から朝礼をやる!」
対面キッチンを挟んで向こう側に進み出たスミは、毅然とした声でこう切り出した。
△このページのトップへ
8『鍋、どごさある?』
「あー、本番は明日だが、今日もログゴに盛る団子を作る。出棺は1時だがら、遅くても12時半までには完成させねばなるめえ。逆算すっとあど3時間半しかねえ。粉っここねるのはおらどマチがやる。湯っこ沸かすのは彩。団子丸める時にのり子も手伝ってけれ。全体の責任はおらが受け持づがら、おのおのけがのねえように。以上」
スミは、滞りなく完璧にスピーチを締めくくった。その内容は全く非の打ち所のない立派なものだったが、なぜか今ひとつ説得力を欠いていた。その理由は、対面キッチンのこちら側にいる3人の視界にスミがいなかったからである。
「スミ、まず何がらやればいい?」
のり子が言った。
「粉っこ来るまで、湯っこ沸がせ!」
テキパキとスミが指示した。
「彩ちゃん、鍋、どごさある?」
マチが彩の顔を見ながら聞いた。
「鍋はここにあるって言ってました」
彩が機敏な動作でサイドボードの扉を開ける。
「なんぼでもおっきい鍋だぞ。おっきい鍋あっか?」
スミが言った。彩は幾つかある鍋の中で一番大きいものを取り出した。
「これは圧力鍋で・・・」
その鍋を一瞥したスミは、彩が言い終わらないうちに、
「ほんでねえ、その鍋でねえ!」
と言って彩の足元に突進してきた。そして、サイドボードに頭を突っ込むような格好で中を物色すると、
「こんたら鍋しかねえのが!」
と言って、大中小3点セットになったオレンジ色の鍋を取り出した。これらの鍋は皆IHクッキングヒーター用の、それも斬新なデザインのかわいらしいものだった。
△このページのトップへ
9『おっきい作業場』
村にはスミやのり子のように独り暮らしの老人も多かったが、彼女たちもかつては大家族で生活をしていたのでおのずと大鍋は必需品であった。また、アルミアルマイトの大鍋は日常生活のみならず、慶弔行事の賄い用や自家製味噌を作るための豆を煮る道具としても欠かせないものだった。
「どうしますか?」
鍋を手に取ったまま困惑しているスミに向かって彩が聞いた。
「しゃあねえ、これで何回も沸がすっかねえべ」
スミは3つのうちで一番大きい鍋と小さなやかんを彩に手渡し、
「この2つさ湯っこ沸がせ!」
と言った。彩は素早く鍋に水を入れ火にかけた。正確にはクッキングヒーターのスイッチを入れた。
一方、団子をこねる担当になったマチは、キョロキョロと辺りを見回して、
「スミ、さ、どごで作る、どごで作る?」
と言った。伸び上がるようにしてキッチンを眺めたスミは、ここでは無理だと判断し、
「床でやるべ」
と言った。そして、テーブルの上にあった新聞紙を持ってきて、キッチンと居間の通路の床にびっしりと敷き詰めた。
そうこうしているところへ、挽いた粉を持った周平が戻ってきた。
「やあ、ちょうど良かったよ。周ちゃん、ありがとな」
マチが大喜びで迎えた。
「いねがったべ。作業場さ入っていったのが?」
のり子が聞いた。
「いや、すぐ出てきたよ」
周平の答えに、のり子は少しがっかりした様子で、
「なら、いいが」
と言った。
「周平!」
スミが言った。
「おめえ、早ぐ行って200円もらってこい! 何もおめえが出すこたねえんだがらな。クルマの油代考えたら2000円もらったっていいくれえのもんだ。さあ、早ぐ行ってこい!」
周平は、スミの興奮を沈めるようにゆっくりとした口調で、
「分がった、分がった。今行ってもらってくるがら」
と言ってニコッと笑顔を作ると、
「それにしてもスミばあ、随分とおっきい作業場こしらえたなあ。これだば、お客さん通られねえべや」
と言って笑った。
通路をふさぐように陣取って座っていた3人は、お互いに自分の陣地の周りを見回して、
「あいい」とか「ありゃー、ほんとだなや」とか言って騒いだが、尻をもじもじさせただけで陣地を縮小する者は結局誰もいなかった。
△このページのトップへ
10『熟練の勘』
キッチンで湯を沸かしている彩に向かって周平は、
(大丈夫か?)
というふうに笑顔を向けると、彩もほほ笑みながら無言でうなずいた。
「じゃあ、団子よろしくな」
周平は全員に声を掛けてから貴志のいる座敷に向かった。
「粉、どのくれえずつやる? なんぼやればいいべ」
マチは、うるち米の粉を右手に、餅米の粉を左手に持ってスミに聞いた。
「なんもや、そいつをこう、このぐれえに対して、こいつをこう、このぐれえだべ」
マチから粉の袋を取り上げたスミは、熟練の勘を頼りにお椀ですくってドバドバッと粉を新聞紙の上にぶちまけた。スミは、何度かそんなふうにして配合を繰り返した。その動作は自信に満ち溢れたものだった。
(さすが長年の勘だわ。ちょっとまねできない)
彩は感心して見入った。
「マチ、なんぼになった?」
スミが急に手を止めて言った。
「えっ? なんぼって・・・あいい、なんぼだっけ?」
マチが狼狽して言った。
「のり子、おら、なんぼ入れだべ?」
スミは、今度はのり子に聞いた。
「なんぼって、そっちの袋がら8つだがど、こっちの袋がら・・・あいい、なんぼだっけ?」
のり子も首をひねった。
「彩、なんぼ入れだ?」
キッチンから見ていた彩だったが、突然そういうふうに振られるとは思っていなかったので、困惑して顔の前で手を左右に振った。
少し沈黙が流れた。
「ちょっと待で! こっちの袋何だっけや。餅米だったが?」
スミがにわかに取り乱しながら聞いた。
「ありゃー、そっちうるちでねえが?」
マチが答えた。
「あいーすかだね。んだば、もう少し餅米入れねば」
スミは、また袋から粉をすくってドバーッと入れた。
「ちょっと待で。そいづはうるちでねえが?」
のり子が口を挟んだ。
「ほれ、その袋さ何だか商店って書いてあるもの」
「ありゃー!」
「あいい・・・」
(この人たちは、この道のプロではなかったのか?)
キッチンからその様子を眺めていた彩は、急に不安を感じてきた。
△このページのトップへ
11『粉の硬さ』
配合のさっぱり分からなくなってしまった粉が、新聞紙の上におぼつかなく広がっていた。その時、何をどう思ったのか、マチが突然その粉をかき回し始めた。それにつられてのり子も両手でグルグル混ぜ合わせ出した。
「少し軟らけぐねえが?」
マチが言った。
「いや、硬えな」
のり子が言った。
(粉の状態でそんなことが分かるのか?)
「スミ、ほら、やっぱり柔らけえよ」
「いや、これは硬えな」
マチとのり子は、お互い根拠のよく分からない主張を繰り返していた。スミは、
「待で!」
と言って、かき回している2人の手を押さえ付けた。それから、おのおのの手を自分の口元に引き寄せて、人差し指を交互にペロッとなめた。
(うそっ!)
彩は、何か気味の悪い霊媒師でも見ているような、そんな気持ちになってちょっと鳥肌が立った。
「何とだ?」
マチが聞いた。
「うーん・・・」
「硬えべ?」
のり子が言った。
「うーん、まず、とにかくやってみでがらだ!」
(おいおい、大丈夫かよ)
彩は先行きに強い不安を感じてきた。
「スミ、軟らけがったべ?」
しつこくマチに聞かれたスミは、
「だがら、とにかくやってみでがらだってばよ!」
と、投げやりに言った。それから彩に向かって、
「やがんの湯っこ沸いだが?」
と、少し怖い口調で聞いた。
「は、はい! もう少しで沸騰するところです」
いきなり振られた彩は、一瞬たじろぎつつもそう答えた。
「ダメだ、ダメだ。あんまり熱いとダメなんだ。ダマになるがらダメなんだよ。少し水で薄めねば」
彩は、そう言われても一体どのくらい薄めるのか加減が全く分からなかった。詳しく聞こうとも思ったが、この粉の配合のように、恐ろしくあいまいな答えが返ってきそうだったので、適当に水道の水を入れてから、
「このくらいでどうでしょう?」
と言ってやかんをスミに差し出した。スミはやかんのお湯を湯のみに少し注ぎ、フーッと息を吹いて冷ましてから一息に飲んだ。
(まさか、「うめえ!」とか言わないでよ)
スミは、飲み終わって口をモゴモゴさせてから、
「うん、こんたもんだべ、彩、このくれえの湯っこ、もう一つ沸かしておげ!」
と言った。
彩の想像は外れたが、どうやらスミはのどが渇いていた様子で、湯のみにお湯をさらに半分ほど注ぎ、今度は冷まさずにゴクゴクとうまそうに飲んだ。心を落ち着けたスミは、やかんを持って新聞紙の上に座ると、まだ粉をかき回しているマチに向かって、
「マチ、おめえ、いづまでやってんだ。あどいいがら始めるど!」
と言った。そして、お湯を注ごうとして動きが止まった。
△このページのトップへ
12『ボール』
「ありゃっ? ボールねえな、ボール」
スミは彩のほうを見て言った。
「ボールですか?」
「うんだ。ボールねえと練らんねえべ」
彩は、キッチンの脇の扉を開けてそれらしいものを探した。赤い小さなボールが出てきた。それをスミに見せようと思って彩は少し躊躇した。
(ほんでね、ほんたら小せえんじゃダメだ)
そう言われると思ったからだ。そこで、さっきのオレンジ色の鍋も一緒に見せて、
「このボールよりは、こっちの鍋のほうがいいかと・・・」
と、遠慮がちに言ってみた。
「ほんたらものしかねえのが、こごの家は!」
案の定スミは、あきれたように言って眉をしかめた。
その時、マチが急にひらめいたように言った。
「おら、持ってくるわ、家さ帰って」
のり子は、いつもののんびりした口調で、
「何も、いいべや、その鍋でも」
と言ったが、マチは聞き入れなかった。
「いい、行ってくる。おら、あのボールでねえとダメなんだ」
「どうでもいいが、おめえ、早ぐ帰ってこいよ!」
スミの言葉に「ああ」と笑って答えたマチは、緩慢な動作でトレードマークの白い頭巾をかぶると、水蒸気が立ち上る庭の芝生を踏んでノッタリクッタリとした足取りでよろめくように出ていった。が、その後ろ姿はなかなか小さくならなかった。
(本当に、この人たち大丈夫だろうか?)
彩は、団子の完成に底知れぬ不安を抱き始めていた。
△このページのトップへ
13『真橋村の源蔵』
マチと入れ違いに源蔵がやってきた。源蔵はいつもの神経質そうな顔でキッチンをのぞくと、キョロキョロと周りを見回して、
「チッ、今日はどうもご苦労さんでごぜえます」
と言った。スミはキョトンとした顔で源蔵を見ると、ひらめいたように、
「あっ! おめえ、真橋村の源蔵でねえが?」
と言った。
「はい、どうも、この度は本当に、大難儀掛げます。チッ」
源蔵はそう言って会釈をした。
舌打ちをすることと顔が尖っていることは一緒だったが、彩が見た昨日の源蔵のイメージとは別人のような低い物腰だった。彩は源蔵に向かって言葉を掛けた。
「あっ、どうぞ。そちらでお茶でも」
「チッ、いやいや構わねえで、チッ」
今日の源蔵は遠慮までしている。
「団子作るのに邪魔になるべがら、おら、あっつさ行ってますから、チッ」
源蔵はそう言ってまた会釈をすると、座敷のほうに行こうとして立ち止まった。
「チッ、美樹はおらんですか?」
「ああ、何だが用あって、い・ね・え・ん・だ・ど・よ!」
スミが嫌みを込めて言った。
「チッ、チッ、チッ、チッ、いねえ? チッ、チッ、チッ、チッ・・・」
源蔵の顔が、また昨日のいらついた神経質な顔に変わった。彩は、何か不穏なことが起こりそうな予感がした。スミは不気味な含み笑いを浮かべて座っていた。一方のり子は、源蔵がいなくなったのを確認してボソリつぶやいた。
「何だって、ああ、チッ、チッ、チッ、チッってうるせごだ」
△このページのトップへ
14『道秋、上機嫌』
そこに、斎田道秋が照子を伴ってやって来た。斎田道秋は今日も上機嫌に笑顔を振りまくと、例によって一方的にベラベラしゃべり出した。
「いやあ、いやあ、どうも、どうも、どうも。皆さん、村の方? 村の女性陣って言ったほうがいいのかな? 年齢もさまざまで、ねえ。娘さんもいれば、あっ、あなた。あなた昨日もお会いしましたねえ。そう、イズミさんだ、イズミアキさん。ねえ」
(ホ・シ・ノ・ア・ヤです!)
「いやあ、いや。お若い方もおれば、熟女もねえ。熟女ってのも何だかあれだねえ。熟した女ってのも何かこういやらしい、いやらしいっていうかねえ、イチヂクの実じゃないんだからねえ。そうだな、昔はさあ、昔は娘さんだったって方だもんねえ。はははっ、ご苦労さんですね。夕べは雨でねえ、いやあ雨なんてもんじゃなかったわね。豪雨、あれ集中豪雨っていうんだよねえ。ものすっごい雨で、この辺もあれでしょ? 浸水とかあったんですか? うちは何とか。ほら、うちは高台っていうか、いくらか土地が高い分助かったんだけどねえ。いやいや、高いったって、違うの違うの値段じゃなくて。いやもちろん、そりゃ値段も少しはねえ。何て言うかこう・・・、いでっ!」
「あなた!」
斎田道秋は照子につねられて黙った。しかし、それも一瞬だった。
「ちょっと、すみませんねえ。ちょーっとここ通してもらえますかあ?」
道秋はそう言って、新聞紙を敷き詰めた通路を通って、昨日から勝手に指定席と決め込んでいる白いソファーのほうへと進み出ようとした。
「ちょーっと、おばあちゃん。すいませーん。ちょーっと、いいですかあ?」
しかし、スミものり子も全く動く気配がない。道秋はスミの肩に手を掛けた。
「ねっ、おばあちゃん。ちょーっと、すこーし、すこーし」
スミは動かない。道秋は、割って入ろうと右足をスミと壁のすき間に強引に差し入れた。その時体のバランスが崩れた。
△このページのトップへ
15『粉ほろげ!』
「うわっ!」
「きゃあ!」
ドデッ!
ドッデーン!
道秋は、前のめりになって粉の上に倒れ込んだ。道秋に引っ張れる形で照子も横向きに粉の上に倒れた。
「あーっ! 粉、粉、粉」
のり子は、飛び散った粉を懸命に集めている。
「おいっ!」
粉を払いながら立ち上がろうとしている道秋と照子に向かってスミは言った。
「粉、全部こごさ戻せ!」
服だけではなく顔や髪の毛にまで付着した粉を払いながら、道秋はムッとして立ち上がった。
「ちょ、ちょ、ちょっとねえ。あなたねえ。私、転んだんだよねえ。少しはねえ、心配してもらわんとねえ。私だけじゃないよ。ほら、私のねえ、大事な妻もねえ、転んだんだよねえ。この人も」
道秋は、そう言って照子の手を引っ張った。
「いいがら、黙って粉ほろげ!」
スミは冷静に言った。彩はただならぬ空気を察したが、かといってどうしていいのか分からなかった。
「あのねえ、私ねえ。こう見えても昔議員やってたんだけどねえ。こういう屈辱は初めてだなあ。初めてっていうか、ありえないことだ。だって議員だったんだから、議員。妻は議員夫人だ」
「それがどうした!」
「どうしたって、あなた何を言ってるの? 私がねえ、ちょっとつまずいただけでもねえ、秘書がねえ、大丈夫ですかってねえ、心配してくれるのよねえ。議員だから私。大事な人っていう意味なのね。そう、重要な逸材っていうかねえ。そういうベイリインポタンな人と比べてさあ、粉はねえ、また買えばいいじゃないの。そんなものは安いでしょ? フーッ。ほらこの通り、粉なんだから。せいぜい何百円でしょ。全く重要じゃなーいの。ノッツベイリ・・・インポタン」
「何だ? インポって」
のり子がボソッとつぶやいたが誰も反応しなかった。
△このページのトップへ
16『険悪な空気』
「何なら私弁償しましょうか? そもそも、あなたがねえ、どけなかったからこういうことになったんでしょう。もし、私たちがけがでもしたら、あなたねえ、訴えられますよ。傷害罪だもの、こういうの。れっきとした傷害罪だよねえ、照子」
照子は黙って服に付いた粉を払っていたが、黒い喪服に付いた粉はなかなかきれいに落ちなかった。
「ちょっとすみません。何か拭くもの貸していただけるかしら?」
照子は、キッチンにいる彩に向かってこわばった顔で言った。
「それから、この粉は弁償させていただきます。一体お幾らかしら?」
照子はハンドバッグを開けながらスミに聞いた。
「金の問題じゃあねえんだよ!」
スミが言った。
「この粉がねえど、団子が作れねえのさ。まあ、今日の分は残りの粉で何とがすっけど、明日の十六団子の分が間に合わねえ。今日中に、うるちど餅米、半升ずづ挽いで用意して持ってこい!」
「だから、それをあなたたちがやっていただけませんの。お金は払いますから」
「だがら、金じゃあねえっつってんだよ。いっくら金積まれたってそういう暇がねえんだよ。おめえらみてえにのんきに茶飲みしてる奴らとはわけが違うんだ!」
「じゃあ、どうしろとおっしゃるんですか!」
照子はこめかみに青筋が浮き出している。
「おめえら、行ってこい!」
スミは低い声でそう言ってから、今度は怒気を込めて叫んだ。
「うるちど餅米、半升ずづ挽いで、こごさ持ってこいってんだ!」
「・・・」
険悪な空気が部屋中に充満していた。照子とスミの攻防をジッと聞いていた道秋が口を開いた。
「あれだな、照子。このばあさんとしゃべってても、さっぱりらち明かないからさ。ねえ、こうしよう。そう、この場合はねえ、喪主にねえ、喪主は貴志君だけどもさあ、責任者なんだから、貴志君に入ってもらってねえ。裁き、裁きっていうか、まあ解決策をねえ、考えてもらう。そう、それがいいと思うなあ。うん。全然らち明かないからさ、このばあさんでは。全然、全く、ダメダメ。ちーっともらち明かないわ、これじゃあねえ」
道秋はそう言って、いまいましげにスミをにらみ付けると、照子の手を引いて部屋を出ていった。その2人の背中に向かって執拗にスミが言った。
「おら、議員ほど虫の好かねえ者はねえんだ。金で何でも解決すっと思ってるバーガな奴らよ。フンッ、どうでもいいがら、うるちど餅米の粉、早ぐ持ってこいってんだ!!!」
△このページのトップへ
17『火葬の打ち合わせ』
座敷では、貴志と二所谷に周平が加わって今日の火葬の打ち合わせが行われていた。
「じゃあ、会葬御礼はこれから届くわけですね」
貴志から火葬場での受付を頼まれた周平が葬儀屋の二所谷に聞いた。
「ええ、11時ごろには届く予定です。取りあえず今日は20個手配しておきましたが、喪主さん、それでいいですか?」
二所谷が貴志に確認を求めた。
「そうですね。まあ、火葬場に何人香典を持ってくるか僕にもさっぱり分かりませんが、そのくらいあれば足りると思います。基本的に葬儀に来られない村の人だけだと思いますから」
「まあ、余ればまた明日使えますからね。多めかもしれませんがそのぐらい用意しておきましょう。あっ、それから確認ですが、会葬御礼のお品は2000円の干し椎茸で間違いなかったですね」
「ええ、それでお願いします」
二所谷は、チェックリストに何やらミミズの這ったような字を書いた。貴志がよく見ると、「かいそうおんれい(ほししいたけ)」と全部ひらがなの文字が並んでいた。
(この人は仏事には詳しいかもしれないが、漢字の書き取りは小学生以下だな。そう言えば、『三具足』や『四華花』の漢字を質問をした時も、彼はパンフレットの文字を指し示しただけだった)
貴志はひそかにそう思った。
二所谷は思い出したように言った。
「あっ、それから会葬礼状ですが、今日はどうしても印刷が間に合いません。明日の本葬までにはもちろんお持ちしますので、今日のところは品物だけ渡していただけますか」
貴志は、二所谷にうなずいてから周平を見て、
「じゃあ、周平くん。そういうことで」
と言った。
「はい、分かりました。あと、会葬者の芳名帳も必要ですよね。筆とかも」
周平が言うと、待ってましたとばかりに二所谷が言った。
「はいはい、それでしたら全部こちらに用意してあります。芳名帳が3冊と筆ペン2本、それからマジックペン2本に、ええと細字のサインペンなども。はい、このとおり。ご夫人は案外細いのを好むんですよね。私などもどちらかと言うとそっち派なんですけど」
貴志は、二所谷が細ペンで書いた芳名帳の文字を想像して是非見てみたい衝動に駆られた。貴志がそんな余裕を持つくらい3人の打ち合わせは順調に進んでいた。
(うんうん、万事上手く運んでるぞ)
そう思うと貴志は、徹夜明けの疲労感さえ和らいでいくような気がした。そんな貴志がホッと気を緩めて、彩が持ってきてくれた枝豆を口にほお張った時だった。居間のほうから、いつものチッという舌打ちをしながらやってくる者がいた。その男は、あいさつもそこそこに貴志に向かって、
「チッ、おい、貴志! 美樹はどごさ行った!」
と言った。泰平の眠りを覚ますこの男の出現が、貴志の穏やかだった気持ちを一瞬にして暗転させた。
△このページのトップへ
18『遺影写真』
「あっ、ちょっと用があって・・・すぐに戻ると思います」
そう答えた貴志の鼻先に、ギュッと顔を近付けた源蔵は、舌打ちを8回しながら至近距離で貴志の顔をにらんだ。
「チッ、遺影写真はどうなった。あん?」
「ああ、遺影写真でしたら葬儀屋さんが、ねえ」
そう言って貴志は二所谷を見た。二所谷は源蔵を一瞥して、こいつは昨日チッチッチッチッ騒いでいた男だなと思った。
(こういう男には、キチンと折り目を正しておくことが得策だ)
二所谷は、長年の営業経験で学んだ知恵でそう考えた。彼は、ズボンのポケットから名刺を1枚取り出すと、
「わたくし、葬祭センタービューティフルセレモニーのフタドコロタニショウジロウと申します。はじめまして」
と言って、いんぎんにそれを差し出した。源蔵は、名刺いっぱいに並んだおびただしい数の文字をへきえきしつつ眺めていたが、やがてチッを4回続けて、
「えらぐ長えな」
とつぶやいた。
「そうでした、肝心の遺影写真がまだでしたね。遺影写真でしたら、はいっ、ここに!」
二所谷は段ボールの箱から写真を取り出すと、貴志たちが見やすいように向きを変えてテーブルの上に置いた。
「なかなかいい写真でしょう?」
自信たっぷりに二所谷が言った。
「笑顔がいいですね」
周平が言った。
「ねえ、若返った感じになったね」
貴志が満足して言った。
源蔵はしばらくその写真に見入っていたが、またチッを連発してこう言った。
「これは、かなめじゃねえ!」
(出たよ)
貴志は脱力しながら思った。
「かなめは、チッ、こんたに髪の毛黒ぐねがったど!」
(あーあ、また始まったよ)
貴志はあきれて源蔵の顔を見た。二所谷は余裕の笑みを浮かべてこう言った。
「はははっ、それはわざと修正してそうしたんですよ。最近の修正技術ってすごいんです。若々しく見せるために、髪の色はもちろん顔のしわだって何だって消せるんです。目をぱっちりさせたり、鼻を高くするなんてことも自由自在なんですよ。ははっ」
源蔵は、二所谷がしゃべっている間、立ったままチッを何回も繰り返していたが、話が終わるとやおら二所谷の隣にあぐらをかいて座った。
「いいが、葬儀屋! チッ、そんたらごどまでして、今更色おなごにする必要あんのが! あん? 見合い写真どはわげが違うんだど! チッ、チッ、チッ」
源蔵は、キーンという耳障りな声を張り上げて二所谷の耳元で怒鳴った。つばが二所谷のほおに飛んだ。二所谷は姿勢を正して源蔵に向き直った。2人が至近距離でにらみ合う格好になった。座敷に緊張が走った。
(もう、頼むからやめてくれよ)
貴志は泣きたくなった。
やがて、源蔵のつり上がった目をきっちりと見詰めて二所谷が口を開いた。
「おっしゃるとおりでございます!」
(えっ?)
貴志と周平は、その意外な言葉に耳を疑った。源蔵も一瞬戸惑った様子だった。
「確かにおたく様のおっしゃるとおりです。本当の所、私も遺影写真を修正することには疑問を持っておりました。白髪には白髪の良さがあります。しわにはしわの良さがあります。そういうものが故人の生きた人生、人となりを物語るんですよね。その通りです。顔は勝手にいじっちゃいけないんですよ。何がコンピューターグラフィクスだってんだ! ちくしょう!」
二所谷は込み上げてくる感情をあらわにしてそう言うと、源蔵の手を固く握りしめた。
「心得違いでした!」
二所谷は、今度はそう言って深々と頭を下げると、なんと涙まで流したのである。
(ちょっと、ちょっと。何なんだよ、これは)
貴志は、まるで下手などさ回りの芝居を見ているようで、拍手を送りたいほどばかばかしくなってきた。
「でも、葬儀屋さん。これはもう出来上がっちゃったんですから、これはもうこれでいいんじゃないで・・・」
「ダメです! すぐに無修正の写真を持ってきます!」
貴志の提案をさえぎって、二所谷は毅然として言った。
「チッ、ああ、そうしろそうしろ!」
「はい、分かりました。では早速」
二所谷は、写真屋に電話をするために外へ出ていった。
(源蔵が来ると、何だかいつも話がこんがらがってくるんだよな。いいじゃないか、別にこの写真で・・・)
貴志はそう思いながら、若作りされたかなめの遺影写真を手に取って眺めているうちに、ふと、幼い時分の記憶がよみがえった。
△このページのトップへ
19『かあちゃんの記憶』
あれはいつだったろう。小学3年生ぐらいだったろうか。
学校の帰り、いたずら仲間のクニちゃんと、火の見やぐらに上って遊んでいると、双六さんの家のユンボと呼ばれていたかあちゃんが白いケツを丸出しにして、畑で立ち小便をしているのが見えたんだっけ。そしたらクニちゃん、口に手を当てて、プッ、プッ、プッ、プッて笑って、それから思いっきり吹き出して、俺もつられて死ぬほど笑って、やぐらから落ちそうになって・・・。
その声が聞こえたのか、ユンボが慌ててモンペ上げながら、どこだどこだってキョロキョロ周りを見回して。あの顔、おかしかったなあ。
「ユンボ、しょんべん漏らしたぞ。ゼッタイ漏らしたぞ」
ってクニちゃんが言って、また死ぬほど笑って・・・。
そうそう、あの畑でこんなこともあったなあ。やっぱりクニちゃんとだった。一緒にスイカを盗んだんだ。いつも学校から帰る時に目を付けてて、大きくなったら絶対食うぞって計画してて、ついにその日が来て、俺たちソッと畑に忍び込んで、クニちゃんが持ってた肥後の守でスイカ切って、死ぬほど食って、スイカの種プッって飛ばして。うまかったなあ。満腹になって、ゲップしながらスイカ畑に寝転んで。空が青くて、雲が白くて・・・。
そうだ。その後、そのことが双六さんにばれて、俺たち呼ばれて、しこたま怒られたっけ。あっ、あん時、そうだ、かあちゃんだ。かあちゃんが謝りにきてくれたんだ。双六さんちに、しこたまカボチャ持ってやってきて、これで許してやってくれって。そうだ、かあちゃんだった。双六んさんちからの帰り道、夕焼けが悲しいくらい赤くて、カラスが鳴いてて、その道でかあちゃん、俺にこう言ったんだっけ。
「いいが貴志、双六はな、おめえらがスイガ盗んだごどを責めでるんではねえ。盗む前になんでひと言声掛げでくんねえのが、水くせえじゃねえがってごしゃいでるんだ。だどもな貴志、それはこの村だがらのごどだど。こごでは、みんな兄弟みてえなもんだがらな。だども、おめえがこの村ば出だらば、こういうごどは通用しねえんだ。誰もおめえをかばったり、助けだりしてくんねえんだど。世の中っつうのはそういうもんだで」
あん時、かあちゃんにそう言われて、俺、何だかわけも分からず泣けてきちゃって、かあちゃんに手をつながれて、俺ベソかいて・・・。
「チッ、おい、貴志! 傘用意したのが!」
「えっ?」
源蔵の声で貴志は我に返った。
△このページのトップへ
20『傘』
「チッ、チッ、傘だでば傘」
「ああ、傘ですか? でも、今日はもう雨降らないんじゃないですか? こんなにいい天気なんですから。夕べの豪雨でさすがの雨も干上がったでしょう」
貴志は玄関から見える、雲一つない青空の広がった景色を見やりながら言った。
「チッ、バガタレ! 降らねえって誰が決めだ? おめえ、いづ天気予報屋になった? あん? いいが、絶対に降らねえど思う、そういう時にこそ用意しておぐのが『備え』っつうもんだべ。備えあれば憂いなしってな。何ぼ言ったら分がるんだ。チッ、チッ、チッ!」
「はあ」
「あのう、俺、村の人回って集めてきますよ。何本ぐらいあればいいですかね」
気を利かせて周平が言った。
「おう、今日は取りあえず30本もあればいいが、チッ、明日は少なくとも70本は要るべよ」
「70本ですか!」
周平はその数に驚いた。全部で68世帯しかない村の家々から1本ずつ借りてきても足りない。
「チッ、とにかぐ、集められるだげ集めでもらいでんだ。おらも今がら村さ帰って集めでみるし、葬儀屋さも頼んでみっから。チッ!」
(源蔵は、なぜそんなに傘にこだわるんだろう。明日の野辺送りの時だったら分からないでもない。でも、今日、仮に万が一雨が降ったとしても一体どの場面で傘が役に立つというんだろう)
貴志は、考えれば考えるほど、源蔵の頭の中が分からなくなった。
「チッ、それがら駐車場はどうした。チッ、ちゃんと頼んだんだべな」
(また、それか)
「ええ、あっ、いや、これからです」
「チッ、何だと!」
「あのう、じゃあ、それも一緒に頼んできます。向かいの貫太郎おじの家がいいと思いますよ。あそこ庭広いから」
周平が言った。
「いやあ、すまない。じゃあ、出棺の前までには戻ってきてくれるかな」
貴志は周平に向かって手を合わせた。
「チッ、大難儀掛げます。チッ」
源蔵もそう言って頭を下げた。貴志は驚いて源蔵の顔を凝視した。源蔵のこういう態度を見るのは初めてだった。
「じゃあ、俺、行ってきます」
周平は勝手口に行こうと廊下に出た。ちょうど時、粉まみれになった斎田道秋たちが居間のほうから出てきた。
「おはようございます」
周平が言った。道秋は周平の顔を見たが、いつものように「やあ、やあ、やあ」とは言わなかった。それどころか周平を完全に無視した。道秋は、周平を恐い顔でにらみ付け、あいさつもせずに通り過ぎたのである。照子も全く同じ行動をとった。
(感じわるー)
周平は、これがもしかしたら、昨日彩が言ってた「やなおじさんたち」だなと思った。周平は出がけにキッチンのほうをのぞいた。
(あれっ?)
朝の様子とは打って変わって、みんなの士気が完全に落ちている。よく見ると、作業場の新聞紙の周辺にまで粉が散乱し、スミとのり子は投げやりな動作でそれをすくい集めていた。
△このページのトップへ
21『団子再開』
「スミばあ、どうした?」
周平が話し掛けると、スミはゆっくり振り返って、
「このざまよ。今、粉付けたじじいどばばあ、そっちさ行ったべ。あいづらのせいでこうなったんだ」
と言って動かしていた手を止めた。それからのり子に向かって、
「あどいいわ。粉集めねくても」
と言った。
「あいづらの体さ付いだ粉で団子こしらえるわげにないがねえ。せっかくの団子がけがれっちまう!」
スミは吐き捨てるようにそう言って、よっこらしょと立ち上がると、いきなり新聞紙を丸め始めた。
「あいい、いだましごどや」
のり子はそう言ったが、スミの勢いに気圧されて立ち上がらざるを得なかった。
「彩、ごみ袋あっか?」
彩は、慌てて大きいゴミ袋をスミに渡した。団子の粉は新聞紙ごとゴミ袋の中に収まった。
「よっし、もう一回1がらやり直しだ。のり子、まだ新聞敷いでけろ!」
スミはのり子に指示を与えてから、周平に向き直って言った。
「なあ、周平、そういうわげで、明日の粉ねぐなったんだ。今日中でいいがら、もう一回行ってきてもらいでえんだが頼まれでくれるが? 餅米もうるちも、おらの家さ行けばあるがらよ。台所の下の瓶さ入ってる。おっきい瓶がうるちでちっこい瓶が餅米だ。今度は5合ずづでいい」
「ああ、いいよ。だども、スミばあの家さ勝手に上がっていいのが?」
「何言ってるんだ。同じ別家仲間だべよ。それにな、おめえは息子みてえなもんだで」
「ああ、分がったよ。5合ずづだな」
「ああ、頼む。それがら200円持ってるが? ねがったらおらの財布がら持っていげ。テレビの上さあっから」
「大丈夫だ、あるある」
周平が笑った。
「あどで必ず貴志がらもらうんだど。いいな」
「分がったでば」
周平は彩にも笑顔を送った。彩もそれに答えて笑顔で手を振った。
「じゃあ、団子頑張ってな」
周平がそう言って出ていこうとした時、のり子がいつもののんびりした口調で言った。
「いねえどぎは、直接作業場さ回りな」
「おう、じゃあな」
いろいろな用件を担ってにわかに忙しくなった周平は、後ろ手を振って慌ただしく飛び出していった。同じくにわかに忙しくなった団子班も、スミを中心にまなじりを決して団子作りを再開した。新聞紙がまた通路びっしりに敷かれ、あらためて粉の調合が始まった。彩はぬるくなったお湯を沸かし直すために、クッキングヒーターのスイッチパネルを押した。
「おい、それにしても、マチ遅ぐねえが?」
新聞紙を広げながらのり子が言った。そう言えば、マチはボールを取りに行ったきりまだ戻っていなかった。
「だーがら言わんこっちゃねえ。やーっぱりマチだなや」
スミがあきれたようにそう言い、彩が窓の外に目をやったその時だった。庭の芝生を踏んで歩いてくる人影があった。その人影は、日よけのためなのか頭に大きな白いものをかざして、後光を浴びながらのんびりゆっくり歩いてくる。彩は、その何とも言えない崇高な姿に、俗世間の人間を超越した何か不思議な力を感じて、
「あっ・・・」
と言ったまま、しばし絶句した。
(托鉢の僧のようだ!)
彩が見とれている中、その影は左右に傾きながら、ゆっくりと、だが確実に大きくなってくるのだった。
△このページのトップへ
22『大逆罪』
「貴志君、貴志君、貴志君。ちょっと、君。あのねえ、これ見てもらえますか? ほらっ、照子もこの通りだ。ねえ、この通りですよ。この通りってことは、分かるかなあ。分かるよねえ。見れば一目瞭然だ。ねえ、本当にこの通り粉まみれなんですよ、私たち。見てよ、ほら、粉ふいちゃって。頭も、顔も、全部、ぜーんぶですよ。ほら、服だってこの通りだ。白い喪服って聞いたことありますか? 私は一度もないね。あったら見てみたいわ。ねえ、葬儀屋さん。ねえ、照子」
道秋は、そう一気にしゃべって二所谷と照子の顔を見た。それから貴志の正面に座って、『妖怪粉ふきジジイ』のような白い顔でまたしゃべり出した。
「あのねえ、貴志君。聞いてくれますか。今ね、大変なことがあったんですよ。大変なんてもんじゃない。これは事件ですよ、事件。はっきり言ってこれは傷害罪ですよ。いや侮辱罪かもしれない。いやいや、名誉毀損と不遜罪だな。いやいやいや、そんな甘っちょろいもんじゃないわ。これはあれですよ。何だ、ええと、そう大逆罪だ。断じて大逆罪です。あの天皇陛下を貶めようとして幸徳秋水たちが死刑になった、あれだ、大逆事件。あれにとってもよく似てる。やつらも死刑です。やつらっていうのはね、あのババアだ。そう、あの凶悪犯人、凶悪ババア。とにかく本当にとんでもないババアだ。誰だ、あいつを連れてきたのは。こんなに粉かぶっちゃって、粉ふいちゃって。もうどうすればいいのか、ねえ照子。これから火葬だっていうのに。あと、今日は5時からお逮夜もあるんだ、お逮夜。それなのに、こんなに粉かぶっちゃって。こういうふうに粉ふいちゃって・・・」
貴志はあっけにとられながら、さっぱり要領を得ないこの男の話を聞いていた。
「向こうでちょっとしたアクシデントがありましてね」
照子が冷静を装って言った。
「原因は、まあ主人が怒るのも無理ないと思いますのよ。確かにどう考えても明らかに向こうさんが悪いんですもの。でも、それはこの際、こういう場でもあることですし、穏便にしてもいいと思います。私たちは大人ですもの。ちゃんと知性も理性も十人並みに持っておりますから」
道秋は白い顔を照子に向けて、何度も大きくうなずいている。
「ただ、これだけは言っておかなければなりません」
「そうそうそう、照子。言ってやって、言ってやって。うん、うん、うん」
道秋が相づちを打った。
「粉のことなんですの。私たちが粉代を弁償しますって言いますのにね。もちろんこちらは全然悪くはないんですのよ。むしろ犠牲者なんですから。悪くはないんですけれども、お金を払うと言ったのにですよ。お金は要らない、とっとと粉買ってこいって、もうけんもほろろに言われたんですのよね」
「そうそうそう。けんもほろろだな、あの言い方は。盗人猛々しいってんだ。ひどい、ほんとに失礼千万だったねえ、照子」
「ああ、はあ」
大逆罪かどうかは別として、斎田たちの怒っている理由が少しだけ分かってきた貴志は、困惑顔でそうつぶやいた。
「ですから、これはもう話になりませんのでね。貴志さんに説得していただきたいと思いましてね。だって、私たちは粉のことなんて皆目承知しておりませんしね。そもそもそういう理由も義務も責任もないわけですからね」
照子はそう言って、パタパタとハンカチで顔の粉をはたいた。加勢を得た道秋は、そうだ、そうだと大きくうなずいて貴志の顔を見ている。数秒の沈黙があった後、今まで沈黙を守っていた源蔵がついに口を開いた。
「チッ、つべこべ言わずに、とっとと買ってこいや!」
その声は、普段よりもさらに1オクターブも高い、ハイCのテノールボイスだった。照子も道秋も驚いて声の主を振り返った。また数秒の沈黙があった。
「さっきの白い喪服のことですが・・・」
(えっ?)
意外な所で口を挟んだ者がいた。全員の視線が、今度はその男の口に注がれた。
△このページのトップへ
23『喪の色』
「日本の伝統的な喪の色は本来白なんです。黒い喪服になったのは明治に入ってからなんです。『ざん切り頭を叩いてみれば文明開化の音がする』ってあの頃。何でもかんでも欧米化の時代、あそこが始まりなんですよ。繊維業界がそれに飛びつきましてね。それで礼服は黒ってことになっていくんですね。バレンタインデーチョコレートもそうです。本来、日本人は、まっ白い大福が好みだったはずなんです。あちらはチョコレート業界が仕組んだんですね。仕掛けたと言いますか。オセロゲームみたいに、勝手に白を黒に変えてしまったんです。いやだ、いやだ、黒はいやだなあ。ですから白い喪服というのは、ありなんです。ありどころか、日本文化の正統派なんですよ。現に今でも白い喪服を着ている地域があるくらいなんだから。いいですねえ。私は断固白い喪服を支持する、白い大福を支持する、そっち派です。さっきの質問にお答えすると、まあそういうことになります」
全員がポカンと口を開けて聞いている中、二所谷は我水を得たりとばかりにしゃべり終えた。
(だから、だから、だから・・・)
貴志は心の中で頭を抱えた。
△このページのトップへ
24『つぶれ大福』
「こいづ穴開いでるがらな」
ようやく持ち場に戻ったマチが、愛用の使い古した白いホーローのボールを前にして言った。
(はあ?)
スミとのり子は手を止めてマチの顔を見た。
「穴開いでるがら気付けれって」
マチは確信を込めてそう言った。
(どういうこと?)
せっかく取りに行ったボールに穴が開いているという。マチはそれを分かってて持ってきたのだ。彩は、自分の理解を超えたものを見ているようで、何とも表現のしようのない不思議な気持ちになった。
「穴開いでるがら使えねえんだが、おら、何だがこれ使い慣れでるもんだがら」
マチは涼しげに言って笑った。
ボールを顔にかざして、穴を確かめていたのり子が言った。
「あいい、ほんとだ。穴いっぺえ開いでるなあ」
スミはゴホンと咳払いをして、
「まあ、いいべ」
と言ったが顔は厳しかった。
こんなふうにして、立ち上がりにいろいろ紆余曲折がありながらも、それでもどうにか粉は練り上げられていった。マチの穴の開いた白いボールの中には、白いもちもちした団子の原型が姿を現した。こうなればもう、穴が開いていようがいまいが関係なくなった。
(何とかなりそうね)
彩は、やっと先行きに希望がわいてきていた。
「今日の団子、何ぼ作ればいいんだ?」
のり子が言った。
「なんぼって、16・・・。あいい、なんぼだ? スミ」
マチが聞いた。
「十六団子は明日だべ。今日の団子はログゴさ積み上げる団子だべ」
スミが答えをぼやかして言った。ログゴとは、長い1本足の付いた木製のおぼんのことである。
「だがらなんぼだ?」
のり子がスミに切り込んだ。
「なんぼって、なんぼだっけ?」
(ちょっとー、いつもやってたんじゃないんですかあ?)
「とにかぐ、まずやってみでがらだ!」
スミがいつもの逃げ口上を口にした。
(また、そうきたか)
次の行程は、もちっと練られた団子の原型を、大福餅をつぶしたような形に小分けしていく作業だった。
(ああ、なるほど。これを丸めて団子にするのね)
彩が感心して見ている中、3人の手で着々と『つぶれ大福』が製造されていった。大福の大きさは個人差があり、のり子のは大きくスミのは小さかった。マチは丁寧で形はきれいだったが作業が非常にのろかった。
△このページのトップへ
25『プカッ!』
「そろそろ、彩、鍋さ湯っこ沸騰させでおげ!」
手を動かしながらスミが指示した。
「はい!」
彩が一旦止めていたコンロをつけた。しばらくして、鍋に水泡が立ったところで彩はスミに向かって、
「お湯、沸きました!」
と叫んだ。スミは、
「よっし!」
と言って、自分の着ているかっぽう着の裾をヒョイとつまんで袋を作り、その中に大小のつぶれ大福を入れて立ち上がった。スミは、そのまま腰の曲がったカンガルーのような格好で彩の元に来ると、
「その湯っこさ、これ入れろ!」
と言って、キッチンの上にかっぽう着の中身をぶちまけようとした。
バラバラバラバラバラッ!
「あっ!」
彩が手伝おうと思った時には時すでに遅く、つぶれ大福は床に落下して「つぶれつぶれ大福」になってしまっていた。
「どうします?」
大福を拾いながら彩が聞いた。
「煮れば何ともねえ」
ある程度予想していた答えだった。
鍋が小さいため1回では全部入り切らず、何度かに分けて彩はそれを煮ることになった。
「いいが、プカッって浮いできたら、中まで煮えだってごどだがらな。そしたら上げるんだ」
「はい、プカッですね」
スミは彩の腰元で指導に当たっている。悲しいかな、スミの目にはプカッと浮かんでくる様子が確認できない。
「まだだが?」
「ええ、まだちょっと」
菜ばしで大福をツンツンとつつきながら彩が言った。
「いいが、プカッだど」
「はい、プカッですね」
大福はなかなか浮かんできてくれない。
「まだだが?」
「ええ、まだかと・・・」
「火力、弱ぐねえが?」
「これが最大ですけどね」
彩の視点から見ると、左目の下方に鍋に入った大福があり、右目のそれより下方にスミの顔があるといった二重アングルだった。右目のスミの顔が少し困惑顔になった、ちょうどその時、待望の左目の大福が1つプカッと浮き上がった。
「浮きました、浮きました。プカッと浮きました!」
彩は感激して叫んだ。右目のスミは、ホッとしたようにうなずいた。
「あっ、また浮きました! プカッ、あっ、プカッ。もう一つ浮いております!」
彩はあたかも実況中継のアナウンサーように、左目に起こったニュースを、興奮をもって右目の視聴者に伝えていた。
「おい!」
右目の視聴者が言った。彩はハタと我に返った。
「浮がんだら、こっちのボールさ移せ!」
「は、はい!」
スミはマチから白いボールを受け取って彩に渡した。
「これにボンボン入れていくんですか?」
「んだ」
彩は、茹で上がった大福をその中に1つずつ投入し始めた。
「でも、くっ付いちゃいますよ」
「いいがら、ちゃっちゃどやれ!」
彩は言われる通り、大小さまざまな形の『茹でつぶれ大福』をボールに移していった。下のほうは完全に合体し始めている。
(これじゃあ、せっかく分けた意味がないんじゃないの?)
彩は、また新たな疑問を持った。ようやく最後のプカッをボールに移し終えた彩は、それをスミに渡そうとも思ったが、また良からぬことになってはまずいと思い、自分で作業場に持っていくことを提案した。
「これ、あっちに持っていくんですよね。私持っていきますから」
そう言って、ホーローの白いボールを持ち上げようとした彩が思わず叫んだ。
「アチッ、アチッ、アッチーッ!」
スミは落ち着き払って、
「早ぐ、水道で冷やせ!」
と言って、自分は濡れたふきんでボールをつかみ、ザリガニのように頭の上に掲げると、さっさと作業場へ持っていってしまった。
△このページのトップへ
26『アッチ、アッチ、アッチ!』
作業場にいたマチとのり子は笑いながら、
「彩ちゃん、大丈夫だが?」
「あいい、よぐ冷やせ、冷やせ」
と声を掛けた。
「すみません、うかつでした。でも、大丈夫です」
手を水で冷やしながら、彩は笑顔でみんなに謝った。
「さ、熱いうぢだど!」
作業場に戻ったスミは、にわかに気合いを入れた。そして、湯気の上がったボールの中に手を入れて、茹で上がったばかりの大福をこね出したのである。
(えええっ?)
次に、マチの手もそれに加わった。
「あじー、あじー、あじー!」
マチが言った。
のり子も、こねるリズムに合わせながら、
「アッチ、アッチ、アッチ」を繰り返した。
彩は、一体この人たちの手はどういう構造をしているんだろうと思った。マチやのり子には熱いというセンサーはあるようだ。しかし、スミは熱いとも言わず黙々とこねている。どうなっているんだ。いや、その前に、そもそもこの作業の意味は何なのだ?
「彩ちゃん!」
マチが言った。
「はい!」
「悪いが、水、持ってきてくんねえかい。手冷やす水っこ」
「はい!」
彩が小さなボールに水を入れて持っていくと、3人とも手が真っ赤になっていた。ボールにまっ先に手を入れたのはマチではなくスミだった。
(プッ! ほんとは熱いの我慢してたんだあ・・・こいつう)
彩は、人差し指でスミをツンツンしたい衝動に駆られた。
△このページのトップへ
27『ジャムの容態』
「極度の脱水状態ですね。注射を打っておきましたが、うーん、正直厳しいです」
『なかよし動物クリニック』の石塚獣医師は、美樹を前にしてそう告げた。
「助からないってことですか?」
落胆した声で美樹は石塚に聞いた。それから、診療台に横たわったジャムを見て顔をしかめた。
「うーん、この年齢になると、もう基礎体力がないんでね」
石塚は、そう言って白衣の胸ポケットから3色ペンを取り出し、カルテに何か短い文字を書いた。
「あのう・・・」
美樹は、憔悴し切った顔を石塚に向けて言った。
「何でしょう」
「もし、そうなった場合、こちらでは、そのう・・・」
「ペットの葬儀ですか?」
「え、ええ、火葬とか納骨とか・・・」
「うちでやるわけじゃありませんがね。そういう業者さんがありまして。あっ、確か案内の冊子か何かあったはずだな」
石塚はそう言って立ち上がると、受付の脇のブックスタンドからパンフレットを1部持ってきた。
「いやあ、聞いた話ですが、本当に立派な葬儀らしいですよ。火葬や納骨はもちろんですが、お経まで上げるんですって。あと、お墓とか仏壇とか何でもあるそうです。とにかく、人間顔負けのサービスだって言ってました」
美樹の前に置かれたパンフレットの表紙には、『ありがとう! 私のペットちゃん。安らかな成仏をお約束します。ジャパンペット成仏堂』と書かれていた。
「先生、もしジャムがそうなっても、キチンと供養すれば、ジャムは、ジャムは苦しまないで、あの世へ、あの世・・・」
美樹は両手で顔を押さえた。
「とにかく、今日はこのままここで様子を見ましょう。何かあったらご連絡いたします」
「はい、どうか、お願いします。あっ、連絡先ですが、今日明日は主人の実家におりますので、そちらに」
美樹は、そう言ってハンドバッグから手帳を取り出し、番号を書いて渡した。
「分かりました」
「どうか先生、よろしく・・・」
美樹はハンカチで涙を拭いながら立ち上がった。そして、ジャムのそばに行って優しく体をなでた。
(ジャム、もしそうなっても、あなたには最高の供養をしてあげるから。私を許してちょうだい)
△このページのトップへ
28『照子VS源蔵』
「チッ! いいがら黙って粉買ってこいってんだ!」
源蔵が道秋たちに怒鳴った。しばらく、あっけにとられていた道秋たちだったが照子が反論した。
「ちょっと、あなた。あなた黙って!」
「チッ、黙れだど!」
「あなたの指図は受けません!」
「チッ、何だど!」
「貴志さん、あなた、あなたに聞いているんです!」
照子は、源蔵の高音に負けないトーンで貴志をにらみ付けながら言った。
「いやあ・・・」
貴志は困った顔で頭をかいている。
「チッ、つべこべ言わず行ってこいってんだ!」
源蔵の声が金切り声になった。
「うるさい! あんたの指図は受けない!」
照子の声がひっくり返った。
「さあ、貴志さん。喪主!」
『貴志さん』のところで1回、『喪主!』と叫んだところで1回、つごう2回も照子は激しく声がひっくり返った。
「ええ・・・そのう・・・どうしますかねえ、粉がないとねえ・・・」
「チッ、チッ、チッ、チッ、おめえら、行ってこい、バガ野郎!」
「うるさーい! てめえの指図は受けなーい!」
『あなた』が『あんた』になり、ついに『てめえ』になった。照子の言葉から理性のメッキが完全にはがれてきた。化けの皮と言ってもいいだろう。2人はものすごいにらみ合いになった。
道秋は照子の言動にただオロオロしながら、金魚のように口をパクパク動かして、声にならない言葉を発しているだけだ。貴志は、神経を逆なでする周波数8000ヘルツ級の高音攻めにあって、またズッキンズッキンと忘れていた頭痛が再発していた。
「私知ってますよ」
(えっ?)
全員が、一瞬静まり返って声の主を見た。
「粉をひく場所なら私知ってますよ。木之倉与左衛門商店っていうんです。ご存じですか? あそこの先代が亡くなられた時うちが葬儀をやったんですね。いやあ、立派な葬儀でした。何でも最近は梅なんかも売ってるそうですな」
あの人だった。
(あー、だから、いいんだよ、お前は引っ込んでろよ。それに、くどいようだけど、あれは梅干し用の小梅を買ってるが正しいんだよ)
貴志は、こんな時に周平さえいてくれたらどんなに助かったか分からないと思った。その周平は今、源蔵に指示されたよく理由の分からない傘集めのために村中を駆け回っているはずだった。
△このページのトップへ
29『へら』
真っ赤に腫れた6本の手によってとことん練り上げられ、もう一度大きな塊となった団子の原型は、湯気を上げながら白いボールの中に収まっている。それはまるで、きねでつき上げたお正月の鏡餅のような美しさだった。
粉を2種類混ぜ合わせて、まとめてポンポン茹でるだけだと思っていた彩は、決して合理的とは思えないが、なるほどこれが供養なんだなと素直に感心した。
(一時はどうなることかと思ったけど、これを丸めればようやく完成ね)
彩がそう思ってホッと一息ついた時だった。
「へらねえが、へらねえが?」
スミが彩を見て言った。
(へら?)
それは、全く予期していなかったオーダーだった。
「はい、ええと・・・」
「へらだ、へら、へら」
スミが急かす。
「あっ、はい!」
彩は引き出しをいろいろ開けて探してみたが、『へら』はなかなか見つからなかった。
「へらねえが、へら!」
スミがまた言った。
「はーい、ちょっと待ってくださーい!」
(へら、へら、へら、へらっと)
あらゆる引き出しという引き出しを探したが、『へら』はどこにも見当たらない。
「彩ちゃん、まんまのへらでもいいんだど」
マチが言った。
(まんまのへら? ああ、炊飯ジャーのね。そっかそっか)
彩は、炊飯ジャーの脇に『へら』がくっ付いていてくれることにいちるの望みをかけたが、それもかなわなかった。
「ありません」
「なんだべ、へらもねえのが、こごの家は」
スミが言った。
「あいい、おら、家さ行って取ってくるわ」
マチが言った。
(うそっ! やめて、やめて!)
彩が心配するまでもなくスミはきっぱりと、
「やめろ、日暮れる!」
と言った。
のり子は不思議そうな顔で、
「この家、まんま何で盛るんだ?」
と言った。
「へっ、大方スプーンででも盛るんだべよ。賢しい人だぢのごどだで」
スミが嫌みを込めて言った。
「スプンって、しゃじのごどだが?」
どうしても合点がいかないのり子は、スプーンでご飯を盛る仕草をしながらブツブツ言っている。
「しゃじで盛ったらなんぼ時間かがるべなあ。こうやって、こうだべ。ふとーっつ、ふたーっつ、みいーっつ、よーっつ・・・」
彩は、ひょっとしてと思って炊飯ジャーのふたを開けてみた。
(あった!)
それは、美樹が一膳飯を炊いた時のごはん粒が付いたままの、まさしく『まんまのへら』だった。
「あったあ! へらありましたあ!」
実況アナウンサーの声で彩が叫んだ。
「20回だばかがるな」
のり子が言った。
△このページのトップへ
30『青っつらジジイ、赤っつらババア』
「あのう、斎田さん。すみません、誰か代わりに行ってあげられれば、あのう、いいのかもしれませんけど、人出がないもんですから。あのう、できれば・・・」
貴志が言った。彼としてはかなりの勇気を振り絞って言ったつもりだった。しかし、極度の興奮状態にあった照子は、即座にその言葉をぶった切った。
「うるさい! 喪主! 黙れ!」
「チッ、何だと、このババア!」
(ああ・・・)
源蔵と照子の狂気じみた応酬がまた始まってしまった。貴志は頭を抱えた。
「ババアだと! この青っつらジジイ!」
「チッ、チッ、チッ、青っつらだど! この赤っつらババア!」
「るっ、さいわね! このチッチチッチチッチチッチ野郎、こんちくしょー!」
「何だど! チッ、チッ、チッ、チッ、このカッカカッカババア!」
「るっさい、るっさい、るっさーい! このチッチチッチジッジッジイ!」
このままではつかみ合いの喧嘩になると思われたその時、今まで金魚の口でパクパクやっていた道秋が、ついにたまりかねて立ち上がった。
「はーい、ここまで。ここまででーす」
それから道秋は、照子の元に行ってそっと彼女の肩に手を置いた。
「照子、照子。分かった、分かった。お前の気持ちはよーく分かったから。ねえ、お前は血圧も高いほうだから。ねえ、少し落ち着いて。そうだ、こうしよう。この場合、そうね、話し合いに、話し合いっていうか、話し合いも何もね、これじゃあもうお話にならない、ならないっていうか決裂ですよ、決裂。拉致問題と一緒でね。何言ったって先方さんはね、民主国家じゃないんだから。これじゃあね、こっちはお手上げですわ、お手上げ。バンザーイだ、ねえ。拉致問題の被害者とおんなじですよ、これは。私は横田滋さんだ。お前は、あれだ、誰だっけ? ええと、そうそう早紀江さんだ、早紀江さん。そうでしょ。かわいそうだねえ、まったく。拉致被害者は本当にかわいそうなんだ。いいですよ、いいですよ。分かりました、分かりました。そっちがそうなら、こっちにだって考えがある。考えっていうのはねえ、作戦だ、作戦。ねえ、戦い方があるってことだ。あなた方のような非合法な皆さんとはねえ、戦い方があるんだ。戦うったてねえ、何もテポドン打つわけじゃありませんよ。非暴力で戦うんだ、非暴力で。あくまでもね、紳士的にね、紳士的にやりますよ。こうなったらね。いいでしょういいでしょう。行ってこようじゃありませんか。粉だか何だか知りませんけどね。そんなもの、拉致問題に比べたら簡単なことだ。あちらは、本当にかわいそうなんだから・・・」
「チッ、いいがら、さっさと行ってこいってんだ!」
源蔵が言った。
「さあさあ、早紀江。行きましょう、行きましょう。行って2人でめぐみちゃんをね。この場合は粉ですけどね。粉ちゃんでも何でも探してこようじゃないですか。たやすいことです、そんなもの。あちらさんは大変なんだ、本当に。ねえ、早紀江」
照子はキッと源蔵をにらんだまま、道秋に手を引かれながら渋々家を出ていった。
「今の方たち、分かったかなあ」
二所谷だった。
「えっ?」
「木之倉与左衛門商店の場所ですよ」
のんきな声だった。
源蔵は、
「チッ、塩まいでおげ!」
と言って、道秋たちの後姿をにらみ付けると、貴志に向き直って、
「チッ、貴志、おめえ、もっとビシッと言わねばダメでねえが!」
と言った。
(そう言われても・・・)
貴志は、頭が割れんばかりに脈打っていた。
「チッ、とんでもねえバガどもだ」
源蔵はそう言って時計を見た。
「葬儀屋、チッ、おだぐの会社に傘ねえが?」
「傘ですか? ありますよ。葬儀社の名前の入った傘でよろしければ」
「ああ、すまねえが、チッ、あるだげ持ってきてくれるが」
「了解です。さすが用意がよろしいですね。私も何本かお持ちしようと思っていた所です。じゃあ、写真屋に行く前に寄ってみます」
(何だかこの2人、妙にウマが合ってないか?)
貴志は思った。
「ああ、すまねえ。チッ、あいづらのせいで余計な時間を食っちまった」
源蔵はそう言ってバタバタと出ていった。二所谷も、まるで子分のように腰をかがめてその後を追った。
△このページのトップへ
31『斉田夫婦の受難』
斎田夫婦は、まず米屋を探しに高合町に行った。米屋は割とすぐに見つかった。
「いらっしゃいませ!」
今村米穀店の若い女性の店員は、殺気じみた形相で入ってきた老夫婦を訝しく思いながら声を掛けた。
「お米下さいな」
憮然とした表情で照子が言った。
「はい、どのような・・・」
「別に何でもいいです」
「何でも・・・と言われましても・・・」
店頭には、産地ごとのブランド米や、有機米、無農薬米、無洗米、カルガモ栽培米、みみず栽培米など、たくさんの種類の米が並んでいた。
「一番安い、安いっていうか、あれだな。並っていうか、そうそうポピューラなやつで、ねえ、この場合いいんじゃないの。ねえ、照子」
道秋が言った。
「ええ、はい。一番安いって言いますとこちらの『がっぷりよつ』ですけど、30キロ7800円になりますね。一番安いのは、これになり・・・」
「ちょっと君、安い、安いってねえ、そうじゃないでしょ。一番ポピューラって言わなきゃ。ねえ、照子。そう。じゃあ、その一番ポピューラなやつでお願い・・・」
「その『どん百姓』っていうのはお幾らかしら?」
道秋の話の腰を折って照子が言った。
「えっ?」
店員が首を傾げた。
「その『完全有機無農薬タニシ土壌作り天日干し米』のことです」
「はあ、それは『どん百姓』ではなくて『ジュン百姓』と読むんですけど・・・」
店員が恐る恐る言った。
「君ねえ、『ジュン』と読もうが、『ドン』と読もうがねえ、この際どっちでもいいじゃないですか。そりゃあ、君はね、その字をジュンスイの『ジュン』と主張するかもしれないよ。ジュンケツとかねえ。まあそれもありますわな。確かにそれも間違いではない。間違いとは言いませんよ、ねえ。そうも読むんだから。でもだねえ、この字はねえ、ドンカンの『ドン』とも読むんだ。そうでしょう? どうだ、まいったか。ハハッ、1本取ったねえ。それからグドンの『ドン』ってのもそうだねえ。どうだ。これで2本取ったねえ。そうでしょう、ねえ。さあどうだ、何か言ってみろ!」
道秋が、照子の気持ちを代弁して言った。
しかし、残念なことにその主張は間違っていた。純粋の『純』は愚鈍の『鈍』ではなかった。2本取ったつもりが、道秋はかえって自分の漢字力のなさを暴露する結果となった。
「確かに似てますけど字がビミョウに・・・」
店員は控えめに食い下がった。
「何よ!」
「それに音の響きっていいますか、高級感が全然違うかと・・・」
「るっさいわね! 一体幾らなの! そのジュンは!」
「あっ、はい。そちらは『がっぷりよつ』の3倍、30キロ2万5800円で・・・」
「それにしてくださいな!」
きっぱりと照子が言った。店に置いてあるお米の中で一番高級な米の注文に店員は少し慌てた様子だった。その慌てぶりに照子は自尊心を満たしていた。
「あ、はい、30キロで?」
「そうです!」
そのやり取りをポカンと口を開けて聞いていた道秋が口を挟んだ。
「おいおい、照子。何もそんな高級、高級っていうか、アンポピューラな米じゃなくても、ねえ。それに、せいぜい1升もあれば、ねえ。そう言ってなかったっけ? いや、半升でいいって、確かあのババア・・・」
「いいんです! それから餅米も一番いいやつにしてくださいな」
「餅米もですか?」
「ええ、これ以上ないってやつで」
道秋は目を丸くして絶句している。
「あ、はい。では、この『純百姓の杵付きふっくらモチモチ』でいかがでしょう。これも30キロでしょうか?」
「もちろん!」
「おいおい、照子。ちょっと、ちょっと。ねえ、お姉さん。相撲部屋の餅つき大会じゃあないんだからさあ。ねえ、そうでしょ。たかが団子のコネコネに。ねえ、お姉さん」
道秋は店員にこわばった笑顔を向けて、団子コネコネをやってみせている。
「全部でお幾らかしら?」
「えーと、合わせますと5万3600円。それと消費税ですが・・・」
「結構です、それ包んでくださいな。それから、おたくでは粉にしていただけるのかしら?」
「すみません。うちは精米はしますが粉に挽くのはやっておりません。木之倉与左衛門商店さんなら挽いてくれると思いますが・・・」
恐縮しながら店員が言った。
「あれですか? 粉にするには一度精米するんでしょうか?」
「はい、普通はそうかと・・・」
「じゃあ、精米もお願いします。お幾らかしら?」
「はい、500円ずつになります」
「結構です!」
精米をしている間、照子は道秋に何も言葉を発しなかった。道秋は、
「なんて言うかなあ。団子コネコネにねえ。うーん、そうねえ。何だねえ。まあ、あれかな。これかな。そうだそうだ。これもねえ。うーん、そうねえ。まっ、いいかねえ」
などと1人でブツブツ言っていた。
「お待たせしました!」
奥にいた若い男の店員が、ずっしりと重い袋を持って出てきた。
「おクルマまでお運びしますが・・・」
男の店員は言った。
「そうね、お願いしますわ。その前に包んでいただける?」
男の店員はキョトンとして女の店員を振り返った。
「あのう、包むと言われましても・・・おのしをお掛けするぐらいでしたら・・・」
女の店員は困惑しながら答えた。
「結構です。おのしを掛けてくださいな!」
「お祝いとか、そういう・・・」
のし書のことを聞かれた照子は一瞬ためらった。
(まさか『お祝い』であるはずはない。ものが餅米だからといって『お年始』というのも変だ。はて?)
その時、道秋が自分の出番とばかりにしゃしゃり出た。
「そうね、この場合は、あれでしょう、照子。『ご仏前』でしょ。ねえ、ご仏前。これは、ほら、粉になって、それからグチョグチョやって団子になっていくわけだから。その団子はねえ。故人、この場合かなめさんだ。かなめさんの元に届けられる、とまあそういう流れに、流れっていうか行程にねえ、なってるわけだから。あっ、お姉さん。すみません『ご仏前斎田道秋』でお願いします。ねえ、照子」
「ご仏前・・・ですか?」
店員は、米袋にのしを掛ける客も初めてだったが、『ご仏前』という予想もしなかったのし書きにはもっと驚いた。
のしの掛かった米袋を2つクルマのトランクに積み終えた男の店員に向かって道秋が聞いた。
「君ねえ、何でしたっけ? 粉にするところ、キムラヨタロウ商店だっけ? そこの場所教えてくれますか?」
「ああ、木之倉与左衛門商店でしたら、この道をまっすぐ行って、次の信号を右に曲がってください。長裾町の入り口です。すぐに分かると思います」
男の店員は2人を見送って店に戻ると、女の店員に向かって、
(何だあいつら?)
という顔をした。女の店員は首を傾げて両手を広げ理解不能のポーズをとった。
木之倉与左衛門商店はすぐに見つかった。大きな屋敷だった。長い木塀には大正御領旗が何本も並べられていた。道秋は入り口と思われる所にクルマを止めた。のり子が言ったとおり、小さな字で、確かに『小梅買います』と書かれた看板があった。
「照子、ここのようだね。いやあ、立派な屋敷だ」
長い塀を仰ぎ見ながら道秋が言った。
「じゃあ、ちょっと行って、ねえ、お店の人に頼んでくるからね。おっ、かなりあるねえ、これ。ねえ、30キロ2つか。結構な量だなこりゃ。うん。これ全部、粉にするってことで、ねえ、よろしいんだよね。あれっ? あっ、どうだっけな? 全部だったっけな? あっ、いいんだ、いいんだ。確か全部だ、全部。あっ、あれっ? そうだっけな? ありゃ? 違ったかな。あれえ・・・」
「全部です!」
念のためと思って聞いた道秋だったが、案の定想像したとおりの返事だった。道秋はエンジンを切ると、木戸を開けて中に入っていった。
「米屋さーん!」
道秋は大きな声で叫んだ。何も反応がなかった。
(あっ、そうか。ここは米屋ではなかったな)
そう思った道秋は、今度はこう叫んだ。
「粉挽き屋さーん!」
やはり反応がない。道秋は屋敷の中に侵入していくと、玄関の戸を開けてまた叫んだ。
「すいませーん、粉挽いてもらえますかー!」
全く返事がない。道秋は30分以上もかけて広い屋敷の隅々の戸という戸を全部開けて叫んでみたが、誰も出てくる様子がなかった。道秋は途方に暮れた。
△このページのトップへ
32『しわ顔』
ちょうど同じ時間、周平は木之倉与左衛門商店の作業場にいた。
「うんまそうな漬け物だなあ、おばあちゃん」
米を粉に挽いてもらいながら、周平は作業をしているおばあちゃんに声を掛けた。おばあちゃんは、顔中の深く刻まれたしわの1本1本に残らず汗をためていた。
「ああ、うめえよ、うちの漬けもんは。ほれ、これ、漬かったどご、食べでみれ!」
おばあちゃんはうれしそうに笑ってキュウリ漬けを1本丸ごと周平に渡した。笑った拍子に、おばあちゃんの顔の無数のしわから、たまっていた汗が搾り出されてあごに伝った。
パリッ、パリッ・・・。
「うっ、うんめえ! うめえな、おばあちゃん」
周平は感嘆の声を上げた。
「はっはっはっはっ・・・うめえが?」
「うん、うめえ、うめえ、こんなうめえ漬け物食ったごどねえ」
おばあちゃんは満面の笑みを浮かべて、まるで自分の孫を見るような目で周平を見ると、
「ほれ、少しもっていげ」
と言って、キュウリやナスの漬け物を10本ぐらいずつビニール袋に入れてくれた。
「えっ! おばあちゃん、これ売り物でねえのが?」
おばあちゃんは作業場の奥を見やってから、シーッと口に人差し指を当てた。その顔が周平にはたまらなくかわいらしく思えた。
粉を挽き終え2つの袋をぶら下げて戻ってきた、これまたいいしわ顔のおじいちゃんが言った。
「ほい、ヌフヤグエン!」
周平はおじいちゃんに200円を渡しながら、彩と俺もこういうしわ顔の老夫婦になれるかなとフト思った。
△このページのトップへ
33『熱中症』
道秋は、さんざん歩き回った挙げ句、汗だくになって地べたにへたり込んでいた。そこは大きな池のある庭だった。投げやりになった道秋は、池の鯉に向かって枯れはらした悲痛な声で叫んだ。
「粉屋ーっ! おーい! 出てこーい!」
驚いた鯉が跳ね、バシャッと道秋の顔に水しぶきが飛んだ。
(ダメだ、ダメだ、ダメだ。これはどう見ても留守に違いない)
道秋は今来た道を引き返そうと、庭の脇を通って表の通りに出ようとした。
(あれっ? ここはどこだ?)
そこは、記憶にある風景とはまるで違う見覚えのない雑木林の中だった。道秋は迷子になった。
熱中症になった道秋がフラフラになってクルマに戻ったのは、出棺の時間を1時間以上も過ぎた午後2時半だった。気温は35度を超えていた。エンジンを切ったクルマの中で、照子もまた熱中症にかかってうなだれていた。30分後、『高合総合病院』の並んだ緊急用ベッドの上に、点滴を打たれて横たわる哀れな老夫婦の姿があった。
△このページのトップへ
34『団子の数』
へらを彩から受け取ると、スミは大きな鏡餅のような塊を今度は再び細かくしていった。そして、20個くらいのいびつな切り餅のようなものが出来上がった。
(せっかくまとめたのに、なぜ?)
彩はもう何が何だかさっぱり分からない。
へらで細分化されたいびつな切り餅は、各いびつな切り餅ごとに3人の手でまたグチュグチュグチュッと練り上げられ、最後にもう一回大きな1つの鏡餅状の塊に統合された。この行程を分かりやすくフローで示せば、
再細分化→再練り上げ→再統合。もっと視覚的に言えば、
いびつな切り餅→ねちょねちょっとした練り餅→美しい鏡餅
ということになる。それにしても何という複雑な作業であろう。彼女たちは、この作業中一切無駄口をたたかず、いたって真剣な職人顔で黙々とこれをやり遂げた。
(すごい! 何だか芸術的。さあ、いよいよこれから丸めるのね)
彩は期待に胸が膨らんだ。
「よしっ、丸めるど!」
いよいよ最終段階に入り、スミの声にも一層気合いが入ってきた。
その時だった。
「あいい、団子何ぼ作ればいいんだっけ?」
のり子が言った。
(出たよ)
「なんぼって、16・・・。あいい、なんぼだ? スミ」
マチが言った。
(あーあ)
「十六団子は明日だべ。今日の団子はログゴさ積み上げる団子だべ」
スミが答えをぼやかして言った。
「だがら、なんぼだ?」
のり子が単刀直入にスミに切り込んだ。
「とにかぐ、まずやってみでがらだでば!」
スタート時と全く同じ会話だった。
(まるで振り出しに戻ったようだ)
彩は、1時間前にタイムスリップしたような気持ちになった。
(それにしても、この人たちには「数」という概念はないのだろうか。あるところではものすごい精緻な作業をするのに、こういう最も肝心と思われる分量や個数といったところでは信じられないほど恐ろしくアバウトだ)
「いいが、このくれえの団子だ」
スミが見本となる団子を丸めて見せた。ビー玉とピンポン球の中間のサイズだった。かなり幅のある表現なので、かえって分かりにくくなることも承知でもう少し詳しく言えば、『チュッパチャップス』を130回ペロペロなめたくらいの大きさだった。
「あいい、それだば小せえべ」
のり子はそう言って、スミよりふた回りも大きな団子を作って、
「このぐれえだべ」
と言った。それは、こだわって言えば、チュッパチャップスを2〜3回ペロペロなめたくらいの大きさだった。
「のり子、なんも、それだばおっき過ぎるって」
マチが言った。
「いいがら、黙ってこんくれえの丸めろ!」
スミはそう言って、自分のサイズでどんどん丸め始めた。
「あいい、ちっちゃぐねえが」
のり子は最後までブツブツ言っていたが、それでも何とか6〜70個ほどの団子が出来上がった。3人のしわ顔にはキラキラとさわやかな汗が光っている。
(ふーっ、やっと完成ね!)
彩は、用意していた麦茶を3人に持っていった。
「さあ、一息入れてください。それにしてもすごい大変な作業なんですね」
彩がねぎらいの言葉を掛けた。
「彩ちゃん、びっくりしたべ?」
ニコニコしながらマチが言った。スミは出来上がった団子を満足そうに見詰めながら、
「こういうごどが大切なんだど、彩。簡単でねえがらごそ供養っつうもんなんだ。それにしても、なーんもねえ家だなや、銭の城っつうどごは」
と言った。
一方のり子は、出来上がった団子を不満そうに見詰めながら、
「ちっちゃぐねえが?」
と言った。
△このページのトップへ
35『大地、郁子、洋ちゃん』
「大きくなったねえ、洋(ひろし)君」
貴志は洋の頭をなでながら、大地と郁子に話し掛けた。
「ええ、やんちゃでどうしようもないんですよ」
郁子が言った。大地はおうように笑っている。
「それにしても遠路お疲れさまだったね。さあ、こっちに座って」
貴志が言った。
「ええ、その前にかなめばあちゃんに・・・」
大地はそう言ってかなめのところへ行くと、白い布を取って死に顔を見た。郁子も洋を連れて傍に寄り添った。
「かなめばあちゃん・・・」
大地はそう言って言葉に詰まった。郁子も目頭を押さえた。
チーンッ!
枕机にあった鈴をやんちゃ坊主の洋が鳴らした。
「洋!」
郁子が叱った。洋はどんぶり飯の割りばしを引っこ抜くと、それを持ってかなめの枕元にやってきた。
「ほら、洋、かなめばあばだよ。分かるかい?」
大地が言った。洋はポカンと口を開けてかなめの顔を見ていたが、突然持っていた割りばしをかなめの鼻穴に奥深く差し込んだ。
「こらっ! 洋」
慌てて郁子が洋の手を引っ張った。つられて割りばしも引っ張られ、かなめの鼻穴が大きく広がった。
「ヒャッ、ヒャッ、ヒャッ。ブータン、ブータン」
洋が笑った。
「洋!」
郁子が叱った。しかし、洋は全くひるむ様子もなく、またかなめの顔の前に行くと、今度はかなめの白髪頭をなでなでした。それから、顔を近付けてかなめの唇にチューッと長いキスをした。大地と郁子は何と言っていいか分からず、お互いに顔を見合わせた。
「ばあば、ちゅめたいっ!」
洋はそう言うと、プイッとそこを離れ、今度はまた枕机の前に行った。
チーンッ、チーンッ、チーンッ・・・。
洋は力任せに鈴を連打した。
奥田大地は、15年前に亡くなったかなめの妹、みよしの孫である。貴志しか子がおらず、その貴志も子宝に恵まれなかったかなめにとって、実妹の孫である大地は目に入れても痛くない存在だった。大地も自分が可愛がられた記憶がずっと残っていて、大人になってもかなめの家によく遊びにきた。
「だいつ、だいつ、おお、だいつ。よーぐ来たな」
というのがかなめの口ぐせだった。かなめがボケて施設に入ってからも、大地は神奈川から3度面会に行った。人の顔と名前が一致することがなかったかなめだったが、大地のことだけはなぜか覚えていて、
「だいつ、だいつ、おお、だいつ」
と、さもうれしそうに笑うのだった。
「結構かかったでしょう、向こうからだと」
貴志が言った。
「そうですね。高速道路の割引日に当たっちゃったんで結構混みました。15時間かな。昨日の8時頃出たんだから」
大地はそう言って腕時計を見た。
「徹夜で運転だったのかあ。そりゃあ、大変だったねえ」
「でも、こうして出棺に間に合ってよかったです」
「仕事のほうは、どう? 順調?」
「ええ、まあ。こういうご時世ですからね。クビにならないだけマシと思って頑張っています」
大地は神奈川の自動車部品工場に勤めていた。
「うちもそうだよ。中国に押されっぱなしでさ」
自動車と電子というジャンルの違いはあるが、同じ部品メーカーという点で彼らは話が合った。
チーン、チン、チン、チーンッ! チチチ、チーンッ・・・。
洋の鈴はいろんなバリエーションで鳴り続けている。洋のいたずらを持て余した郁子が、困り果てた顔で大地の隣に来て座った。
「まったく、これですから。本当にすみません」
「いえいえ、母さんも、にぎやかでかえって喜んでるでしょう」
貴志が笑顔で言った。
「そうそう、洋が描いた絵を持ってきたんです。一緒に棺に入れてもらいたいと思って」
大地が言った。郁子は紙袋から1枚の絵を取り出した。絵はとても前衛的なものだった。手前の大きなカマキリのようなものと、奥に小さな宇宙人のようなもの、それから、たくさんの団子のような丸いものの上に、人間のようなものが寝ているような、飛んでいるような・・・。貴志が判別できたのは、大体そのあたりまでだった。
「いやあ、独創的な絵だねえ」
貴志は感嘆して言った。
「何だかよく分からないでしょ? そのまん中の人がばあばだって洋は言うんですよ」
郁子が解説した。
「ああ、この人でしょ。この寝ているような、飛んでるような人・・・。ああ、そう言えば、どことなく似ているような、似てないような」
貴志が寝ているような飛んでるような人を指さした。
「ええ」
チチチ、チーン! ゴドッ。
洋は、ついに鈴をひっくり返したようだった。
△このページのトップへ
36『親分子分』
そこへ二所谷が大汗をかいて戻ってきた。二所谷は小脇に遺影写真を抱え、反対の小脇には傘の束を抱えていた。
「喪主さん、これ見てください。こっちのほうが全然いいですよ!」
二所谷は遺影写真を貴志に差し出した。顔のしわまで拡大された白髪の老婆が写っていた。
(そうかなあ・・・)
貴志はそう思って、修正版の写真のあるほうをチラッと見やった。
いつの間にか傍に来ていた洋が、持ってきた写真を見て言った。
「ばあば、ばあば」
大地も郁子もその写真に満足しているようだった。
貴志は修正版と比較してみることをあきらめた。
「いやあ、どういうわけか、会社に9本しかなかったんですよ。困ったなあ。源蔵さん、怒るかなあ」
すっかり子分と化した二所谷は親分の機嫌を気にしている。彼の持ってきた傘には黒い文字で、『葬祭センタービューティフルセレモニー』とグルリ全面に大書されていた。
ちょうどそこへ、やはり大汗をかいて源蔵が戻ってきた。
「チッ、これしか集まらねがった」
彼はそう言って抱えてきた傘を、バラバラバラッと上がりかまちに広げた。二所谷は「親分!」とばかりに近寄ってくると、
「申し訳ありません。私のほうはたった9本でした」
と、肩を落として言った。
「チッ、葬儀屋、大難儀かげだな。ほいでも、チッ、おらの34本ど合わせれば43本だ。まあ、今日のどごろは何とがなる」
「それにしてもさすがですね。1本1本にみんな名札が付いている。これ全部ご自分で縫われたんですか?」
子分が親分に敬服して言った。
「ああ、チッ、間違うどかなわんがらな」
源蔵の持ってきた傘には白い布が1本1本縫い付けられていた。そこには、『伝助のチーちゃん』とか、『三十郎のゴサグの孫娘まなみ』といった具合に、家号のようなものと所有者の名前が1本1本抜かりなく細い油性マジックで書き込まれていた。
(一体、いつそんな時間があったんだろう?)
貴志は、源蔵のきちょうめんさもさることながら、その手際の良さがにわかに信じられなかった。
(この人は天性の葬儀屋なんだな。二所谷が敬服するのも分かる)
貴志はつくづく舌を巻いた。
「これから雨なんですか?」
その状況をずっと興味深く見ていた郁子が貴志に聞いた。
「いや、天気予報では明日まで快晴です」
「・・・」
郁子はしばらく何か思案していたが、ハッとひらめいたように、
「あっ、そっか! 日傘ですね」
と言ってひざを打った。
(本当はそうじゃないんだけどな)
そう言おうと思ったが、話が面倒くさくなるだけだと思い直し、貴志はそれ以上の説明を割愛した。
△このページのトップへ
37『タマヨの握り飯』
源蔵のすぐ後に戻ってきた周平は、勝手口から入って台所に顔を出した。
「帰ったよ!」
台所では、盛り付けを待つばかりの団子を前にみんなが一服しているところだった。
「おお、お帰り。周ちゃん、ご苦労さんだったなあ」
マチがまず声を掛けた。
「おっ、団子でぎだのが? すげえなあ」
周平が言った。
「ああ、あどはログゴさ盛って終わりだ」
スミが安堵した表情で言った。
「みんな、ご苦労さんだな。あっ、明日の粉挽いできたど。ほらっ」
周平が袋を2つ差し出した。
「やあや、周平ありがど。ほんとに助かったわ」
スミが言った。マチものり子も、キラキラした瞳を周平に向けている。彩は何だか自分のことのように誇らしい気持ちになった。
「あっ、そうそう、これもらったがら、みんなで食べてや。すっげえうめえど」
周平はもらった漬けものの袋も差し出した。みんなのキラキラした瞳が一斉にその袋に注がれた。のり子の腹がグーッと鳴った。そう言えばもう昼時だった。
「みんな、まんま食ったのが?」
周平が聞いた。
「いやあ、あど盛れば終わりだがら、それがらだ」
マチが言った。
「あのなあ、タマヨばあがな。おにぎり持っていげって、こんなにもらったんだよ。みんなにも食わせろって」
周平は、タマヨが愛用している肩ひもの付いた巾着袋を肩から下ろすと、それごとマチに手渡した。マチが中を開けると、アツアツのおにぎりが5個ずつ入った包みが3包み出てきた。包みは竹の皮に包まれていた。
「わあーっ!」
彩がまっ先に歓声を上げた。
「タマヨの握り飯はうめえんだ」
スミが言った。
「漬けもんもあるがら、言うごどねえな」
のり子も目を輝かせている。
「あっ、それがら、直接、作業場さ行ってみろって、のりばあの言ったとおりだったぞ。お陰さんで、ありがとよ」
周平はそう言ってのり子の顔を見た。のり子は、
「それほどでもねえが・・・」
と言って、赤い顔で少し照れた。
周平が彩に目配せをして立ち去ろうとすると、スミは、
「周平、貴志がら200円もらえよ!」
と、いつものように言った。
「周ちゃんも、あどで一緒に食べような」
マチが言った。
周平は笑顔でみんなに手を振ると、勝手口に立て掛けておいた傘の束を持って玄関に回った。
△このページのトップへ
38『貴志の嘘』
「おお、周平君。ありがとう!」
貴志がいち早く周平に気付いた。周平は貴志に軽く会釈をしてから、源蔵に向かって言った。
「ここには25本しかありませんが、今、村の邦彦さんと滋子にも集めてもらってます。それから、駐車場は貫太郎おじに了解してもらいました。好きなだけ使っていいって。30台は停められるでしょう。そこの向かいのうちです」
源蔵は、周平の話をチッ、チッ、と言いながら聞いていたが、
「大難儀掛げました」
と言って深々とお辞儀をした。傘は、43本と25本で全部で78本になった。すでに大台を上回る数ではあったが、周平の話ではまだその数は増えそうだという。
(ひょっとしたら、百本超えるかもしれないな)
貴志は、ここまできたらそれだけの数の傘を見てみたいというおかしな衝動に駆られた。
「皆さん、お昼は?」
洋を抱き上げながら周平が言った。洋は周平のモンタージュ顔が気に入った様子で、目や鼻や口をモンタージュ写真のようにいじくり回している。
「あっ、そう言えば、美樹が買ってくるはずなんだけど・・・」
貴志はそう言ってから、
(しまった!)
と思った。悪い予感は的中した。
「チッ、何? 美樹はまだなのが!」
久しぶりの源蔵の金切り声だった。
「そう言えば、美樹さんいないですね」
大地が言った。
「あ、うん。ちょっと急用ができて・・・」
貴志がしどろもどろになりながら言った。
「チッ、こんな大事な時に。何だ、急用って!」
貴志は追い詰められた。
(まさか、飼い猫が病気だとは、口が裂けても言えない)
「あっ、実は・・・。美樹の・・・」
「美樹の何だ!」
源蔵が詰め寄った。
「はあ、美樹の、美樹の・・・」
全員が、身を乗り出して貴志に注目した。
「おとうさんが病気で・・・」
チーンッ!
周平の手を離れた洋がお気に入りの鈴を鳴らした。
大地と郁子がそろってため息を吐いた。
(あー、やばい、やばい。嘘をついてしまった!)
貴志は、自分の口から出てしまった取り返しのつかない言葉に激しく狼狽した。その様子を別の意味で取った大地は、
「要三さん、そんなに悪いんですか?」
と、真剣な顔で貴志に聞いた。郁子も心配そうに顔をゆがめている。
「ああ、まあ、ちょっと、ええ。去年おかあさんが亡くなってから、少し、ええ、病気がちで・・・」
自分の口から嘘が勝手に飛び出していることに貴志は気付いてはいた。気付いてはいたが、もうどうしようもなかった。
(こうやって、嘘はどんどん上塗りされていくんだよな。でも、この場合、嘘も方便ってやつなんだ。だってどうしょうもないじゃないか)
貴志は半ば開き直ってそう思った。
「チッ!」
源蔵は舌打ちをしただけでそれ以上の言及をしなかった。
(あとで美樹とお父さんに口裏を合わせてもらうしかない)
貴志は小賢しいことまで考え始めていた。
「まんま、まんま」
洋が郁子のひざに座って言った。
「そうね、ご飯ね」
郁子が言った。
「よかったら、おにぎりがありますから、皆さんでいかがですか?」
周平が言った。洋が周平の足にしがみついた。周平は洋を軽々と抱き上げると、台所のほうに向かって歩き出した。
△このページのトップへ
39『メッセージカード』
「ええ、では、これから出棺に先立ちまして、故人に旅の支度を施しますが・・・」
みんながおにぎりを食べ終え、一息ついたところで二所谷が言った。
「その前に、こちらにメッセージカードがありますから、故人への思いをおのおのつづってあげてください」
彼が取り出した短冊型のカードは、ベージュやライトブルー、淡いピンクなど、どれもカラフルなものだったが、なぜかカードの下部に『葬祭センタービューティフルセレモニー』と印字されていた。
(旅立つ人に今更宣伝もないんじゃないの?)
貴志は不思議だった。
「えー、それからこの台紙にも、何かひと言書いてあげてください」
二所谷は、これが当葬祭センターオリジナルのスペシャルサービスでーすと言わんばかりに、それらの紙類とカラフルなサインペンセットをテーブルの上に広げた。
(何て書こう?)
ペンを持った貴志だったが、あらたまってみると書く言葉が見つからない。貴志は考え事をする時のいつもの癖で、左手で頬杖を突いた。
源蔵は、
「チッ」と言いながら、淡いピンクのカードを1枚取り出すと、
「チッ、葬儀屋!」
と言った。
(また文句かよ)
「何色のペンで書げばいい?」
(えっ?)
貴志の頬杖がカクンと外れた。
「ピンク系の紙ですから、暖色系の色がよろしいかもしれませんね」
「チッ、おう」
源蔵は暖色系の意味が分からなかったようで、濃い青のペンを持って書き始めた。
大地や郁子もそれぞれに紙とペンを持った。
「あっ、周平さんもどうぞ」
二所谷は周平にも書くように促した。
「え? でも、俺は親族じゃないですから」
「いいんです。故人へのはなむけですから。さっ、どうぞ!」
二所谷は薄い緑色のカードと濃い紫色のペンを周平に渡した。
周平はそれを手に取ってかなめとの思い出を回想してみた。小さい頃の記憶が幾つか浮かんできたが、一番印象に残っているのは、3年ほど前に同級生の滋子に用があってかなめが入所していた『さやか苑』という施設に行った時のことだった。
△このページのトップへ
40『さやか苑のかなめ』
「周ちゃん、宮下の貴志さんちのばあちゃん、分がる?」
「ああ、分がるよ」
「あのばあちゃん、こごさいるんだよ」
滋子が言った。
「へえー、そうが?」
「うん、会っていってみるが?」
そう言って、滋子は周平をかなめの部屋に案内した。かなめは、ベッドの上で「結んで開いて」の動作で手を動かしながら、ブツブツ独り言を言っていた。
「かなめばあ、元気が?」
周平は枕元で声を掛けた。かなめは一瞬キョトンとして周平を見詰めると、急に視界に花が咲いたように、満面輝かしい笑みを浮かべた。
「おお!」
かなめは結んで開いての手を大きく広げて、恋愛映画の再開シーンのように叫んだ。
「おおー! おおー! おおー!」
周平は予想もしなかったかなめの歓迎ぶりに、少し戸惑いながら滋子を見た。滋子はクスクス笑っている。
「かなめばあ、分がるかい?」
周平は自分を指さしながら尋ねた。
「ん?」
かなめは小首を傾げた。滋子は「耳が遠いんだよ」と言う代わりに、自分の耳を指さして周平に教えた。周平はかなめの耳元に顔を近付けて大きな声で聞いた。
「かなめばあ、俺誰だか分ーがーる?」
かなめは、うん、うんと大きくうなずいた。
周平はニッコリ笑って、かなめと滋子を交互に見た。
周平がかなめに向かって次の言葉を言いかけた時、かなめが満面の笑みでこう言った。
「おめ、誰だ?」
(あれっ?)
周平はカックラキンになった。
「周平だよ、大工の晋平の息子の」
「おおー! おおー!」
「ばあちゃん、元気かい?」
「ん?」
「げーんーきーだったあ?」
かなめは、また、うん、うんと大きくうなずいた。
かなめは満面の笑みでまた言う。
「おめ、誰だ?」
(あれ?)
周平はこける。
滋子は隣でクスクス笑って、そのやり取りを聞いている。
「貴志さんたちは来るのかい?」
「ん?」
「たーかーしーさん来るう?」
うん、うん、かなめがうなずく。そして言う。
「おめ、誰だ?」
こういうやり取りが果てしなく続いた。
「じゃあ、帰るからな。かなめばあ、元気でな」
帰り際に周平が言った。
「ん?」
「げーんーきーでーなあ」
かなめは、うんうんとうなずいた。
周平が滋子と一緒にドアを開けて廊下に出ようとした時だった。
「おめ、誰だ?」
結んで開いてをしながら、かなめがまた言った。
(ダメだこりゃ)
滋子は、プッと吹き出して周平を見た。
周平が忘れられないのは、周平の顔を見てから帰るまで終始かなめが見せていたこれ以上の笑顔はない、というような無心で無垢なあの笑顔だった。周平はカードに、
ーかなめばあの笑顔、素敵だったよ。周平ー
と書いた。
△このページのトップへ
41『お棺行っちまう』
二所谷は余ったメッセージカードを持って、台所にまで進出した。
「みなさん、こちらにメッセージカードがあります。故人の旅のはなむけになりますので、そうぞ何か書いてあげてください」
「あいい、おらだぢも書くのかい?」
マチが目を丸くして言った。
「そうです。みなさんこそ、書いてあげるべき方々です」
「あいい、すかだね、なんとだど」
のり子は腰を浮かして前掛けで手を拭いている。
「どれ、ちょっと、おら、メガネ持ってこねばね」
マチはソワソワして立ち上がった。老眼鏡を家に取りに行くというのだ。
「やめろ! お棺行っちまう」
スミが止めた。
ひとしきりみんなが書き終わったのを確認した二所谷は、貴志たちに向かって言った。
「さあ、じゃあ、色紙のほうにもお願いします」
そう言ってテーブルの上を探した二所谷だったが、色紙はそこになかった。色紙は遠く枕机の上にあった。彼はそれを手に取って驚いた。そこには、大きなカブトムシのようなものと、小さな船のようなもの、そして、たくさんの団子のような丸いものの上に、横になっているか、飛んでいるような人間のようなものが、カラフルな色彩で、色紙の裏表いっぱいに描かれていた。
△このページのトップへ
42『美樹』
なかよし動物クリニックを出た美樹は、パンフレットを持っていったんマンションに戻った。昼食を買って11時半までには帰ることになっていたが、美樹はそのまま愛宕村に向かう気力がわかなかった。
美樹は、ダイニングテーブルの椅子にガックリと肩を落として腰掛けた。
自分の中から魂がスッと抜けてしまったような、もぎ取られるような喪失感を美樹は心のひだで感じていた。ジャムのいない部屋は生気のない無機質な空間だった。暗い部屋の中で、頬杖を突きながら美樹は、ジャムと過ごした18年間を思い起こした。涙がボトボト音を立ててテーブルの上に落ちた。
時計はすでに11時を回っていた。
美樹は涙を拭うとヨロヨロと椅子から立ち上がった。床に美樹の黄色いバスタオルが落ちていた。あの夜、かなめの危篤の報を受けて慌てて出掛けていった時の残骸だった。
(あのことがなければ。あのことさえなければ・・・)
それを拾い上げた美樹は、そこにジャムの白い毛が付着しているのを見つけた。美樹はバスタオルを抱きしめ、それに顔を埋めて激しく嗚咽した。
△このページのトップへ
43『旅装束』
「さあ、では、いよいよ旅の支度を行います。ええ、旅装束を着せることはどういう意味があるのでしょうか?」
二所谷はみのもんた調に切り出した。
(もう、メモとか言わないでよ)
貴志は、あの夜のことを思い出してちょっと身構えた。
「それは、死というのは、つまり西方浄土への旅立ちを意味するからです」
洋はかなめの浴衣の裾をめくって、興味津々の目で中を眺めている。
「こらっ、洋!」
郁子が叱った。二所谷は洋のほうに目をやって、
「ええ、今、おぼっちゃんがめくっている浴衣の上にこの経帷子を着せます。最近では、簡略化して浴衣の上に掛けるだけにしたり、故人が着ていた洋服などを着せる人もおりますが私は断固好みません。古くからの本式にこだわりたいからです。経帷子は左前に着せることになっております」
と言った。
(それにしても、なんでこの人は、こんなに古来、本式にこだわるんだろう)
貴志は思った。
洋は、自分に視線が注がれていることに気を良くしたのか、浴衣の裾をつかんで思い切りそれを引っぱがした。かなめの陰部が露出した。
(わっ!)
「こらっ、洋!」
さすがにこの時は大地が叱った。大地は慌てて着衣の乱れを直すと、洋の手を引っ張って座敷の奥に連れていった。
全員、何となく、見てはいけないものを見てしまったというかなり気まずい空気が流れた。
うっ、うっ、うえーん・・・。
遠くで洋の泣き声がした。
経帷子を着せるのは予想以上に大変な作業だった。死後硬直状態のかなめの腕はなかなか思うように曲がってくれなかったからだ。貴志、周平、源蔵、二所谷は、まるで『リカちゃん人形』の着せ替えの時のように、かなめの体を右に倒し、左に倒し、腕を曲げ、腰を起こして、全員汗だくになりながら悪戦苦闘した。かくして経帷子をまとった『かなめちゃん人形』は出来上がった。
二所谷はしたたる汗を腕で拭うと、緊張した面持ちでこう言った。
「ええ、それでは、手甲、脚絆、三角巾、白足袋、わらじの順で身に付けさせていきます。白足袋、わらじは左右逆に履かせます。これはご遺族の最も大切な仕事です。ええ、まずは手甲です。こんなふうにやります」
二所谷がしゃがんで見本を見せている時、彼は偶然美樹と目が合った。いつの間にか戻っていた美樹は、音もなく座敷の後ろのほうに1人立っていたのだ。
「あっ、奥さん、じゃあ、これやってください」
二所谷はそう言って、もう一つの手甲を美樹に差し出した。
(奥さん?)
驚いて貴志は二所谷の視線の先に目をやった。美樹がいた。源蔵や周平、郁子も美樹を見ている。全員の視線が美樹に注がれた。
「ほかの人やって」
ふてくされたようなしゃがれた低い声で、肩をゆらゆら揺らしながら美樹が言った。一瞬、場が激しくピリピリした。
「ダメです、奥さん、あなたがやってください」
いつもより強い口調で二所谷が言った。
源蔵は、チッ、チッ、チッを繰り返しながら、すごい形相で美樹をにらみ付けている。
「誰かほかの人やって」
美樹がまた言った。
貴志は、美樹と二所谷と源蔵の顔を交互に見比べながら激しく狼狽した。
(ぼくがやりましょう)
という言葉がとっさに浮かんだが、それで事態が収拾するとは思えなかった。その時、周平が美樹に笑顔を向けた。
「美樹さん、どうぞ」
周平は、そう言って美樹を手招きすると、二所谷から手甲を受け取り美樹の元に持っていった。
「さっ、どうぞ」
仏頂面で手甲を受け取った美樹だったが、周平の笑顔にほだされたのか渋々かなめの傍に歩み出た。貴志はホッとした。
「あーあ、奥さん、そうではありません!」
手甲のひもを結んでいた美樹を二所谷は慌てて制止した。
「ひもは縦結びです!」
「何それ」
二所谷にガン付けながら美樹が言った。
「縦結びというのはこうです。さっき見てなかったんですか?」
「うん」
二所谷は一瞬ムカッとした顔になったが、気を取り直して、
「こういうふうに、結び目が縦になるように結ぶんです!」
と言いながら実際自分でやってみせた。
「そっ」
美樹はそう言って立ち上がると、さっさと自分のいた場所に戻った。
何となく気まずいムードの中、旅装束のセレモニーは進んでいった。わらじを履かせる作業は、ひもの掛け方が複雑だったばかりでなく、足の指が開かなかったり、くるぶしが曲がっていたりして難航を極めた。左足を担当した周平は、ほふく前進のスタイルで、頭を畳にすり付けながら、まるでクルマの修理工のようにその難作業をやり抜いた。
したたる汗をまた拭った二所谷は、
「では、お手数ですが、男の方にお願いしてご遺体をお棺に納めます」
と言った。各自汗をしたたらせながら持ち場に着いた。
「せえの!」
息が合っていた。旅装束のかなめは静かに棺桶に納まった。
(いいチームワークになってきたぞ)
貴志は思った。二所谷は「うんうん」と満足げにうなずいて、今度は段ボールの中から白い袋を取り出した。
「ええ、この頭陀袋の中には六文銭が入っております。六文銭は三途の川の渡し賃です。どなたか肩に掛けてやってください」
貴志はチラッと美樹を見た。美樹は、フンとそっぽを向いている。
「あっ、はい!」
貴志が手を挙げた。
「ええ、最後に、こちらの数珠と杖を持たせます。はい、どなたか」
二所谷はそういって周りを見た。
「チッ」
源蔵は、美樹をいまいましく見やってから数珠を取った。
「どなたか、杖を」
貴志は郁子に目配せした。郁子は美樹を気にして視線を送った。美樹は右肩を斜めにしてゆらゆら揺らしながら、やはりそっぽを向いていた。
「あっ、はい!」
郁子が慌てて手を挙げた。
「これで無事旅の支度が整いました。では、故人にお土産を持たせてあげてください。先ほどのメッセージカードや色紙、何か思い出の品などありましたらお入れ下さい。眼鏡や時計、指輪などの貴金属は入れることができません」
(思い出の品か・・・)
貴志はあらためて、かなめとの思い出の少なさに思い至った。
(何かを買ってやったりしたこともなく、旅行はおろか食事にさえ誘ったことがなかった。そういう50年を俺は過ごしてきたんだ。たった1人の息子だというのに)
貴志は、さっき書いたメッセージカードを丸めてポケットにしまうと、もう一度座敷に戻ってペンを取った。
洋が泣きはらした目で戻ってきた。洋は郁子に手を引かれ、自分が描いて持ってきた絵と、さっき色紙に描いた裏表2種類の絵、つごう3部作の「・・・のような絵」を棺桶に入れた。台所にいたスミたちも呼ばれ、めいめいに書いたメッセージカードを入れて手を合わせた。マチのカードには、
ーかなめ、おぢゃのみ楽しがったな。団子食って元気にくらすてください。マチー
と書かれていた。スミは、
ーみぼずんくらぶはおらさまがせろ。なんもすんぺねえ。スミばばー
と書いた。
ーあいいい、すかだにゃなああ。ー
と書いたのは、のり子だった。
最後にかなめの胸に置かれた貴志のメッセージカードには、
ーかあちゃん、ごめんな。何もしてやれなかった俺を許してください。親不孝息子ー
と書かれていた。
二所谷はたくさんの切り花を箱から出して、全員に配りお棺に入れさせたが美樹はそれにも参加しなかった。最後の最後に棺桶のふたに釘を打つところでも、美樹は肩を揺らしそっぽを向いたままだった。怒り心頭に達した源蔵は、貴志から石を受け取る、怒りに任せてそれを振り下ろした。
ダンッ!
金属音ではなかった。
豚ロース肉を叩いたときの音だった。
△このページのトップへ
44『かなめとジャム』
時計は12時半を回った。1時の出棺を前に、宮下家には村の別家衆たちが集まり始めていた。本家の作之進は、息子の一三と連れ立って黒い喪服姿で現れた。2人とも顔にびっしょり汗をかいていた。作之進は愛用の竹の杖を持ち、一三は同じく愛用の書道具箱を抱えていた。2人は、玄関の前でいったん立ち止まると、ほぼ同時に深々と貴志に頭を下げた。
「あっ、どうぞ作之進さん、一三先生、中へお入り下さい」
玄関を掃いていた彩が2人に向かって声を掛けた。
「かなめの、旅支度は済んだかの?」
作之進がゆっくりした口調で言った。
「ええ、先ほど終わりました」
作之進から竹の杖を受け取った彩がそう答えた。作之進は安心したように「うんうん」とうなずいて、
「いよいよ、行ってしまうんじゃのお」
と、少し寂しそうな顔をしてハンカチで額の汗を拭った。
一三は、昨日帰っていった時の難しい顔に疲労の色を浮かべて座敷に上がると、貴志の傍に行って、
「いやあ、苦労すますた。徹夜ですた」
と、声をひそめて耳打ちした。
「そうでしたか。先生、本当にすみません」
貴志は恐縮した。
「いやあ、とんでもない。これは、僕の能力のなさゆえのことです。お恥ずかすいことです。昔、君だぢの通信簿をつける時にも、僕は3日も徹夜したことがあるくらいなんです。本当にお恥ずかすい限りです」
一三はそう言って書道具箱を開けて、順番を書いた紙を取り出した。目を見張るような達筆な文字が半紙いっぱいに整然と並んでいた。
「わあ!」
貴志は思わず感嘆の声を上げた。
しかし、一三はここでまた急に難しい顔になって、
「これは完成ではないんです」
と言った。
「えっ? と言いますと」
「ええ、ここに、美樹さんの関係者も入れなければなりません」
(あっ!)
貴志は、昨日一三に言われていたことを思い出した。あの後いろんな事があり、貴志はすっかりそのことを失念していたのだ。
「ああ、そうでしたね。すみません、その連絡がまだでした」
貴志は頭をかきながら一三に詫びた。
「いやいや、忙すい時ですから無理もありません。それで、美樹さんは?」
「あっ、はい。今呼んできます」
貴志は立ち上がって美樹を捜した。台所にも居間にも美樹の姿はなかった。仕方なく戻ってきた貴志は困惑した顔で言った。
「先生、すみません。ちょっと見つからないものですから・・・。あっ、彩さん、美樹知りませんか?」
彩は玄関の履物をそろえていたが、ちょっと考えて、
「もしかしたらあちらの部屋かもしれません。さっき入っていったような・・・。私見てきましょうか?」
と、居間の隣の部屋を指さした。そこは、かつてのかなめの寝室であったが、貴志たちが家を改修した時に、自分たちの寝室用に作り替えた部屋だった。もっとも、ほとんどこの家に泊まることのなかった2人にとってその部屋は、立派なダブルベッドや家具はあっても、実際には物置に過ぎなかったのだが。
「ああ、いいです、いいです」
立ち上がった彩を笑顔で制した貴志は、その部屋に向かって歩き出した。
「ああ、貴志君、忙すいようなら後でも構いませんからね」
一三が貴志の背中に声を掛けた。
「ええ、大丈夫です」
貴志が、軽くドアをノックして開けてみると、カーテンを閉め切った真っ暗な部屋の中に美樹の小さな影があった。美樹はベッドの隅に腰掛けていた。
「おい、どうしたんだよ!」
「何が」
「何がって、さっきの態度だよ!」
「・・・」
「もうすぐ出棺なんだから出てこいよ。一三先生もお前の関係者のことで用があるって言ってるし」
「何、用って」
「だから、お前の会社関係者とか、親族のことを詳しく聞きたいって」
「何すんの」
「何って、お膳に座る順番とか、野辺送りの持ち手を決めるんだって」
「適当にやって」
「だから、そうはいかないんだよ」
「なんで」
「なんでって、そういうしきたりっていうか、それが大事なんだって」
「なんで、それが大事なの」
「えっ?」
「もっと大事なことがあるじゃない!」
「・・・」
「ジャムはね、ジャムは・・・」
美樹はそう言って言葉に詰まった。それから肩を振るわせ声を殺して嗚咽した。ダブルベッドのバネのせいで、美樹の体は大きく上下に揺れている。
貴志はジャムのことを失念していたが、そのことを美樹に詫びる気にはなれなかった。むしろ貴志は、沸々とわき上がってくる強い怒りの感情にあらがえなくなった。
「ジャムと俺のかあさんと、どっちが大事なんだ!」
貴志はそう叫んで部屋の外に出ると、乱暴にドアを閉めた。
貴志が美樹に対してここまで感情的になったことは今まで一度もなかったことだ。意見の対立があっても、先に折れるのは決まって貴志だった。
(しまった。俺らしくないことをしてしまった。こんな状況の中で異常に高ぶっている神経のせいなのか・・・)
ドアを閉めながら貴志は一瞬激しく内省した。
(でも・・・)
貴志は思った。
(これは違う。かなめよりも飼い猫が大事なはずがないじゃないか。かなめは人間なんだ。しかも俺の母親なんだ。かなめの死以上に大事なことがあるものか)
貴志はそう自分に言い聞かせて座敷のほうに振り向くと、そこに忘れようのない懐かしい顔があった。
△このページのトップへ
45『クニちゃん』
「よう!」
「あっ!」
「分がっぺ?」
「ク、クニちゃん、クニちゃんか?」
「んだ、久しぶり!」
邦彦は、昔スイカを盗んだ時と同じいたずらっぽい笑顔を貴志に向けた。貴志はささくれ立っていた気持ちが急速に和らぐのを感じた。
「傘のことで、邦彦さんにも世話になって」
隣にいた周平が言った。
(そうか、邦彦っていうのはクニちゃんのことだったのか)
貴志は周平が言っていたことを合点した。
「ああ、すまない。クニちゃん。助かるよ」
貴志はそう言って笑顔を作った。
「俺のほうは36本。あど滋子が施設がら持って来る」
邦彦が言った。
これで滋子の分を待たずに傘は100本を超えた。貴志は源蔵の喜ぶ顔を思い浮かべた。同時に、傘集めの目的や意義のいかんはさておき、この『傘集めプロジェクト』の団結力のすごさに胸を打たれた。
(でも、返す時はまた大変だろうな)
そう思うと貴志は、理屈じゃなくとてもありがたい気持ちになった。
「クニちゃん、何年ぶりだべな」
そう言ってから貴志は、自分の言葉が昔のようになまっていることに気が付いて少しおかしくなった。
「高校までは、ちょくちょぐ会ってだどもな。タガが大学さ行ってがらは一度も会ってねがったべさ」
「せば、かれこれ40年にもなるんだなあ」
「うん。おめえ、厄年の同級会さも来ねがったもんな」
(そうだった。そう言えばあの時は会社の組合問題があって行けなかったんだっけ)
貴志は15年前のことを思った。
「だども、タガは出世頭だって、同級会の時もみんなしゃべってだぞ。おらなんか、何て言われだど思う? 『クニちゃんは、相変わらずのいだずらボンズのまんまだなあ。なーも変わんねえなあ』って」
邦彦はそう言って笑った。日焼けした顔から真っ白い歯がこぼれた。
「おら、勉強きれえだったけど、牛の言葉は分がるんだど。モーにもいっぺえ意味があってさ」
「えっ? 牛の言葉?」
「ああ、おらベゴ飼ってんだ。18頭。五反山のふもとさ牛舎こしらえで少しずつ増やして今年で8年目だ」
「へえー、それは知らねがったなあ」
「父ちゃん死んでがら始めだんだ。あっ、周平さも手伝ってもらってる。牧草刈ってもらったり牛舎掃除してもらったり。なあ周平」
邦彦はそう言って周平に目配せした。周平はいつものモンタージュ顔でほほ笑んでいる。
「へえー、それは知らねがったなあ。だば事業家でねえが、クニちゃん」
邦彦は事業家という言葉に少し照れて、
「なーも、ほでね。ただのベゴ飼いのペーターだべよ」
と言って笑った。
その時貴志は、自分の後ろを何かがスーッと動く気配を感じた。邦彦と周平の視線の動きから、それは実体のあるものであることが分かった。彼らの視線は一三のいる方向で止まった。貴志が目をやると、美樹は一三の前に座り何かしゃべっている。彼女の表情に生気はなく、もし事情を知らない人が見たら、葬儀の悲しみに憔悴し切っている遺族の姿に見えないこともない。いや、あるべき遺族の姿そのものだ。対面している一三の表情もそれを反映してかいたって神妙なものになっている。
それを見ていた貴志は、同級生との昔話に花を咲かせている自分が少し浮いているような感覚を覚えた。
「じゃ、おらはこれで。明日はダミの手伝いさくっから」
邦彦も何となくそういう場違いな雰囲気を感じたのか、そう言って別れを告げると傘を置いて帰っていった。
△このページのトップへ
47『美樹と一三』
「彩ちゃん、ちょっと来てけれ、ちょっと来てけれ」
座敷に顔を出したマチが、言葉とは裏腹なのんびりした顔で彩を呼んだ。
「何でしょう」
次々にやってくる村人たちに座布団を勧めたり、お茶を出していた彩が答えた。
「何が紙っこねえべが」
マチは座敷の入り口に立ってそう言った。
「えっ? 紙っこ、ですか?」
「うん、ほれ、団子載せるログゴの上さ敷ぐ、こう、真四角の白い紙っこだ」
マチは指で四角を作った。
「ああ、団子のあれですね」
彩も同じ四角のポーズを作ってうなずいた。
それから彩は美樹のほうに視線を送った。美樹は、一三の前で取り調べを受けている犯人のようにうつむいていた。彩はそっと近付いていくと、美樹の後ろから声を掛けた。
「あのう、美樹さん、何か紙ありませんか? 団子を載せる白い紙です」
美樹は黙ってうつむいている。その様子を遠くから見ていたマチは、首を傾げて思案顔になった。
「あのう・・・」
もう一度そう言った彩に、美樹は無言で首を横に振った。
彩は困惑してマチのほうに視線を送った。
その時、間近な所で声がした。声の主は一三だった。
「すろい紙なら・・・」
一三は、そう言って書道具箱から半紙を2枚取り出すと、
「こごに!」
と言って、彩にサッとそれを差し出した。
「わあ、すごーい!」
彩が驚いて叫ぶと、一三はウーパールーパー顔の小さな鼻をヒクヒクさせて、ふふっ、ふふふっ、と笑った。
「さっ、どうぞそうぞ。遠慮なくふふっ、ふふふっ・・・」
「助かりましたあ!」
彩は一三にお辞儀をしてから、マチにもニッコリ笑って合図を送った。。
「いえいえ、また必要なら、いくらでもふふっ、差す上げますからふふっ、ふふふふふっ・・・」
鼻の中ではじけ出しそうな笑い玉をどうにか抑えつつ、一三はゆっくりと美樹のほうに向き直った。
「いやあ、こんなこともあろうかと思ってふふっ、僕はいつもふふっ、書道具箱だけはふふふっ、手放せませふふふふっ・・・」
「・・・」
・・・。
「・・・」
・・・。
一三はコホンとひとつ咳払いをした。そして急に難しい顔になって会葬者リストに目をやった。
「このう・・・近藤・・・」
「武郎」
「このう・・・近藤武郎さんの役・・・」
「社長」
「しかす、新聞社の場合、社主とい・・・」
「社長」
「代表の場合はいろい・・・」
「社長」
「しかす、それは正式・・・」
「社長」
「・・・」
△このページのトップへ
47『アバ?』
一方台所は、いよいよ本日の最終段階を迎え、にわかに緊張感がみなぎっていた。紙を調達して凱旋したマチと彩を「ごぐろう」とねぎらったスミは、この日最後の訓示をたれるべく、また対面キッチンの向こう側のステージに歩み出た。
「あー、こっからが最後の仕上げだ。おのおの手抜がりのねえように。団子を三角に並べる役はおらがやる。以上」
スミの訓示は、朝礼と同じく声だけの、つまり、あまり説得力のないものだった。
(手抜かりと言われても、この段階で団子を並べる役以外に、何かやることがあるのだろうか?)
彩は不思議に思った。
「少しおっきぐねえが?」
半紙を手に持ったのり子が言った。
「んだな」
スミが言った。
(おお、初めて大きさのことで、2人の意見が一致したぞ!)
彩はうれしくなった。
「したらば、長えどご切って真四角にしろ」
すかさずスミの指令が飛んだ。
「あいい、彩ちゃん。ハサミねえがい?」
マチが言った。
(ハサミ、ハサミ・・・)
彩はその辺を探したが、ハサミもカーターナイフも見当たらなかった。
「美樹さんに聞いて・・・」
「いい!」
スミがさえぎるように言った。
「アバさ聞ぐごどねえ!」
(アバ? 何?)
△このページのトップへ
48『スガズ?』
彩は一瞬疑問を持った。愛宕村に来て5年、随分方言には慣れてきたつもりだったが、いわゆる隠語だとか、感情や抽象的なイメージを表す言葉は難しく、その意味を尋ねても、かえって意味が分からなくなるということが多かった。
彩が愛宕村に来たばかりの頃、ミニトマトの苗を一束抱えて、彩たちの畑に現れたおばあちゃんがいた。
「おらはスガズっちゅうもんだども、ほれ、苗っこ余ったがら、おめえさけっから」
「わあ! ありがとうございます。こんなに?」
「ああ、あどナスの苗っこも今度持ってきてやっから」
「わあ! すみません。おばあちゃん、スガ・・・」
「スガズだ」
「スーガーズ?」
「ああ、変わってるべ」
スガズと名乗ったおばあちゃんは、そう言って笑うと自分の名前の由来をこう説明した。
「おらのなめえは、スガズっちゅうが、おらの父親がな、役場さ行って戸籍係さこう告げだんだど。『おらは字書げねえがら、おめえに代わって書いでもらいてえ。娘はスガズ生まれだ。だがらスガズって名にした。そう書いでけれ』って。だども、おら学校さ行ってがら笑われでなあ。担任の先生も、『スガズ、おめえ、4月生まれだらば、シガツが本当で、スガズっつうごどはねえべ』って。おら同級生かて死んたげ笑われだもんだ。なあ、おがしいべ」
そう言ってスガズは笑った。それからスガズは、村にもう1人「スアシ」という名前のおばあさんがいると言い、こちらは12月生まれで、師走を読み違えた結果であることを教えた。こうした嘘みたいな本当の話に、彩は腹を抱えて笑った記憶がある。スガズは、そうやって彩をいっとき笑わせてから、
「おらの息子でば、まんずながらまんずで、さっぱり家さもけってこねば、嫁ももらわねばで、まんずまんずゆるぐねでば」
と言った。息子の愚痴を言っていることは何となく分かった彩だったが、「ながらまんず」と「ゆるぐね」の意味がよく飲み込めなかった。
「おばあちゃん、『ながらまんず』ってどういう意味?」
スガズは、ポカンと口を開けてしばらく考えていたが、
「ながらまんずっちゅうのはなあ・・・」
「うんうん」
「ながらまんずだべ」
「はあ?」
「おらの息子みでえなのを、ながらまんずっちゅうんだ」
「・・・」
「ああ、タマヨの息子。誰だっけ? 正夫が。正夫も、まあ、んだな。あれもまあながらまんずだべな」
「ん、ん、ん?」
彩が村の人に方言の意味を尋ねても、決まってこういう問答になった。そして、正確な答えはより深い樹海の闇に入っていくのだった。かくして彩は、それ以上の質問を控えて、後で周平に教えを請うことが常だった。
△このページのトップへ
49『ながらまんず』
「ねえ、スガズばあさんが今日、ミニトマトの苗を持ってきてくれてね」
晩ご飯の支度をしながら彩が言った。
「へえ、スガズばあも、なかなかしゃれたもの作ってんだな」
風呂場で汗を流してきた周平が、白いタオルで頭を拭きながら言った。
「うん、年とるといろいろ面倒くさくなって、そのまま口にポーンと入れて食えるのがいいんだって。こんなふうに」
彩はそう言って口を大きく開けると、揚げたばかりの鶏のから揚げをほお張った。
「あっ、ずるっ。俺にも」
彩は菜ばしでもうひと片から揚げをつまむと、
「じゃあ、この質問に答えたらあげる」
と言った。
「何?」
「いつもの翻訳の問題です」
「ああ」
「おらはスガズっちゅうもんだども」
彩はおどけて言った。
「いいから、早く早く。から揚げ冷めちまう」
「エッヘン! おらはスガズだが・・・」
「だーかーらー」
「おらの息子でば、まんずながらまんずで、さっぱり家さもけってこねば、嫁ももらわねばで、まんずまんずゆるぐねでば」
彩は、スガズの言葉を完璧に再現したばかりか、声色や顔の表情まで似せていた。周平はおかしくなってケラケラ笑いながら手を挙げた。
「はい。何語で訳しましょうか? ハングルもできますよ」
「日本語の標準語でお願いしまーす」
「はいはい、では。ええ、私の息子ときたら何ともなまじっかで、あっ、やることなすこと中途半端でのほうがいいかな。ええ、それで、さっぱり家にも帰ってこないし、嫁ももらわないでいるので、何とも大変な、あっ、大変というよりは、うーん、厳しいとか容易でねえのほうがいいかな。まあ、そんな感じかな。分かった?」
「ながらまんずってそういう意味なんだ。やることなすこと中途半端みたいな」
「うん、たぶんそんな感じかと」
「ゆるぐねって、緩くない、つまり容易じゃないみたいな感じなのね」
「うん、おらも、今日のベゴ小屋の掃除はゆるぐねがったなあ。くそまみれでなあ」
「なっ、るほどねえ」
「はい、ご褒美。はい」
周平は大きな口を開けている。
「なっ、るほどねえ」
彩はそう言って、つまんでいたから揚げを周平ではなく自分の口に入れた。
「あっ、ずるっ!」
「へへっ、ゆるぐねんべ?」
「おい、それ用法違うぞ!」
△このページのトップへ
50『ログゴ』
「彩! 早ぐ包丁!」
スミが急かした。彩は慌てて台所のキッチン包丁をスミに渡した。
2枚の正方形の紙が出来上がった。いよいよこれを一対の『ログゴ』というおぼんに載せ、その上に団子を積み上げるばかりになった。
「さっ、んではログゴ」
スミが言った。全員が彩を見た。
(えっ? ログゴ?)
彩は目をパチクリさせてうろたえた。なべ、やかん、へら、紙、包丁とさまざまなオーダーに何とか対応してきた彩ではあったが、自分でも見たことがない『ログゴ』というおぼんの注文は、彼女の職務範囲を大きく超えるものだった。彩は無言で生つばを飲んだ。やがて、彩を見詰めていた3人の視線は、彩を離れて各人をスクランブルに行き交った。数秒の沈黙があった。
どこの家にも当然あるべきはずの『ログゴ』だった。しかし、ここ、銭の城には、ことごとく当然あるべきものがないのだ。ハサミもない家にどうして『ログゴ』などあろうものか。
(うかつだった)
誰もがそう思い、今になってめいめいにそのことを悔やんだ。最も肝心なところでの最も致命的な手抜かりだった。殊に団子リーダーのスミは、自分の犯した過失を強烈に恥じた。スミの顔色が青ざめた。
「あ、あ、彩。今、な、な、何時だ」
スミが震える声で聞いた。
「12時48分です」
慌てて彩が答える。
「ぼ、ぼ、坊主、何時に来る?」
「あっ、はい。1時だからあと12分かと」
「あいい、すかだにゃ。時間ねえべさ」
のり子が、彼女にしては少しだけ取り乱した調子で言った。かなりの緊張感が作業場を満たしている。
「おら、取りさ行ってくる」
マチが言った。だが、もう誰も取り合う余裕がない。
「あ、彩! しゅ、周平呼んできてけれ!」
「あっ、はい!」
彩は壁の時計をチラッと見やって、バタバタ座敷に駆け出した。
「あいい、あいい」
のり子が腰をもぞもぞさせながら言う。スミは何かを思い詰めたような青ざめた顔で、じっと目を閉じている。
「周ちゃん!」
マチが叫んだ。
「何だい? スミばあ」
周平の声にスミはカッと目を開けて、
「周平! た、た、頼む。おらの家さ行って、ロ、ロ、ログゴ取ってきてけれ!」
と言った。
「分がった」
「台所の上の棚さあっから」
「3分で戻る」
ただならぬ空気を感じた周平は、そう言って外へ飛び出した。
「は、は、早ぐな!」
スミが後ろから叫んだ時には、そこに周平の姿はなかった。
周平は、赤い漆塗りのログゴを2本抱えて本当に3分で戻ってきた。坊主到着まで残り10分を切っていた。団子チームは、いよいよその真価が問われる正念場を迎えていた。
「マチ、おめえ団子並べれ!」
スミが意外なことを言った。
「えっ? スミ、おめえやるって言ったべさ」
マチは釈然としない。
「いいがら、おめえさ譲る」
「あいい、何だどや。おめえのほうが上手いべや。おらしばらぐやったごどねえもの」
(ど、どうしたの? もう時間がないのに。あっ、スミばあちゃん手が震えてる。この人、意外と気が小さいんだあ)
彩は思った。その時、敢然としてのり子が言った。
「俺さ任せろ!」
のり子は団子を両手でわしづかみにすると、ログゴの上にどんどん並べていった。スミとマチはぼう然とその様子を見ているだけだ。
(未亡人倶楽部の会長は、やがてこの人になるかもしれない)
彩は思った。
最初の1段目と2段目の三角はまあ何とか上手くいった。しかし、団子は3段目になってコロコロと崩れ出した。
「あいすかだにゃ、崩れだど」
のり子が言った。
「あいい、ちょっと、こっち高ぐねえがい?」
マチが言った。
「なんもだ、こっち高えべ」
「あれでねえが、少しやっこがったんでねえがい。ほれ、下のほう、つぶれでるもの」
マチとのり子の言い合いを、ジッと聞いていたスミがついに口を開いた。
「彩! ハナガミ持ってこい!」
(ハナガミ?)
またしても突然振られた意外な注文に、彩は狼狽しながら頭をフル回転させた。
(もしかして鼻をかむ紙かしら。つまり、ティッシュペーパー?)
彩は鼻をかむポーズをとってみた。
「んだ、早ぐ!」
スミが急かした。
「ティッシュですね?」
「んだでば。チッシュ!」
彩はティッシュペーパーの箱をスミに渡した。
(どうするんだろう?)
みんなが見守る中、スミはティッシュペーパーを2〜3枚取り出して丸めると、低くなってるところに詰め始めた。
「中のほうだがら分がらねべ」
スミはそう言って、その上に団子をどんどん重ねていった。
「スミ、まさが・・・」
マチは目を丸くしている。のり子も、
「あいい・・・」
と言ったまま黙ってしまった。
「いいがら、時間ねえんだ!」
スミは1脚目のログゴを完成させると、もう一つのログゴに団子を並べ始めた。1段目、2段目が終わり、3段目も間もなく終わろうとしていた時だった。
「ありゃ?」
スミの手が止まった。団子の在庫が残り2つになったのである。完成まで5〜6個は確実に足りない。
(あー、やっぱり・・・)
ひょっとしたらこんなことになるのではないかと思っていた彩の予感は的中した。
「ひとつ、ふたつ余計にあればよがったなあ」
マチが残念そうに言った。
「ほれみろ、らも、少しちっちゃいなあど思ったんだよ」
のり子が敵を取ったように言った。
(逆、逆、逆。あなたのサイズだともっと足りなくなってたんですよー)
ピーッ!
その時、ちょうどタイムリミットを知らせる壁時計の電子音が鳴った。全員がその音の方向を見た。にわかに緊張が走り、スミの顔色はもう一段青みを帯びた。
「鼻紙丸めで入れろ。鼻紙丸めで入れろ」
スミが手にペッとツバを付けて、ティッシュペーパーを団子のように丸め出した。のり子は、
「あいい・・・」
と言いながらもティッシュの箱を手に取った。マチは最後まで、
「なんぼなんでも、それだばうまぐねえべ」
と言っていたが、
「中のほうさ入れれば、分がらねえがもなあ」
と、無理矢理自分を納得させると、緩慢な動作で自らも鼻紙を丸め出した。
彩はあっけにとられてこの様子を見ていた。何か見てはいけないものを見ているようで、できればこの場から中座したい衝動に駆られた。
1時4分。かくして、上げ底ならぬ上げ鼻紙による団子は完成したのである。
(かなめばあさんは、この中に6個の「なんちゃって団子」があることに気が付いて怒るだろうか。いや、きっと「スミだぢのやりそうなごどだわい」と言って笑ってくれるに違いない)
彩はひそかにそう願った。
スミは、団子を載せたログゴを両手に持って枕机に向かった。持っていく途中でのアクシデントをみんなは心配して手伝おうとしたが、その役だけはどうしても自分でなければならないという無言の強いオーラをスミは放っていた。みんなは、仕方なくただ見送るしかなかった。
後ろから見るスミの格好は、これぞ絵に描いたような『ザリガニ』だった。左右の手に握られた赤い漆塗りのログゴは、まさにザリガニのハサミそのものだったし、ハサミの先からはブクブクと白いアブクまで吹き出しているというかなり精緻な演出までなされていたからである。
△このページのトップへ
51『コブ』
「貴志さんから聞きました。そんなにお悪いんですか?」
一三の取り調べを終えた美樹に郁子が聞いた。目を移すと、取調官は難しい顔に一層困惑の色を浮かべジッと考え込んでいる。
「うん」
心ここにあらずの美樹が言った。
「そうですかあ」
「・・・」
「私も何かお手伝いすることがあれば、おっしゃってください」
郁子はそう言って、近くにいるはずの洋を見やったが洋はいなかった。
チーンッ!
洋はまた枕机の鈴を鳴らしていた。
その音に反応して、座敷に居合わせた20人ほどの人が一斉にそっちの方向を見た。
チーンッ、チーンッ、チーンッ!
「こらっ、洋!」
郁子は美樹に愛想笑いを残して、慌てて洋の元へ走った。
「お坊さん、そろそろですね」
腕時計を見ながら二所谷は貴志に言った。
「ええ」
貴志も柱時計を見た。
その時、腰を曲げて目の前を横切る者があった。頭を畳スレスレにつけながら、万歳をした両手には足の長い赤い塗りのおぼんが握られ、おぼんの上には5段重ねの団子がうず高く積まれていた。
「ああ、できたんですねえ。いやあ、立派なものだ」
二所谷は深く感心してそれを見ている。
その様子を目にした源蔵は、慌ててスミの元にやってくると、
「本当に、チッ、大難儀掛げますた」
と礼を言って、スミの進路を開けながら枕机のところまで先導した。
貴志も礼を言わなければと思い、スミの元に駆け寄った。
「おい、ボンズ。どげろ!」
源蔵は、しつこく鈴を鳴らしている洋を叱った。
「洋、こっちに来なさい!」
洋は、スミが持っている団子を興味津々で見詰めながら、郁子に手を引っ張られて引きずられるように退場した。
スミは枕机の前に立ち止まると、曲がった腰をいったん伸ばし、それからいんぎんにお辞儀をした。
「いやあ、スミさん、本当にどうも、立派な・・・」
貴志がお礼を言おうとした時だった。
ガヅッ!
(あっ!)
バラッ、バラバラバラッ・・・。
(ああーっ!)
お辞儀をしようと頭を下げたスミは、机の角にしこたまおでこをぶつけた。痛そうな鈍い音だった。その拍子に、団子はログゴから落下し枕机や畳の上に転がった。転がった団子を源蔵と貴志は慌てて拾おうとした。
「やめろ! 触るな!」
スミは、ギッとにらみを利かせて2人に言った。ひるんだ2人に向かって、スミは振り返ってさらに言った。
「シッ! あっちゃ行ってろ! シッ!」
スミはおでこの痛みも忘れて、ログゴに団子を積み上げ直している。貴志と源蔵は遠巻きにその様子を眺めるしかない。
泡を食って並べ直された団子は、当初の巧妙な細工が失われ、なんちゃって団子が随所に露出する結果になってしまった。しかし、それでも何とか自分の使命を果たし終えたスミは、みんなに賞賛されながら無事本拠地に戻ることができたのだった。
「あいい、スミ。ごぐろうさん!」
マチが帰還した英雄に言った。
「無事、納まりましたか?」
彩が聞いた。
「まあな」
スミが少し沈んだトーンで言った。
「スミ、おめえ、なした? ナジギさコブでぎでるど」
マチがスミの顔をのぞき込んで言った。
(わあ! ホントだ。すごいコブ!)
彩も驚いてスミを見た。
「何でもねえ」
スミはそう言ってそっぽを向いた。
「あいい、冷やせ、冷やせ! 彩ちゃん、水っこ」
マチが言った。
「はい!」
彩は慌てて水道の蛇口をひねった。
おでこのコブをまじまじと見詰めていたのり子がボソッと言った。
「このっくれえの・・・団子だばいがったんだよ」
△このページのトップへ
52『イージー』
坊主は、予定の時間になってもなかなか現れなかった。
「遅いですねえ」
二所谷は、時計を見ながらソワソワしている。時刻は1時20分を回って、集まった村人たちもざわめき始めていた。その中で、ひときわイライラしていたのは源蔵だった。彼は、玄関から身を乗り出して外を見やっては、チッチッチッチッを連発した。彼は、イライラした顔で貴志の元に歩み寄ると、
「チッ、ちゃんと連絡したんだべな」
と言った。
「あっ、はい。ちゃんと1時って、何度も伝えてあります」
貴志は、「何度も」に力を込めてそう言って隣の一三を見た。
一三は昨日のことを思い出したのか、苦々しい顔で3回大きくうなずいた。
「電話してみろ。寺さ」
源蔵が言った。
「はあ・・・」
「チッ、手違いってごどもあるべ」
いつの間にか源蔵の脇に寄り添っていた二所谷も、「うん、うん」とうなずいている。
「ああ、はいい・・・」
貴志は渋々立ち上がろうとした。その時だった。
タタタータータータタタータータ、タタタータータータタタータータ。
玄関の向こうから、聞き覚えのある着信音が聞こえてきた。その音は、セミの声に紛れて聞き取れないほど小さく遠くで鳴っていたが、貴志と一三の耳には、いまいましさの記憶を伴ってはっきりと残っている旋律だった。
(へっ、イッツアスモールワールドだとさ)
貴志は、全身の力が投げやりに脱けていくのを感じた。一三は、にわかに体を硬くして口をへの字に結んだ。
「チッ、おい、早ぐ!」
源蔵が急かした。貴志が落ち着き払って言った。
「来ましたよ、坊主」
源蔵と二所谷が同時に後ろを振り返った。玄関には誰もいない。
「チッ、誰もいねえべよ」
源蔵が言った。
「ええ、誰もいませんねえ」
二所谷も相づちを打った。
「外で電話してますよ。もうすぐ来ます」
貴志が言った。
「ええ、すぐに来ます。賭げでもいいです」
今度は一三が強く相づちを打った。
源蔵と二所谷は、超能力者でも見ているかのようにポカンと顔を見合わせた。
「・・・分ーかったって。あーい、あいあい、あーい」
彼らがもう一度振り返った時、玄関には一三たちの予言通り坊主がいた。坊主は、耳にショッキングピンク色のケータイを当て、視線を上方斜め45度に泳がせながら涼しい顔でフワフワと揺れるように立っていた。
荘道が到着したことで、集まった村人たちもにわかに居ずまいを正し静寂が座敷を満たした。荘道という林峰寺の若い坊主を実際に見るのは初めてだった村人の多くは、彼の一挙手一投足に食い入るような視線を送っていた。
枕机の前に座った荘道は、20分も遅れたことに全く悪びれる様子もなく、モスグリーンのかばんから白木の位牌を取り出すとそれを遺影写真の前に置いた。白木の位牌に貼られた白い紙には、『梅室妙要大姉』と、かなめの戒名が書かれていた。
(イージーだな。これが10万円なんだとさ)
貴志は、梅松の梅の字を取り、かなめを要と漢字にしただけの、いたって定型的な戒名を見てそう思った。
一三は、戒名もさることながらその筆跡に注目していた。一見しては分からないが、位牌に貼られた紙に書かれた戒名の文字は、直筆ではなく、直筆を装ったパソコンの毛筆書体だった。他の人の目はごまかせても、一三の目はふし穴ではなかった。一三は、またも苦々しく坊主の後ろ姿をにらんだ。
△このページのトップへ
53『アバの悪態』
その時、台所のほうから聞こえてくる話し声があった。それは、読経前の静寂の中、はっきりと内容が分かるボリュームで座敷中に響き渡っていた。
「マチ、貴志のアバ見だが。おらだぢさ、ありがどうでもごぐろうさんでもねぐ、プイッてなもんだったべ」
「ああ、ほんとだな。知らんぷりして行ったっけなあ」
「とんでもねえ、アバだなや」
「ああ、驚いだアバだ」
一三がまっ先にそっちの方向を見た。集まっていた7割ぐらいの人たちも、めいめいに声の方向を見た。周平の隣に座っていた彩は激しく焦った。
(うわあ、どうしよう。筒抜けじゃない!)
慌てて彩が向けた視線の先で、貴志も隣に座っている美樹の顔をチラッとのぞき見ていた。美樹は、心ここにあらずのまま、ただうつむいているだけだった。
一三はスッと立ち上がると、着座している人たちの間をかいくぐって台所に向かった。
「団子作ってくれって言うがら、来てやったのによう。あの態度はねえべや。なあ、のり子」
「んだなあ、ペコンとでもすればいいべなあ」
「あのアバ、いってえ何のまねだべ」
「まったぐ、あのアバ、アバ、アバッ? あ、あ、ありゃ? あいい、イズゾーしぇんしぇ。どんもどんも」
一三に気付いたのり子が言った。
「皆さん!」
「あん?」
「あっつまで声がつづぬげです!」
一三は厳しい顔で、声をひそめながら言った。
「あいい、あっちゃ聞こえだのがい!」
マチはびっくりしてさらに声が大きくなった。
「しっ!」
一三は人差し指を口に当てると、
「明日、僕の妻も手伝いに来ます。妻にも言っておぎますが、いいですか、これですよ、これ」
と言って、もう一度人差し指を口に当てた。
チーンッ!
読経が始まった。
一三に注意されたスミたちは、さすがにバツが悪くなってちょっと黙ったが、そのうち、
「んだってほんとのごどだものなあ」
「んだんだ」
「ほんとにひでえアバだもの」
などと小声でブツブツ言いながら、散らかった作業場を片付け始めた。
△このページのトップへ
54『ライト感覚』
チーンッ!
荘道の読経はあっという間に終わった。向き直った荘道は儀礼的に頭を下げ皆も一斉に頭を下げたが、ひと頭だけ下がらない頭があった。ウーパールーパーの頭だった。
「お逮夜は何時?」
荘道は立ち上がって貴志に聞いた。
(だから、だから、だーかーらっ!)
貴志は、何だかどうでもいい気持ちになった。口をきくのさえ嫌になった。貴志は、「5時」と言う代わりに、荘道の顔の前で右手をパーにした。
「あっ、5時ね。リョーカイ!」
荘道はそう言って、自分も右手をパーにするとうれしそうにニッと笑った。荘道はそのまま手を挙げて、貴志とハイタッチをする勢いまで見せた。
(こいつとは、こういうコミュニケーションのほうが上手くいくのかもしれない)
貴志は思った。
(相手を坊主と思うんじゃなく、例えば、ディズニーランドで一緒にスプラッシュマウンテンに乗るような、そんなライト感覚で)
貴志は一瞬そう思ったが、すぐに考えを改めた。
(いやいや、冗談じゃない。だったら、なんでこっちがこいつに大枚なお金を払わなければならないんだ!)
荘道は例によって例の通り、ケータイを片手にフワフワと帰っていった。
△このページのトップへ
55『一三先生の出番』
出棺の時間が大きく遅れてしまったことに二所谷は慌てていた。彼は、思案顔で貴志の元へ来ると、
「火葬の時間まであと5分しかありません。困ったなあ。1枚増やしてもらえますか?」
と言った。
「えっ?」
「例のあれです。彼ら結構時間にうるさいんですよ」
(何のこっちゃ)
貴志は二所谷が言っている意味が分かったが、取り合う気にもならなかった。
「ええ、では出棺に当たって、棺桶の持ち手を発表すまーす!」
大きな声は一三だった。一三は、自分の書いてきた半紙を広げながら、ここが自分の真骨頂とばかりにテキパキと的確な指示を出している。
「宮下裕太郎さーん、星野周平さーん。前を持ってくださーい!」
周平と裕太郎は、呼ばれて棺桶の前のほうに進み出た。
「宮下常吉さーん、坂下源蔵さーん。後ろを持ってくださーい! 斎田道秋さーん、野々村昭介さーん。お2人は、中のほうを支えてあげてくださーい!」
源蔵と常吉は前に進み出たが、斎田道秋と野々村昭介が出てこない。
「斎田さーん、野々村さーん。お願いすまーす!」
(そう言えば、粉を買いに行ったまま道秋夫婦は戻っていない。野々村昭介たちもまだだ)
貴志は一三の元に行って2人が不在であることを告げた。一三はうなずいて、
「では代わって、その代役は宮下永幸さんと高津末之助さんにお願いすまーす!」
と言った。彼は交代要員まで考慮していたようだった。
持ち手がそれぞれ配置に着いたのを確認した一三は、さらに、位牌、遺影写真、骨箱、花、団子などの持ち手を次々に発表した。休憩用のお菓子や飲み物の持ち手に至るまで、それは実に周到なものだった。
「最後に、ゴミ袋は袋原伸之助さんにお願い致すまーす!」
この人選には、どうも『袋』が絡んでいるようだった。
(二所谷さん、悪いが君のお株は完全に奪われたようだな。こういうことをさせたら一三先生にかなうものはいないんだよ)
貴志はそう思って、二所谷がどんな顔をしているか確かめたくなった。貴志はチラッと二所谷を見た。
(あれっ?)
当の二所谷は相変わらず思案顔のまま、まだ何かブツブツ言っている。
「二所谷さん、棺桶出ますよ!」
イライラした声で貴志が二所谷を急かした。
二所谷はそれには反応せずに、おもむろに貴志の耳元に顔を近付けるなり小さな声でこう言った。
「やっぱり5にしましょう。5なら何とかなる」
そして、コッソリ右手の指を広げて貴志の顔にかざした。
「二所谷さん! 早く霊柩車開けて!」
貴志はたまらずに怒鳴った。
かなめの棺を載せた霊柩車は予定より30分遅れて、長い警笛を残して生家を後にした。
△このページのトップへ
56『野々村高太』
その頃、火葬場には10名ほどの人たちが霊柩車の到着を待っていた。仕事場から駆け付けた村人たちに混じって、そこには野々村やえ夫婦と息子の高太がいた。
「あんたの顔知ってるのって、村のばあさんたちだけなんでしょ?」
やえが言った。昭介は、フィルター寸前のところまで吸っていたたばこを、けちくさくつまんで地面にこすりつけると、ボラ顔を上げて、
「ああ、分かんねえさ。それにあのババアたち、もう大方くたばってるって」
と言った。
「ならいいけど。あたし嫌よ。もうころごりだわ」
火葬場から延びる蛇行した道路を見下ろしながらやえは無表情に言った。
「おやじ、受付で何て言えばいいんだ?」
高太が言った。
「あっ? 『この度は、白たび黒たび』って言えばいいんだ」
昭介が答えた。
「ははっ、白ヤギさん黒ヤギさんみてえだなあ、おやじ」
高太は、イチローのバッティングフォームをまねながらバカづらで笑った。
「なあ、受付のノートには名前を書くんだろ?」
高太がまた聞いた。
「ああ、あれはホウメンチョウっていうんだ」
「へえ、シチメンチョウみてえだな、おやじ」
「書く時は3人一緒に行かないで、1人1人ずらして行ったたほうがいい」
昭介が言った。
「え? どうしてだい? おやじ」
「こういうもんは、『ああ、わざわざご丁寧に、何度も何度も』って思わせることが肝心なんだ。ホウメンチョウはあとで遺族が必ず見るもんだからな。『野々村』って文字がたくさんあればあるほど、先方の印象が強くなるって寸法よ。いいか高太」
「なるほど、バッキシずらしたほうがいいってことだな」
「ああ」
「じゃあ、名前もバッキシ大きく書いたほうがいいな」
「ああ、そうだ」
「バッキシ、リキ入れて書いたほうがいいな、おやじ」
「ああ、それがいい。高太、お前、この頃少し知恵が付いたようだな」
昭介のガラスべんちゃらに気を良くした高太は、子ボラ顔をホゲホゲさせた。
学校の勉強がまるでダメだった高太は、高校を中退して板金工になった。しかし、それも半年もしないうちに飽きて、それからは家に寄生しながらアルバイトをやったりやらなかったりの、ブラブラした『ながらまんず』な生活を送っていた。
「おやじ、おいらバッキシいい考えあるぜ」
「何だ?」
「へへ、あとで教えてやっからよ」
そう言って高太は小ボラ顔でニヤニヤ笑った。
「あっ、来たわ」
遠くに金ピカの霊柩車を見つけたやえが言った。霊柩車の後ろには十数台のクルマが、ヘビのようにくねくねと続いていた。
△このページのトップへ
57『カシラの頭』
間もなく、かなめの遺体を乗せた霊柩車は火葬場に着いた。荷物を乗せて軽トラックを運転してきた周平は、それを持ってクルマを降りると、霊柩車から棺桶を下ろす作業に加わった。
二所谷は家に残って祭壇の設置をしていたので、それに代わって源蔵が葬儀社さながらに手際よく火葬場の祭壇に飾り付けをしていた。黙々と水を得たように振る舞う源蔵の口からは、不思議なことに「チッ」は全く出なかった。
休憩所のほうは、大地と郁子が中心になってお菓子や飲み物の配膳をしていた。配属場所が配属場所なだけに、当然のことながら、
「こらっ、洋!」
という叱り声が途切れることはなかった。
台車に乗せられたかなめの棺は、二所谷が言っていた白い作業服を着た3人の男によって、いたって公務員的に2機ある火葬炉の前に運ばれていった。
3人共、『千と千尋の神隠し』に出てくる「オイ」としか言わない『カシラ』のような顔をしていた。
貴志は二所谷の言葉を思い出していた。
(彼らは白い作業着というか制服を着ています。脇には大きな外ポケットが付いています。だから案外入れやすいんですよ)
二所谷はそう言った。
(アレをやるのは、恐らくこのタイミングなんだろうな)
3人のリーダー、つまりカシラの頭と思われる年配の男の制服を貴志はチラッと見やった。確かに「ここにソッと入れてください」と言わんばかりに、ノーフラップの大きなポケットが大きく口を広げて付いていた。
(今まで、あのポケットにどれだけの千円札が不正に投入されたことだろう?)
貴志は思った。
(でも、彼が収賄罪で捕まる可能性はほとんどゼロだろうな。だって、彼は何の要求もしていないんだから)
カシラの頭のすすけた顔を見ているうちに、貴志はカシラのつぶやきがこんなふうに聞こえてくるのだった。
(俺はこの年まで35年間、死臭漂う火葬場で、毎日毎日朝から晩まで、ただひたすら焼いてきたのだ。しかもパンやうなぎを焼くのとはわけが違うぞ。こっちは、れっきとした人間の、それも死体なんだぞ!)
貴志はカシラの頭が不憫に思えてきた。
(世の中じゃ3K仕事が毛嫌いされているようだが、こっちのKは『気持ち悪い』『気色悪い』『気味悪い』のK、ついでに『臭い』『きもい』も入れれば5Kなんだぞ。なのに、危険手当も悪臭手当も、気持ち悪手当さえなく、給料はほかの事務役人とおんなじだなんてどう考えてもおかしいだろうが!)
貴志は、そうだそうだと思った。そして、だんだん世の中の理不尽さに怒りが込み上げてきた。
カシラの頭はポケットに手を入れながらこう思うだろう。
(おっ、何だこれは。また今日も入ってたぞ。そうか、これはお仏様から俺へのお布施に違いない。うん、きっとそうだ)
そして、ついでにこんなことまで考えるだろう。
(今日はこれで焼酎でも買って、焼き鳥をつまみに一杯やるとするかな。ありがたいお布施なんだから。そうだ幸子にも何かお土産を買っていってやろう。何がいいかな? 焼き物つながりでタイ焼きがいいかな? 幸子は甘いもんが好きだから)
貴志は、カシラの頭の幸せな家庭生活を想像して微笑ましくなった。
(だが・・・)
貴志はここでハタと我に返った。
(だが、俺の行為はどうだろう。『刑法198条』つまり、公務員に対して財産上の利益を供与する行為に明らかに該当してしまうではないか! これはれっきとした『贈賄罪』なのだ!)
貴志は激しく狼狽しながら、自分のズボンのポケットをまさぐった。二所谷の提案を心の中で侮蔑しながらも、貴志はしっかりと千円札を5枚用意していた。
カシラの頭は、急に何かを思い出したように持ち場を離れると、脇の暗い通路のほうに消えた。
(あっ! もしかしたらこのタイミングなのかもしれない)
貴志は、心臓がバックンバックン脈打っていた。脂汗が流れ体が震え出した。
「どしたの」
隣で美樹がボソッと聞いた。
「あっ、いや」
貴志の足がガタガタ震えている。
(初めて万引きや痴漢やスリをする時って、こんな気持ちなんだろうか)
貴志は、自分にはとてもできないと思った。
カシラの頭は間もなく戻ってきた。
「喪主さん」
彼は煙焼けのしゃがれた声で言った。
「はっ、はい!」
貴志は自分が痴漢で、それを見とがめられた時のように狼狽した。声が上ずっていた。
「よろしいですね」
「はっ、はい!」
カシラの頭が、カシラの子分の1人に合図を送った。カシラの子分が手前の火葬炉のボタンを押そうとした。
「ゴホン!」
カシラの頭が咳払いをした。カシラの子分が手を止めてカシラの頭を見た。カシラの頭が首を横に振った。カシラの子分は奥の火葬炉のボタンを押した。
ギーン、ガダン!
物々しい音がした。カシラの頭がもう一度脇の通路に消えた。
(これが、恐らく最後のチャンスなんだろうな)
貴志はそう思ったが、追い詰められて観念した犯罪者のようにもう一歩も動けなかった。
カシラの頭はしばらくして戻ってくると、
「では」
と言って、貴志の顔をチラッと見た。
「最後の」
と言って、もう一回念を押すように貴志に視線を送った。貴志は目を伏せた。
「お別れになります」
グゥオーン、ゴドゴドゴド・・・。
火葬炉の扉が開いた。
かなめの棺を載せた台車が奥の火葬炉に送り込まれ重い扉が閉まった。何人かのすすり泣く声がした。
(かあさん、上骨でなくても許してくれるよな。並骨でもいいよな)
貴志は手を合わせながらそう願った。一方美樹は、全く違うことを考えていた。
(ジャム・・・)
手を合わせ深くうつむいた美樹の目から涙が堰を切ってこぼれた。村人たちはそんな美樹を見て、目を丸くしたり、訝し気に首を傾げたりしたが、中にはもらい泣きする者さえあった。
△このページのトップへ
58『白たび黒たび』
棺桶が火葬炉に収まるのを確認した周平は、入り口に折りたたみ式のテーブルを出して、急いで受付の準備に取り掛かった。テーブルの上に2冊の芳名帳を並べ、ペンを4本置き、段ボールに入った会葬御礼を20個分、白い紙袋に入れた。
「この度は、白たび黒たび」
周平が準備を終えたのを見計らったかのように、まずやってきたのは野々村昭介だった。昭介はいんぎんに周平に頭を下げると、一番太いサインペンを持ってまっさらな紙の上にペン先を置いた。
ボキッ!
(あっ!)
いきなりペン先が折れた。昭介は、折れたペン先をいまいましげに見やってから、今度は別のペンを手に取って名前を書いた。大きな下手くそな字だった。
彼は、猪首のボラ顔を持ち上げて周平にもう一度頭を下げると、チラッと会葬御礼の入った袋のほうを見た。
「あっ、すみません」
周平は慌ててそれを渡した。昭介はそれを受け取ると、ゆっくりと祭壇のほうに向かって歩き出した。
△このページのトップへ
59『高野辺貞幸』
続いてやってきたのは、高野辺貞幸という61になる独身の男だった。今ではそういうことはないが、昔はてんかん持ちは結婚できないとか、運転免許が取れないなどと、まことしやかに言われていた時代があった。
てんかん持ちの彼は、中学を出ると必死に自分の働き口を探した。そして、屠殺という職業を選んだ。選んだというより、当時はそれぐらいしか選択肢がなかったと言っていい。
周平が小さい頃、村には豚を飼っている家が結構あって、豚の餌にする『ジョミズ』という、家庭で出た野菜や魚の生ゴミを、一斗缶を2つ吊るした肥え桶のようなものを担いで毎日集めにくる人が何人かいた。貞幸も、屠殺をする傍らジョミズ集めもしていた。
「ジョ、ジョ、ジョミズねーすかあ?」
どもった声で貞幸が叫んだ。貞幸の声は大きく、周平の家の土間を伝って裏の畑までよく響いた。
「あるあるー、ちょっと待でえ!」
周平の母、さえ子が畑から呼び止めた。さえ子が小走りに流しに行き、残飯のバケツを持って現れた時、貞幸はジョミズ桶を肩から下ろし、飼い犬のズロと遊んでいた。ズロはあまり人に懐かない犬だったが、不思議と貞幸にはよく慣れ、仰向けに足を投げ出し白い腹を出してじゃれていた。
「あり、あり、あり、ありがど」
さえ子に気付いた貞幸が礼を言った。貞幸は、バケツを一斗缶の中にひっくり返した。
「おっ! キン、キン、キン、キンキだな!」
缶の中をのぞいた貞幸が驚いて叫んだ。
「あん?」
さえ子は、初め意味が飲み込めなかった。
「キン、キン、キン、キンキの、カッ、カッ、カッ、カッシラあるっちゃ、ほれ!」
貞幸は、普段でも声が異常に大きかったが、驚いた時はより一層ボリュームが上がった。
「あー」
ようやく意味を理解したさえ子は、ニッコリ笑って、
「昨日、高津の家で祝儀あったべ」
と言った。
「まさ、まさ、まさ、まさみづ。ケッ、ケッ、ケッ、ケッコンしたんだどな」
「うんだ。祝儀の膳こさキンキ付いでだんだど。とうちゃん持ってきてみんなで食ったんだ」
「わあーっ! キン、キン、キン、キンキ、クッ、クッ、クッ、食いでえなあ」
貞幸は大きな声でそう言うと、ジョミズ缶の中をうらやましそうにまたのぞいた。さえ子は、そんな貞幸を不憫に思い、
「貞幸、おめえさ別のキンキけっからな」
と言って立ち上がると、冷蔵庫からキンキに似た赤い魚を持ってきた。
「これはキンキではねえが、おらだぢ庶民にとってはキンキど一緒だ。アガウオっつんだ。これ持っていって食え」
「おう、おう。キン、キン、キン、キンキ、キンキ!」
貞幸は飛び上がらんばかりに喜んで、ズロに、
「ほれっ、ズ、ズ、ズ、ズロちゃん。いいべ、いいべ」
と言い残して、小躍りしながら帰っていった。
貞幸はそれから、ジョミズを集めに来るたびごとにきな声で、
「キン、キン、キン、キンキ、ウッ、ウッ、ウッ、うめがったなあ!」
と、さえ子だけでなく周平たちにも満面の笑みで言うのだった。
それから3年後、さえ子がガンで亡くなった時、貞幸は大きな本物のキンキを2尾持って葬儀にやってきた。貞幸は、キンキのような大きな目から涙をボロボロ流して、
「キン、キン、キン、キンキ、ウッ、ウッ、ウッ、うめがったなあ!」
と言って、さえ子の遺影の前で手を合わせた。
貞幸は心の優しい男だった。たとえそれが職業とはいえ、生き物を殺生することが貞幸にとってどんなにつらかったことだろう。周平は幼心に「差別」という2文字を心に刻んだ。
今では、村で養豚をしている家は1軒しかなくなり、貞幸はもう屠殺の仕事をすることもなくなった。彼は年老いた母親の面倒を見ながら、春夏は、周平と同じ牛舎の掃除や田畑の手伝い、秋冬は、薪割りや年寄りの家の屋根の雪下ろしといったよろず仕事をしながら、貧しくも堅実な生計を立てていた。
周平たちが愛宕村に来て初めて迎えた冬は豪雪だった。屋根には1メートルもの雪が積もっていた。ある朝貞幸は、滑らないように靴底をわらで縛った長靴を履いて玄関の前に立っていた。
「ユッ、ユッ、ユッ、雪下ろして、ケッ、ケッ、ケッ、けっから」
そう言って屋根に上った貞幸は、3時間以上もかけて屋根の雪下ろしをしてくれたのだった。中でお茶を飲むように勧めても、
「ヨッ、ヨッ、ヨッ、汚れっから」
と言って、貞幸は入ろうとしなかった。お礼に缶詰を幾つか渡した周平たちに、貞幸は満面の笑みを浮かべて、
「アッ、アッ、アッ、ありがどなあ」
と言った。
「コッ、コッ、コッ、このたびは」
貞幸はそう言うと、懐から香典袋を出して周平に渡した。
(あっ、そう言えば、さっきの人香典もらってなかった)
周平は、しまったと思った。
「貞幸さん、どうぞ」
と言って周平が会葬御礼を差し出すと、貞幸は、
「ゴッ、ゴッ、ゴッ、ごぐろうさんだな」
と言って少しだけ笑った。
△このページのトップへ
60『プロファイラー星野周平』
それから続けて、村の人が9人香典を持ってきて署名した。
(足りるだろうか?)
周平は、あと9個しかない会葬御礼を見やって、少し不安になってきた。
そこへ見知らぬ女性がやってきた。野々村やえだった。やえは、
「この度は・・・」
と、語尾をモジャモジャにしてそう言ってから、スラスラと名前を書いた。
(野々村? 待てよ。どっかで見たような)
やえは、周平に香典袋を差し出した。周平は会葬御礼を渡した。
また、続々と村の人たちがやってきた。さっきの疑問に答えを出せないまま、周平はにわかに忙しくなった。
(困ったな。あと3つだ。でも、村の人だったら、あとで渡すことも可能だな)
列が途切れたところで、周平は急に尿意を催した。祭壇のほうを見ると、源蔵は完璧に支度を整えたようで、余裕で一番前の席に座っている。周平は源蔵に代わってもらおうと思って、香典袋の束をバッグに入れ祭壇のほうへ向かった。
「あっ、どうも。ご苦労様です」
大地が、後ろから周平に声を掛けた。脇に郁子と、郁子に抱っこされた洋がいた。洋は、口の周りにチョコレートのようなものをくっ付けて笑っている。
(こいつ!)
周平は洋の膨らんだほっぺたをつねった。洋は負けじと周平のほっぺをつねってケタケタ笑った。
「あのう、すいません。ちょっと1分だけ、ここで受付しててもらえませんか?」
周平が言った。
「あっ、いいですよ。何か?」
大地が言った。
「あっ、いえ。ちょっと・・・おしっこ」
照れながら周平が言った。
「チーッコ、チーッコ!」
洋が、周平を指さしてまたケタケタ笑った。周平は洋のおでこを人差し指でギューッと押して、急いでトイレに走った。間もなく周平が用を足して戻ると、大地は周平に向かって、
「1人来ましたよ」
と言った。
「あっ、そうですか。すいません」
「この方です。若い男の人でした」
周平は芳名帳を見た。そこには、ものすごい斜め文字のものすごい巨大文字で、『野々村高太』と書かれていた。
(野々村?)
周平が首をひねっていると大地が言った。
「何だか、白ヤギさんとか黒ヤギさんとか、わけの分かんないこと言ってました」
(はあ?)
「あっ、それから、その方ものすごい筆力で、サインペンを2本も折りました。これです」
と言って、壊れたペンを差し出した。
「それから、この袋をいただきますって言うんで渡しましたが、よかったですか?」
周平は大地に対しては、
「あっ、ええ。ありがとうございました」
と言って礼を述べたが、心の中では、やられたと思った。そして、この野々村と署名した3人の正体を暴きたい衝動に駆られていた。
(もし、3人が一味なら・・・。香典1つで3つの会葬御礼を略奪したことになる。これは、用意周到な組織犯罪と見ていいだろう。特に最後の高太という若い男は相当の知能犯だ。俺の行動をすべて監視していたに違いない。彼は、ほんのわずかな隙をついて行動に出たのだろう。うかつだった!)
念のために、周平は野々村やえの差し出した香典袋を開けてみた。中身は、相場を大きく下回るたったの千円だった。
「じゃあ、僕はこれで」
大地はそう言って祭壇のほうへ消えた。大地におじぎをして周平はまた考えた。
(何か犯罪の匂いがするぞ。でも、香典泥棒は聞いたことがあるが、会葬御礼泥棒っていうのはあまり聞いたことがない。わずか2000円程度の干し椎茸を、何個略奪したところでなんぼのものでもないだろう)
周平はこの犯行組織のプロファイリングを試みた。
野々村昭介→せこい。
野々村やえ→せこい。
野々村高太→知能犯。でもせこい。
これが、プロファイラー星野周平の出した犯人像であった。
△このページのトップへ
61『念仏』
かなめの遺体が骨になるまで2時間ぐらい掛かるということだった。火葬に訪れた人たちは、各自祭壇に水を上げ焼香をして拝んだ。それから、脇に立っている貴志と美樹に頭を下げ弔意を表すと、そのまま祭壇の前に設置されたパイプ椅子に座った。骨を拾う近しい親族を除けば、そのまま帰っても差し支えなかったのだが、村人たちも親族同様に居残っていた。
最前列には、作之進と一三親子、そして源蔵、野々村昭介などが座っており、中程に野々村やえ、後ろのほうには高野辺貞幸ら村人に混じって野々村高太がいた。
(やつら、わざと散らばったな)
FBI捜査官と化した周平は、犯行メンバーの動きに鋭く目を光らせた。
ジャリーン!
その時、祭壇のほうからシンバルのような音が鳴った。
(何だ、何だ?)
周平はもちろん、大地や郁子、ひざの上にいる洋までも驚いて身を乗り出した。
(まさか、祭壇に爆発物?)
捜査官は焦った。周平が現場に駆け寄ろうとした時だった。最前列に座っていた作之進が立ち上がって、ゆっくりと後ろを振り向いた。
「こごで、念仏をやろうと思っての」
作之進はそう言うと、立っている貴志に視線を送って、
「いいかの?」
と言った。
貴志は周りを見回して、村人たちとの間で密約ができていたことを知ると、隣の美樹に視線を送った。美樹はただ沈鬱にうつむいているだけだ。
「あっ、はい」
作之進は、うんと大きくうなずくと一三に合図を送った。一三は立ち上がって、B6サイズの水色の冊子の束を持って、
「この小冊子を1部ずつ取って、後ろの人に回すてくださーい!」
と、先生が試験の問題用紙を配る時のように言った。
冊子の表紙には、『西国三十三所御詠歌』と書かれていた。
ジャリーン!
シンバルのような鉦を鳴らしていたのは源蔵だった。源蔵もひそかに村人たちの密約に加わっていたのだった。
補陀洛や岸うつ波は三熊野の
那智のお山に響く滝つせ
一三が音頭を取って念仏が始まった。一三は、左手で起用に木魚を叩きながらリズムを取っている。村人たちが、それに合わせて御詠歌を詠い始めた。貞幸も、小学生が学校で本読みをさせられた時のように、冊子を両手で掲げ持って一生懸命詠っていた。
「フッ、フッ、フッ、フダラクヤ。キッ、キッ、キッ、キシ、キシ、キシウツ・・・」
とやっている間に、彼はどんどんみんなから遅れていったし、音程もかなり外してはいたが、それでも貞幸は一生懸命詠っていた。貞幸の声は、主旋律を圧倒する絶対的大音量で火葬場の外にまで響き渡った。
一方、一番後ろの隅に座った野々村高太は、渡された冊子を一瞥すると、ポイッと会葬御礼の入った袋の中に放り投げた。高太は御詠歌が始まっても、辺りをキョロキョロ見回したり、貧乏揺すりをしたり、腕を頭の後ろに組んであくびをしたりと、多動性障害児のように落ち着きがなかったが、始まって5分もしないうちに、ボラ口を思い切り開けて寝てしまった。
ジャリーン!
源蔵が、一番終わるごとに鉦を鳴らした。
ふるさとをここに紀三井寺
花の都も近くなるらん
紀の国(和歌山県)の那智山寺から始まり、紀三井寺と続き、美濃(岐阜県)の谷汲山まで、近畿2府4県と岐阜県に点在する33カ所の観音霊場を、奈良時代、花山法皇が巡礼し、その時に和歌を読んで、寺に奉納したことが起源と言われる『御詠歌』は、この北国の田舎の村にも、念仏信仰と共に浸透してきたものと思われる。それが、千年以上の時を超えて、こうして今も詠われていることに、貴志は深い感銘を受けていた。
それにも増して、巡礼経験はもちろん、恐らく西国にさえ言ったことのない村人が、歌の意味の解釈は別にしても、こうして立派に唱和できていること自体に貴志は驚きを禁じ得なかった。
御詠歌は長々と続き、やがて佳境に入っていった。
独り来て独り帰ると思うなよ
南無阿弥陀仏お供で帰るぞ
有り難や有り難舟に乗りそめて
いかなる道も失せぬうれしき
有り難や玉のすだれ巻き上げて
念仏の声を聞くぞうれしき
ここも旅また行く先も旅の空
故郷の土になるぞうれしき
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏
ジャリーン!
念仏は終わった。
かなめは、自分たちの歌を聞きながら安らかにあの世へ旅立ったのだ。村人たちは一様にそう思い、安堵の表情を浮かべていた。どの顔もさわやかに輝いている。貴志までもが、何だか心が浄化されたような神聖な気持ちになった。そして、「念仏はやりません」などと豪語した自分の浅はかさを恥じた。
(汗顔の至りとはこのことだな)
貴志は素直にそう思った。
「念仏も悪くないじゃないか」
祭壇の脇に立っている貴志が、隣の美樹に言った。
「・・・」
「お父さんが病気だってことにしてあるからな」
貴志は厳しい口調でそう言った。
「・・・」
「それでお前が動揺してるってことにしてある」
「・・・」
「そういうことで口裏を合わせてくれ」
「・・・」
「そういうことにしてあるから」
「何で」
「何でって、そう言うしかないだろう」
貴志は語気を強めた。
「・・・」
「ほかにどうやってかばえって言うんだ」
「・・・」
「お前のために言ったことなんだぞ」
「・・・」
「だからお父さんには、葬式に来ないように言ってくれ」
貴志は無言の美樹にくさびを打つようにそう言った。
△このページのトップへ
62『諜報部員』
念仏のためにやってきた村人たちは、おのおの連れ立って帰り支度を始めたが、その中にタマヨと歌子がいた。タマヨは、かの有名な『タメばあ物干し事件』の時、スミにデベソであることをばらされたばあさんだったし、歌子は、最初にかなめに情報を伝えた有能な諜報部員であった。
「歌子、あのツラどっかで見だごどねえが?」
帰りのお焼香をし終えたタマヨが歌子に言った。
「どご、どご?」
歌子は諜報部員らしく、さりげなくタマヨの視線の方向に目をやった。
「あいい、誰だっけや」
タマヨはジッと考え込んでいる。
何食わぬ顔で手あぐらをかきながら、最前列に座っている昭介を歌子は素早く目の端に留めた。歌子はハッとひらめいたように言った。
「ボラブダだ」
「えっ?」
「ボラブダ野郎だでば。あの、物干しの」
ようやく意味の分かったタマヨは、
「あー、あの時のボラだなあ」
と言って振り返ると、昭介の顔をマジマジと見た。
「だども、なしてこごさいるんだ?」
「分がらね」
2人は同時に上体を傾げて昭介を見詰めた。その視線に気付いたのか、昭介はチラッと2人のほうを見ると、立ち上がって素早く休憩所のほうに消えた。それを見て、やえと高太も急いで昭介の後を追った。
「おいおい、子っこのボラもいだど」
驚いたタマヨが言った。
「ほんとだ。子っこボラブダもいだな。うーん、いってえどういうごどだべ?」
歌子の顔がキッと諜報部員の顔になった。
受付の机を片付けながら、もう1人、ジッと3人の動きを監視している捜査官がいた。捜査官は休憩室に向かった犯人一味の行動を決して見逃してはいなかった。
「周平!」
諜報部員が後ろから捜査官に声を掛けた。捜査官はその声に振り返って、
「ああ、歌子ばあか」
と言った。
「今の男誰だ? おめえ分がるが?」
歌子が聞いた。
「ああ、野々村って名前なんだけど、正体は分がらねえ」
周平が答えた。
「怪しいな」
「うん、歌子ばあもそう思うが?」
「ああ、あいづ、昔タメに6万もする物干しつかませだ野郎だど」
「えっ! そういえばボラ顔だったなあ」
村の伝説となった『タメばあ物干し事件』は、当然周平もよく聞かされていた。
「油断するなよ」
歌子が言った。
「分がった」
周平は、香典袋を入れたバッグをしっかりと小脇に抱えた。
「シュッ、シュッ、シュッ、周平」
今度は貞幸が声を掛けた。
「あっ、貞幸さん」
「キョッ、キョッ、キョッ、今日の、ベッ、ベッ、ベッ、ベゴ小屋の掃除、オッ、オッ、オッ、オラやっておぐがら」
貞幸が言った。<第1部第2章完>(まだまだ続きます!)
△このページのトップへ
●『第1部第3章』へ続く